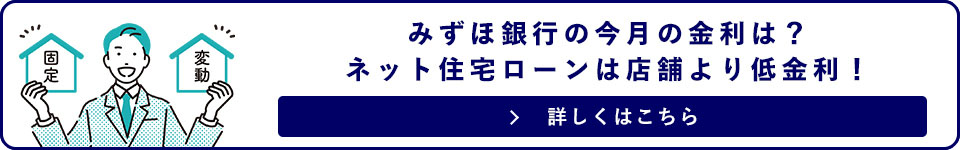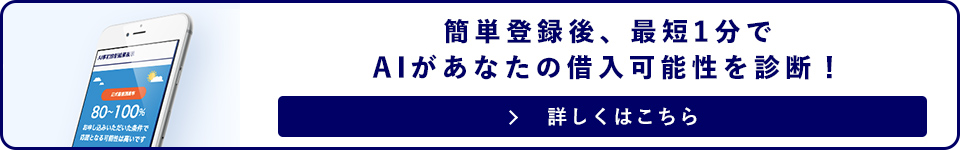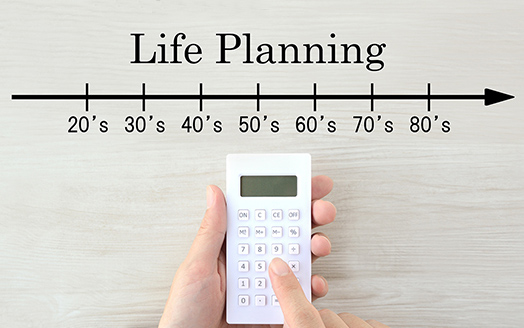住宅ローンのおすすめの返済方法は?種類や選び方のポイント
掲載日:2023年10月5日

目次
住宅ローンを返済していく方法には「元利均等返済」と「元金均等返済」の2種類があります。住宅ローンは長期に渡って返済していくことになります。自分に合った方法を選んで、少しでもお得に返済していきたいものです。そこで今回は、「元利均等返済」と「元金均等返済」それぞれの特徴や、メリットやデメリットを分かりやすくまとめてみました。返済方法と借入額によって、月々の返済額や総返済額がどの程度変わるのかも解説しています。合わせてチェックして、ライフスタイルや家族のライフイベントに合った返済方法を考えていきましょう。
1. 住宅ローンの返済方法(返済方式)の種類

住宅ローンの返済方法は、大きく分けると2種類あります。毎月の返済額を一定にして返済していくのが「元利均等返済」で、毎月の返済元金を一定にして返済していくのが「元金均等返済」です。どちらも、毎月の返済に加えて「ボーナス払い」「繰上返済」などの返済方法を併用し、返済を加速することができます。余裕があったら前倒しの完済も視野に入ってきます。それぞれの内容を把握して、返済のスピードアップを検討していきましょう。
元利均等返済のメリットと注意ポイント
元利均等返済とは、元金と利息を合わせた毎月の返済金額を一定にする返済方法です。毎月の返済額が変わらないため、返済計画を立てやすく、急な出費などにも備えられるのがメリットです。ただ、元金均等返済と比べて総返済額が多くなるというデメリットもあります。
元利均等返済で変動金利のプランを利用すると、金利の上昇によって返済額が増えてしまうリスクもあります。そのため、変動金利のプランの多くには「5年ルール」や「125%ルール」など、金利上昇時の負担を抑えるルールが用意されています。
変動金利の場合、通常は半年に1度のタイミングで見直されます。この際に金利変動があっても、5年間は返済額が固定されるのが「5年ルール」です。金利の上昇があっても5年間は家計の影響を抑えられるため、教育や介護などで支出が増えることが分かっている家庭も安心です。そして、5年ルールの適用後、金利の上昇で6年後に返済額が増える場合でも、変更前の返済額から25%以上は増額されないのが「125%ルール」です。
金利動向に不安があっても、着実に返済していきたい方は、このルールをしっかり把握しておきましょう。元利均等返済の注意点をさらに掘り下げたい場合、次の記事をチェックしてみてください。
元金均等返済のメリットと注意ポイント
元金均等返済とは、毎回の返済元金を一定の金額とするもの。返済元金に利息を加えた額面が毎月の返済額になるため、ローン残高に応じて毎月の返済額が変わります。メリットは、元利均等返済に比べて総返済額が少なくなること。返済開始当初は毎月の支払額が高いため、余裕を持って返済していける家庭に向いています。この返済方法は金融機関によっては取り扱っていないこともあります。事前に必ず確認しておきましょう。
ボーナス払いはどんな方におすすめ?
ボーナス払いとは、年に2回のボーナス月に一定額を上乗せして返済するという方法です。ほとんどの住宅ローンでは、契約時にボーナス払いを手続きできます。ただし、ボーナス払いにできる額面には上限があり、「借入額の40%程度まで」と定める金融機関が多くなっています。毎月の返済額を抑えたい方、賞与を確実にもらい続ける見込みがある方におすすめの返済方法です。
住宅ローンのボーナス払いを利用するメリット・デメリット、注意点
繰上返済
繰上返済とは、住宅ローン残高の一部を繰上げて返済していく方法です。まとまった金額が用意できたケースなど、毎月の返済とは別に返済を加速できます。繰上返済の分は元金の返済に充てられるため、それに伴う支払利息をカットできます。つまり、総返済額を減らすことができるのです。
繰上返済には「期間短縮方式」と「期間不変方式(返済額減額方式)」 の2種類があります。「期間短縮方式」は、繰上返済した額だけ、返済期間を短くするもの。繰上返済後も毎月の返済額は変わりません。「期間不変方式(返済額減額方式)」は、返済期間は変えずに、繰上返済した額に応じた割合で毎月の返済額を少なくできるもの。繰上返済は支払う利息を減らしたり、総返済額を減らしたりするのがねらいです。利息の軽減については、「期間短縮方式」の方が「期間不変方式(返済額減額方式)」よりも効果が高い傾向にあります。
繰上返済を考える際に気になるのが、「繰上返済と住宅ローン控除(住宅ローン減税)のどちらを優先すべきか」というポイントです。住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んだ人の所得税や住民税の負担が軽減される優遇措置です。一定の条件に沿って住宅ローンを利用すると所得税が控除される仕組みになっています。
この有利な制度を利用するためには、住宅ローンの返済期間が「10年以上あること」が条件になります。繰上返済によって返済期間が10年未満になると適用外になりますし、住宅ローン残高が減るため、控除額も減少してしまうデメリットもあります。このため、控除の期間中にまとまったお金が用意できるようなら、繰上返済ではなく貯蓄に回すのがベター。控除期間が終了した後、繰上返済を進めて利息を減らしていくのが望ましいでしょう。
住宅ローン控除の適用条件は?新築と中古の違いと制度利用時の注意点
一括返済のメリットと注意点は?
一括返済とは、住宅ローンの返済中に、残債を一括で全額返済することです。返済期間を短縮できるため、支払利息が抑えられ、総返済額も減らすことができます。
ただ、一括返済する額が大きい場合、預貯金など手元資金が一気に減るため、病気やケガなどで急な出費が発生した場合は家計のリスクが高まります。また、住宅ローン控除(住宅ローン減税)を利用している場合、一括返済によって所得税額から受けられる控除がなくなり、税負担が増すことになります。さらに、一括返済することで住宅ローンは「完済」になり、返済中にカバーしていた団信(団体信用生命保険)の保障がなくなります。このため、生命保険などを見直し、新たに加入する必要も出てくるでしょう。一括返済はこれらのメリットとデメリットを天秤にかけ、慎重に検討することが必要です。
2. 自分に合ったおすすめの返済方法を選ぶためのポイント

憧れの物件を購入したら、家族を支える金融資産も守っていかなければなりません。そのためには、自分に合った返済プランを選択するのがベストです。返済方法のメリットとデメリットを比較しつつ、自分に合った返済方法を選ぶためのポイントを紹介します。
住宅ローンを契約する際、元利均等返済と元金均等返済のどちらを選び、ボーナス払いも検討することになります。返済途中に選択できるのが繰上返済です。それぞれの違いとメリット、デメリットをまとめてみました。
住宅ローンの返済方法の比較表
| 返済方法 | 概要 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 元利均等返済 | 毎月の返済額(元金と利息の合計)を一定の金額とする返済方法 | 毎月の返済額が変わらないため、返済計画が立てやすい | 元金均等返済と比較すると総返済額が多めになる |
| 元金均等返済 | 毎月の返済額(元金と利息の合計)のうち、元金を一定の額とする返済方法。ローン残高が少なくなるほど利息分が減るため、返済が進むほど返済額は少なくなる | 元利均等返済と比較すると総返済額を抑えられる | 返済開始当初の返済額が最も多いため、当初の返済負担が重くなる |
| ボーナス払い | 毎月の返済額に加えて、ボーナス月にはさらに上乗せして返済する方法 | ボーナス月以外の返済負担を減らすことができる | ボーナスの支給額が減ったり、支給がなかったりすると家計の負担が増す |
| 繰上返済 | 毎月の返済とは別に、まとまった金額が用意できた際に返済する方法 | 返済分は全て元金の返済に充てられるため返済利息を減らすことができる | 住宅ローン控除が利用できなくなる場合も。また、預貯金から返済する場合は手元資金が減る |
1.月々の返済額を見極めて返済方法を検討する
元金均等返済は元利均等返済に比べ、当初の支払負担が大きい傾向にあります。元本の金額が一定で、そこに利息が加わるためです。このため、毎月の返済額がどれだけであれば余裕を持って返済していけるのか、慎重なプランニングが必須です。子どもの教育費がいつからいつまでかかるのか、老後資金はどうやって確保するのか。毎月の出費を節約しても不安は残るかもしれません。ライフプランの中で費用がかさみがちな時期を慎重に判断し、返済方式を選択するようにしましょう。
2.総返済額を減らしたい方は
「当初の支払い負担が少々増しても、総返済額を抑えたい」という方には元金均等返済がおすすめです。元利均等返済に比べ、支払う利息の軽減効果が期待できるためです。当初の返済額が多めでも、残高が減るにつれて毎月の返済額は減っていきます。
住宅ローンの返済額の計算方法と平均│借入前の確認ポイントは?
3.ボーナス払いや繰上返済でどうなる?
支払いで元利均等返済を選択し、さらにボーナス払いを併用すると元金を減らすスピードを速めることができます。ただ、不確定な時代にあって、ボーナスが「必ず」「想定した額面の通りに」支給される保証はありません。ボーナス払いの割合をできるだけ少なくすることで、返済時のリスクは軽減できます。返済中に繰上返済を視野に入れているなら、返済負担を一定にできる元利均等返済が有力な選択肢になるでしょう。
3. 【返済方法別】住宅ローンの返済額シミュレーション
元利均等返済と元金均等返済では、月々の支払額や総返済額にどの程度の差が出るのでしょうか。以下の条件でシミュレーションしてみました。
(条件)
借入金額:3,000万円
借入期間:35年(返済回数:420回)
借入金利:1.0%(全期間固定)
ボーナス払い:なし
| 元利均等返済 | 元金均等返済 | |
|---|---|---|
| 初回の返済額 | 84,685円 | 96,428円 |
| 10年目の返済額 | 84,685円 | 89,344円 |
| 20年目の返済額 | 84,685円 | 82,201円 |
| 返済総額 | 35,567,804 円 | 35,262,332 円 |
| 利息総額 | 5,567,804 円 | 5,262,332 円 |
上記のシミュレーション結果から分かるように、住宅ローン金利が同じであっても、元利均等返済と元金均等返済では初回の返済額に12,000円程度の差が出ます。元金均等返済は住宅ローンの借入残高に応じて利息額が計算されるため、返済当初の支払い額が最も多く、それ以降は徐々に減っていくのです。20年目の返済額を比べると、元金均等返済の方が支払い負担を減らせていることが分かるでしょう。注目したいのは総返済額の差です。元利均等返済と元金均等返済では、最終的に約30万円の差が出ます。これはすべて支払い利息分の差額です。
借入時に申し込みした返済方法は原則的に変更できませんが、金融機関によっては対応してもらえることもあります。例えば、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して融資するフラット35では、「生活状況の変化」「収入の変化」があった場合、変更を申請できます。元金均等返済から元利均等返済へ、または元利均等返済から元金均等返済へ、ライフプランやライフイベントによっては、タイプを変更したほうが良い局面もあるでしょう。
返済方法が変更できない場合には、金利方式の変更によって不透明な金利情勢に備えたり、ライフイベントによる家計の変化に対応したりすることが可能です。例えば、みずほ銀行では、変動金利方式と固定金利選択方式で金利方式を切り換えることができます(全期間固定金利方式は切り換え不可)。住宅購入者の多くは変動金利を選んでいますが、金利上昇局面では金利方式の選択が大きなポイントになることもあります。金利の選択については下記の記事で解説していますので、ぜひチェックしてみてください。
金利上昇の住宅ローンへの影響は?金利の最新動向と対策ポイント
返済方法や金利方式の変更が代表的な打ち手になりますが、長い返済中にはプランの微調整を検討すべきターニングポイントもあります。住宅ローン契約時に返済方法や金利方式を選択するのは重要ですが、相談しやすい金融機関を選ぶことも、同じぐらいに大切です。ネット銀行で簡便な手続き方法を選ぶのか、窓口で相談できる金融機関か、自分に合ったアプローチをイメージしておきましょう。
合わせて読みたい
4. 住宅ローンの返済方法はライフプランを考慮して決めることが大切
「月々の返済負担を減らすこと」に重点を置くか、「総返済額を減らすこと」を第一に考えるのか――? 住宅ローンの返済について考えることは、返済方法を考えていくことにつながります。もちろん、これは時代の経済状況によっても大きく変わります。
返済額は「元金分と利息分の合計」ですから、高金利であれば、利息を含めた総支払額の差は大きくなります。一方、現在のような超低金利下では、元金均等返済と元利均等返済のどちらを選択しても、そこまでの差が生じない可能性もあるでしょう。
住宅ローンを組む際には、「長い期間、無理なく返済していけるか」を念頭に置くことが大切です。夢の住まいを手に入れたとしても、無理な借入によって家計の収支が悪化してしまっては本末転倒です。自己資金はいくら確保できるのか。完済時まで、自身や家族にはどのようなライフイベントが発生するのか、さらに住宅ローンの返済以外の出費が「いつ」「どのくらい」発生するのか。余裕資金を見込んでライフプランを明確に描いていきましょう。その検討のプロセスで、家庭に合った返済方法がおのずと見えてくるはずです。

新井 智美
(あらい ともみ)
CFP(R)認定者/一級ファイナンシャルプラン二ング技能士/DCプランナー/住宅ローンアドバイザー/証券外務員等の資格を保有し、コンサルタントとしての個人向け相談の他、資産運用等上記相談内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)を行う傍ら、年間100件以上の執筆・監修業務を手掛けている。
CFP(R)認定者/一級ファイナンシャルプラン二ング技能士/DCプランナー/住宅ローンアドバイザー/証券外務員等の資格を保有し、コンサルタントとしての個人向け相談の他、資産運用等上記相談内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)を行う傍ら、年間100件以上の執筆・監修業務を手掛けている。