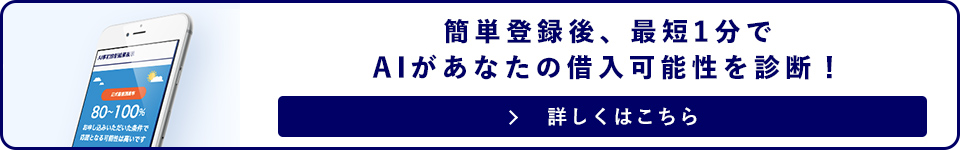いくらまで住宅ローンが組めるか調べる方法と年収ごとの借入額の目安
掲載日:2022年12月22日

目次
住宅ローンを検討する際、心配になるのは「自分はいくらまで借りられるのか」ということです。一戸建てでもマンションなど、憧れのマイホームを思い描いても、資金計画が組めなければ夢のままで終わってしまいます。不動産の購入にあたっては、月々の返済をしっかり計算しつつ考えていくことが大切です。この記事では、一般的なローン借入額の値を参照しつつ、収入に合った住宅購入額の算出方法を解説していきましょう。
1. 住宅ローンの借入可能額とは?
住宅ローンがいくらまで組めるか、つまり借入可能額は契約者の収入と密接に関わっています。自己資金はもちろん、申込者の様々な要素から判断し、金融機関は融資額を決定していくのです。
住宅ローンには借入できる金額に制限がある
住宅ローンが組める金額は借入可能額と呼ばれます。つまり、契約する本人がどれだけ借りられるかを示すもの。これは複数の要素によって判断されますが、住宅ローンを取り扱っているどの金融機関も明確な基準は公表していません。ただ、申込条件や提出書類に求められる記入事項などから、何が重視されるのかを推測することはできます。
住宅ローンを申し込んでから借入に至るまで、事前審査から本審査といった流れを経る住宅ローン審査があります。気になる審査項目には雇用形態や勤続年数、健康状態などがあり、審査基準は金融機関によって異なりますが、信用情報も重要です。収入や健康はもちろん、その他の借入状況を含めて、返済能力が支払能力のメリット、デメリットとして総合的にチェックされるのです。
2. 住宅ローンがいくらまで組めるか調べる方法

ここでは、住宅の購入価格と年収の割合から、借入可能額の目安を算定する方法を解説します。住宅ローン利用者の平均を見つつ、シミュレーションについて紹介していきましょう。
返済負担率から借入可能額の目安を算出する
まず、フォーカスするのが返済負担率です。これは年収に占める年間返済額の割合のことで、返済比率とも呼ばれます。住宅金融支援機構による「住宅ローン利用者の実態調査」(2022年4月)によると、返済負担率は15%~20%程度が最も多い現状が分かります。
ここで返済負担率の算出方法を見てみましょう。
例:年収400万円、返済負担率20%
この場合、年間の返済額の上限は、400万円×20%=80万円になります。借入期間を35年に設定した場合は、80万円×35年=2,800万円。このように、返済負担率から借入額の目安を求めることができます。返済負担率は返済期間や年収、金利によって変わってくるため、あくまでも目安として考えるようにしましょう。例えば、総返済額には金利が含まれるため、実際の借入可能額は単純計算で試算した額面より少なくなります。
平均の返済負担率は15~20%でしたが、銀行など金融機関の多くは、借入可能額を審査する際に、返済負担率を25%~35%程度に設定することが多くなっています。この審査結果に大きく影響するのが、他からの借入です。金融機関の審査では、年収と合わせて個人信用情報を参照し、融資の可否を出します。信用情報には、クレジットカードや公共料金などの借り入れを延滞することなく行えているかどうか、他での借入状況がないかどうかをチェックします。ローンの審査書類には自動車ローン、分割払いにしたスマートフォン・携帯電話の契約などを記入しますが、これらの支払状況に遅延がないかどうかも精査されます。
信用情報は、CIC、JICC(全国銀行個人信用情報センター)、KSCといった個人信用情報機関に開示請求をかけて調査されます。これらの機関にはクレジットカード会社や信販会社、消費者金融、銀行の情報が登録されており、個人のキャッシング、カードローン、リボ払いなどの履歴、記録が共有されています。
「借金が多額になったり、過去に自己破産を経験したりしたことが理由でブラックリスト入り。それが問題になったのか、審査落ちして住宅ローンが組めなかった」といった経験談を聞いたことがあるかもしれません。これは、信用情報機関に「異動情報」が記載されている状況のことです。
異動は「金融事故」とも言われますが、どのようなケースが「事故情報」に該当するのでしょうか。それはクレジットカードの支払の滞納、自己破産や個人再生、債務整理、任意整理といった事例です。こうした事故情報が原因となり、住宅ローン審査を通過しにくくなる可能性もあります。
「そういえば、クレジットカードの支払を滞納したことがあった。審査で不利になるのかも」と不安を覚えた方もいるでしょう。その場合は、3社の個人信用情報機関に情報開示の請求をかける手続きにより、自身の事故記録の有無を確認できます。延滞や自己破産などの情報は一定の登録期間があり、最長10年程度で消去されます。万が一の不安がある方は、各機関に照会して信用情報を調べてみるという対処法もおすすめです。
金利タイプ別の住宅ローン返済負担率の利用割合
| 返済負担率/金利タイプ | 変動型 | 固定金利選択型 | 全期間固定型 |
|---|---|---|---|
| 10%以内 | 10.6% | 9.7% | 10.5% |
| 10%超15%以内 | 19.8% | 23.2% | 21.8% |
| 15%超20%以内 | 27.3% | 24.7% | 23.3% |
| 20%超25%以内 | 22.3% | 16.2% | 22.6% |
| 25%超30%以内 | 10.6% | 14.3% | 10.5% |
| 30%超35%以内 | 5.4% | 5.4% | 6.0% |
| 35%超40%以内 | 2.4% | 4.2% | 3.0% |
| 40%超 | 1.5% | 2.3% | 2.3% |
金融機関のシミュレーターを使用して算出する
「住宅ローンがいくらまで組めるか」を無料で算出するシミュレーターをWEB上に用意している金融機関もあります。これは必要な項目を入力するだけで、借入可能額の目安を簡単に出してくれるもの。例えば、みずほ銀行の「AI事前診断」では、希望額で借入ができるかどうかの確率を最短1分で算出します。
あくまでシミュレーションツールではありますが、借入希望額、借入希望期間、年齢、資金使途などを入力することで、本審査に近い基準で試算することができます。自分の家庭でいくら借りられるか把握することが、有利な返済計画を組む際の参考材料になるはずです。
3. 【年収別】いくらまで住宅ローンが組めるかの目安一覧表
住宅ローンを組む際に気になるのが「自分はいくらまで借りられるのか?」というポイントです。ここでは、年収別の借入可能額を算出してみましょう。
年収別に「いくらまで住宅ローンが組めるのか」、つまり借入可能額の目安を試算してみました。ここで算出した数字は借り入れられる上限の額になりますので、一つの目安としてご覧ください。
【計算条件】融資金利:1.540%
返済期間:35年
返済方法:元利均等
ボーナス払い:なし
その他:住宅ローン以外の借入なし
| 年収 | 借入可能額の目安 |
|---|---|
| 300万円 | 2,433万円 |
| 400万円 | 3,786万円 |
| 500万円 | 4,732万円 |
| 600万円 | 5,679万円 |
| 700万円 | 6,625万円 |
| 800万円 | 7,572万円 |
| 900万円 | 8,000万円 |
| 1,000万円 | 8,000万円 |
| 1,100万円 | 8,000万円 |
| 1,200万円 | 8,000万円 |
| 1,300万円 | 8,000万円 |
| 1,400万円 | 8,000万円 |
| 1,500万円 | 8,000万円 |
4. 住宅ローンはいくらまで組める? 大切なのは慎重に調べること
住宅ローンの借入可能額をシミュレーションしましたが、実際の額面は様々な要素から総合的に判断されます。注意点として、キャッシングやローンなどの債務もしっかり把握しておくことが欠かせないことも分かりました。長きにわたる返済期間は、結婚や出産、子供の進学や親の介護など、お金の面でも山あり谷あり。その先には、安定した老後を過ごすための備えも考えていかなければなりません。毎月の返済負担を照らし合わせ、無理なく完済できるかどうかを念頭に入れ、借入額を慎重に考えていきましょう。

佐々木 正孝
(ささき まさたか)
編集/ライター。キッズファクトリー代表。教育・ビジネス系の記事を執筆しつつ、児童書の編集やマンガ原作も手がける。
編集/ライター。キッズファクトリー代表。教育・ビジネス系の記事を執筆しつつ、児童書の編集やマンガ原作も手がける。
ほかの人が次に読んでいる記事

住宅ローンは何歳まで組める?借入時の平均年齢と理想の完済時年齢
公開: 2022年12月22日

フラット35のメリット・デメリット、向いている人の特徴とは?
公開: 2022年7月14日

金利上昇による住宅ローンへの影響とは?返済額をシミュレーション
公開: 2022年5月25日
住宅ローンに関するほかの記事を探す
住宅ローンシミュレーション
毎月の返済可能額やあなたの年収から借入額をシミュレーションできます。資金計画をシミュレーションしてみてください。
みずほ銀行の住宅ローン
みずほ銀行で住宅ローンをお借り入れいただく場合の適用金利についてご紹介します。変動金利と全期間固定金利、固定金利選択からお選びいただけます。
資産形成について学ぶ
みずほ銀行おかねアカデミー
皆さまが将来を見据えて資産を形成できるよう、4つのカテゴリーに分けて資産形成に関する情報やデータをまとめたコラム記事をご用意しています。