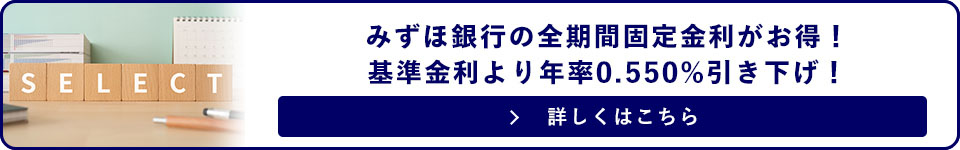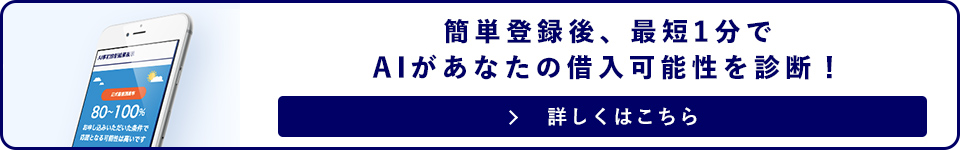フラット35の審査基準│審査の流れから向いている人の特徴まで
掲載日:2022年5月25日

目次
住宅購入のために住宅ローンを利用する際、多くの方がフラット35を有力な選択肢として考えるのではないでしょうか。返済期間中の金利が変わらない固定金利型のフラット35ですが、利用するためには一定の条件を満たす必要もあります。今回はフラット35の審査申込から契約までの流れ、購入する物件の条件などの審査基準、ご利用まで具体的なケースも解説していきます。
1. フラット35の審査申込から契約の流れ
まずはフラット35についての住宅ローン審査から契約までの流れをダイジェストで紹介します。一連の流れの中でチェックポイント、用意すべき書類も押さえておきましょう。
購入する物件を決める
まずは自分たちにフィットする大切な住まい探しです。購入する物件が決まっていなければフラット35の審査には進めません。ハウスメーカーの住宅展示場やモデルルーム、不動産会社の見学会などを活用し、理想の住まいを見つけましょう。希望物件の価格や頭金から月々の支払額をシミュレーションし、資金計画を立てたいですね。マイホームにしたい物件が見つかったら購入の申込へ進みます。
事前審査を申し込む
物件の購入申込後、フラット35を提供する金融機関で事前審査を申し込みます。この審査は任意ですが、販売会社の意向に沿って利用することが多くなっています。一般的には、この事前審査に通過しなければ本審査に申し込むことはできません。申込に必要な書類は金融機関によって異なるため、事前に確認し、漏れのないようにしましょう。審査結果はおおむね数日で出ます。
本審査に申し込む
事前審査に通過したら、いよいよ本審査の手続きに進みます。必要書類の種類は本人確認書類の身分証明書、実印、収入を確認する収入証明書など、物件を確認するための資料など。その後には印鑑証明書や住民票、課税証明書、売買契約書、工事請負契約書などの提出が必要になるので、チェックリストを作って整理しておきましょう。提出された資料、情報をもとに行う本審査に通過すると融資の仮承認が受けられます。
適合証明書を取得する
ここで必要になるのが適合証明書です。適合証明書は購入する住宅が、住宅金融支援機構が定める独自の技術基準に適合していることを証明するもので、フラット35を利用するなら、この書類の提出が条件になります。適合証明書の発行は不動産会社や建築会社への依頼が一般ですが、検査機関に直接依頼して自分で入手することも可能です。この適合証明書に加え、仮承認の際に通知された資料などを提出して資金の受取日を決定します。これらの必要な条件が整うことで、最終的な融資承認を受けられるのです。
金銭消費貸借契約を結ぶ
本審査を経て適合証明書も取得したら、ローン契約(金銭消費貸借契約)に進みます。ここで最終的に借入金額、実行金利、返済年数・期日、毎月のローン支払い額、抵当権の設定、遅延損害金など、契約の内容の取り決めが行われます。
物件の購入資金が申込者の口座に振り込まれるのが「融資実行」です。契約書で定めた融資実行日に融資を確認し、受け取ります。融資実行日に住宅の代金を精算して引き渡しを受けます。この契約時に合わせ、司法書士によって抵当権の設定も行われます。
2. フラット35の審査基準
フラット35を借り入れる際の審査基準、条件は銀行や信用金庫など、どの民間金融機関でも共通です。その基準をチェックしていきましょう。
申込者本人に関する条件
まず、申込者の年齢は申込時に70歳未満であることが条件です。そして、額面年収の「400万円」が一つの基準になっていて、400万円未満か400万円以上かで返済比率の上限が異なっています。返済比率とは、年収のうち年間にどれだけ返済するかという額の割合です。年収400万円未満は返済比率30%まで、年収400万円以上は返済比率が35%までとなっています。
購入する住宅に関する条件
対象になる住宅にも条件があります。新築一戸建て、新築マンション、中古一戸建て、中古マンションで以下のようにそれぞれ技術基準が定められており、この技術基準を満たす住宅でなければフラット35の融資が受けられないのが注意点です。
新築住宅の技術基準
| 一戸建て住宅等(※1) | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 接道 | 原則として一般の道に2m以上接すること | ||
| 住宅の規模(※2) | 70平方メートル以上 | 30平方メートル以上 | |
| 住宅の規格 | 原則として2以上の居住室(家具等で仕切れる場合でも可)ならびに炊事室、便所および浴室の設置 | ||
| 併用住宅の床面積 | 併用住宅の住宅部分の床面積は全体の2分の1以上 | ||
| 戸建型式等 | 木造の住宅(※3)は一戸建てまたは連続建てに限る | ||
| 断熱構造 | 住宅の外壁、天井または屋根、床下などに所定の厚さ以上の断熱材を施工(断熱等性能等級2レベル以上) | ||
| 住宅の構造 | 耐火構造、準耐火構造(※4)または耐久性基準(※5)に適合 | ||
| 配管設備の点検 | 点検口等の設置 | 共用配管を構造耐力上、主要な壁の内部に設置しないこと | |
| 区画 | 住宅相互間等を1時間準耐火構造等の界床・界壁で区画 | ||
| 床の遮音構造 | 界床を厚さ15cm以上(RC造の場合) | ||
| 維持管理基準 | 管理規約 | 管理規約が定められていること | |
| 長期修繕計画 | 計画期間20年以上 | ||
- ※1.一戸建て住宅等には連続建て住宅および重ね建て住宅を含みます。
- ※2.住宅の規模とは住宅部分の床面積をいい、車庫や共用部分(マンションの場合)の面積を除きます。
- ※3.木造の住宅とは耐火構造の住宅および準耐火構造(※4)の住宅以外の住宅をいいます。
- ※4.準耐火構造には省令準耐火構造を含みます。
- ※5.耐久性基準とは基礎の高さ、床下換気孔等に関する基準です。
中古住宅の技術基準
| 一戸建て住宅等(※1) | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 接道 | 原則として一般の道に2m以上接すること | ||
| 住宅の規模(※2) | 70平方メートル以上(共同建ての住宅は30平方メートル以上(※4)) | 30平方メートル以上(※4) | |
| 住宅の規格 | 原則として2以上の居住室(家具等で仕切れる場合でも可)ならびに炊事室、便所および浴室の設置 | ||
| 併用住宅の床面積 | 併用住宅の住宅部分の床面積は全体の2分の1以上 | ||
| 戸建型式等 | 木造の住宅(※5)は一戸建てまたは連続建てに限る | ||
| 住宅の構造 | 耐火構造、準耐火構造(※6)または耐久性基準(※7)に適合 | ||
| 住宅の耐震性 | 建築確認日が1981年6月1日以後(※8)であること (建築確認日が1981年5月31日以前の場合(※9)は耐震評価基準などに適合) | ||
| 劣化状況 | 土台、床組等に腐朽や蟻害がないこと等 | 外壁、柱等に鉄筋の露出がないこと等 | |
| 維持管理基準 | 管理規約 | 管理規約が定められていること | |
| 長期修繕計画 | 計画期間20年以上 | ||
- ※1.一戸建て住宅等には連続建て住宅、重ね建て住宅および地上2階以下の共同建ての住宅を含みます。
- ※2.マンションとは地上3階以上の共同建ての住宅をいいます。
- ※3.住宅の規模とは住宅部分の床面積をいい、車庫やバルコニー等は含みません。
- ※4.共同建ての住宅の場合は建物の登記事項証明書による確認においては28.31㎡以上あれば構いません。
- ※5.木造の住宅とは耐火構造の住宅および準耐火構造(※6)の住宅以外の住宅をいいます。
- ※6.準耐火構造には省令準耐火構造を含みます。
- ※7.耐久性基準とは基礎の高さ、床下換気孔等に関する基準です。
- ※8.建築確認日が確認できない場合は新築年月日(表示登記における新築時期)が1983年4月1日以後とします。
- ※9.建築確認日が確認できない場合は新築年月日(表示登記における新築時期)が1983年3月31日以前とします。
融資に関する条件
借入額の上限は8,000万円で、借入期間は原則15年以上と定められており、「35年」「80歳から申込時の年齢を引いた数字(1年未満は切り上げ)」の、いずれか短い年数が上限になります。
合わせて読みたい
3. 商品特性・審査基準から見るフラット35に向いている人・いない人
フラット35はその名の通り、金利が「フラット(平ら)」で返済期間が最長35年の住宅ローンです。商品の魅力と向き・不向きに注意を払いつつ、ニーズと突き合わせて民間金融機関のローンとも比較検討してみてください。
フラット35を相談・申込可能な窓口
フラット35とは国の独立行政法人の住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して融資している全期間固定金利の住宅ローンで、2003年からスタートしています。住宅金融支援機構と契約した民間の金融機関で相談・申込ができ、窓口となる金融機関によって住宅ローン金利のタイプ、手数料に違いがあるのが特徴です。
フラット35に向いている人の特徴
返済期間中の返済額を一定にしたい人
フラット35は全期間固定金利ですから、返済期間中は返済額が一定です。そのため、返済プランを立てやすくなっています。
住宅の質を重視したい人
上記で紹介した通り、住宅金融支援機構が定めた技術基準をクリアするのが融資の要件になります。省エネルギー性、耐震性など厳密な基準があり、住まいには安心感があります。住宅の性能によっては金利引下げのメリットも視野に入ります。
家族で返済を考えたい人
住宅金融支援機構の条件を満たせば連帯債務を利用することができ、所得を合わせることで借入金額を増やすこともできます。親子リレー返済を利用することで70歳以上の方でも利用可能です。
他の住宅ローンで取り扱いができない土砂災害特別警戒区域で家を建てたい人
通称「レッドゾーン」と言われる地域での建築は利用できる住宅ローンが限られてしまうという問題があります。この場合も、フラット35で融資する方法で、その土地への建築の可能性を検討できます。
フラット35に向いていない人の特徴
返済時の利息負担をできるだけ減らしたい人
フラット35は全期間固定金利です。返済当初は変動金利のほうが金利は低めで、利息額は少なくなります。今後、金利が上昇することで利息が増加するリスクより現在の利息負担の軽減を優先するなら、民間の変動金利型の住宅ローンがおすすめです。
フラット35技術基準に適合していない住宅を購入する人
フラット35の技術基準に適合しない住宅を購入したい場合、融資を申し込むことができません。
4. 物価上昇に強く、住宅の基準も厳密なメリットは要チェック

住宅ローンを考えるなら選択肢に入るフラット35について、あらためてまとめてみました。民間金融機関が独自に展開している住宅ローンよりも金利は高めですが、物価が上昇しても金利が変わらないなど、全期間固定金利ならではの魅力は見逃せません。
災害への不安があるので対策をしておきたいという方も、フラット35に適合する住宅は耐火性、耐震性も厳密な基準が定められているので安心です。また、収入を合算して計算し、家族で返済を考えていきたいという方も使いやすいのが特徴です。審査基準、傾向などをチェックしつつ、有力な選択肢として考えてみてはいかがでしょうか。

佐々木 正孝
(ささき まさたか)
編集/ライター。キッズファクトリー代表。教育・ビジネス系の記事を執筆しつつ、児童書の編集やマンガ原作も手がける。
編集/ライター。キッズファクトリー代表。教育・ビジネス系の記事を執筆しつつ、児童書の編集やマンガ原作も手がける。