マイクロ法人とは?個人事業主との違いやメリット・デメリットを分かりやすく解説
掲載日:2025年5月14日起業準備

従業員を雇わずに代表者一人で事業を行う法人は、「マイクロ法人」と呼ばれることもあります。
マイクロ法人と個人事業主の違いが分からない方や、「マイクロ法人を設立した方が税金の負担額を抑えられるのでは」と迷っている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、マイクロ法人のメリット・デメリットや個人事業主との違い、作り方を解説します。
<最短翌営業日に開設>来店不要で休日・夜間も受付中!
法人口座開設のお申込方法やお得な特典等の詳細は、以下のページをご確認ください。
目次
マイクロ法人とは
一般的にマイクロ法人とは、従業員を雇わずに代表者一人で事業活動を行う法人を指します。あくまでも一般的な名称であり、会社法等で法的に定められている概念ではありません。設立の際は、一般的な法人と同様に法務局への登記が必要です。
マイクロ法人は、税金や社会保険料の負担を軽減する手段の一つとして設立されます。設立を検討するケースとして、主に以下のものが考えられます。
- 個人事業主としての事業が成長してきた
- 個人事業主として事業を行っているが、法人として新規事業を行いたい
- 会社員とは別に、副業の所得が増えてきた
マイクロ法人と一般的な法人の違い
マイクロ法人は俗称であり、法的に定められている法人形態ではありません。そのため、法律上は一般的な法人(株式会社や合同会社等)と同様に取扱われます。
| 項目 | マイクロ法人 | 一般的な法人 |
|---|---|---|
| 法人格 |
あり |
あり |
| 従業員・外部株主の有無 |
なし(代表者一人) |
あり |
| 設立の主な目的 |
税金や社会保険料の軽減等 |
事業の拡大等 |
| 法人格 | |
|---|---|
| マイクロ法人 |
あり |
| 一般的な法人 |
あり |
| 従業員・外部株主の有無 | |
| マイクロ法人 |
なし(代表者一人) |
| 一般的な法人 |
あり |
| 設立の主な目的 | |
| マイクロ法人 |
税金や社会保険料の軽減等 |
| 一般的な法人 |
事業の拡大等 |
一般的に、ご自身以外の従業員や株主がいないことがマイクロ法人の特徴です。
マイクロ法人と個人事業主の違い
マイクロ法人と個人事業主には、法人化しているかどうかの違いがあります。
| 項目 | マイクロ法人 | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 法人格 |
あり |
なし |
| 資本金 |
必要 |
不要 |
| 手続き |
定款の作成や登記手続き等 |
開業届の提出 |
| 法人格 | |
|---|---|
| マイクロ法人 |
あり |
| 個人事業主 |
なし |
| 資本金 | |
| マイクロ法人 |
必要 |
| 個人事業主 |
不要 |
| 手続き | |
| マイクロ法人 |
定款の作成や登記手続き等 |
| 個人事業主 |
開業届の提出 |
個人事業主は、税務署に開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出すれば事業を始められます。
一方、マイクロ法人として事業を行うためには、定款の作成や法務局への登記申請等を行う必要があり、個人事業主と比べて手続きが煩雑です。
また、法人格の有無に伴い、税金や社会保険等にも様々な違いがあります。
個人事業主のメリットやデメリットをより詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。
関連記事:「個人事業主とは?必要な手続きやメリット・デメリットを解説」
マイクロ法人設立のメリット
マイクロ法人は、主に税務上のメリットを享受する目的で設立されます。設立による主なメリットは、以下の通りです。
- 税金の負担額を抑えやすい
- 社会保険料の負担額を抑えやすい
- 経費として認められる範囲が広くなる
- 社会的な信用を得やすくなる
税金の負担額を抑えやすい
マイクロ法人を設立すると、税務上のメリットを享受できます。
個人事業主の事業所得に課される所得税の税率は、5%から45%の7段階に区分されています。所得が多くなるにつれて段階的に税率が高くなる「累進税率」がとられており、所得金額に応じて最大45%の税率で所得税を納めなければなりません。
一方、マイクロ法人の事業所得には法人税が課されます。法人税の税率は原則として23.2%(資本金1億円以下の法人で所得金額800万円/年以下の部分は15%)であるため、所得金額によってはマイクロ法人を設立した方が税金を抑えられる可能性があります。
また、法人化し、社長として受け取る給与(役員報酬)は、所得税を計算する際に給与所得控除を適用することが可能です。役員報酬が年間162万5,000円以下の場合、55万円を差し引いて給与所得を計算できます(2025年3月時点)。
社会保険料の負担額を抑えやすい
社会保険料の負担額を抑えやすいことも、マイクロ法人を設立するメリットの一つです。
個人事業主とマイクロ法人の社長が加入する社会保険は、それぞれ以下の通りです。
| 区分 | 社会保険 |
|---|---|
| 個人事業主 |
主に国民健康保険、国民年金 |
| マイクロ法人の社長 |
健康保険(協会けんぽ)、厚生年金 |
多くの個人事業主が加入する国民健康保険の保険料は、前年の所得が高いほど高くなる仕組みです。
一方、マイクロ法人を設立して社長になると、健康保険に加入します。保険料は役員報酬を基に決まりますが、保険料の負担を考慮してご自身で役員報酬額を決めることが可能です。そのため、役員報酬額を可能な限り低くすることで、保険料の負担額を抑えられる可能性があります。
また、国民健康保険には扶養の仕組みがありません。一方、法人化して健康保険に加入すると、一定の条件を満たす家族は扶養に入れるため、扶養家族の保険料の負担額を軽減できる可能性があります。
厚生年金保険料は、一般的に国民年金保険料よりも高くなりますが、将来受け取れる年金が増える点はメリットと言えるでしょう。
個人事業主が加入する社会保険や法人との違いをより詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。
関連記事:「個人事業主が加入できる社会保険は?法人化でどう変わるかも解説」
経費として認められる範囲が広くなる
マイクロ法人を設立すると、個人事業主のときと比べて経費(損金)として認められる範囲が広くなります。
事業で得た所得は、収入から経費を差し引いて計算するため、経費として認められる支出が増えると課税所得が減り、税金の負担額の軽減につながります。
例えば、マイクロ法人の社長が受け取る役員報酬は、一定の条件を満たせば経費として計上が可能です。個人事業主の場合、ご自身の給与(所得)は経費になりません。
また、マイクロ法人を設立して健康保険・厚生年金に加入すると、社会保険料は法人との折半になり、会社負担分の社会保険料は経費として認められます。
その他、法人名義で契約する生命保険料や出張時の日当等も、一定の条件のもとで経費計上が可能です。
社会的な信用を得やすくなる
マイクロ法人は登記手続きを行って設立し、会社法等の法律に基づいて運営します。そのため、個人事業主のときと比べて社会的信用を得やすくなり、取引先の拡大等が期待できるでしょう。
なお、法人を設立した際は、法人口座を開設することで企業としての信用度がより高まります。
関連記事:「新設法人が法人口座を開設するメリットは?口座開設の流れやポイントも紹介」
マイクロ法人設立のデメリット

マイクロ法人を設立すると、税金面や社会的信用等でメリットがある反面、法人化によるデメリットも存在します。
- 経理事務の負担が大きくなる
- 法人の設立費用や維持費用がかかる
- 赤字でも納めなければならない税金がある
経理事務の負担が大きくなる
マイクロ法人を設立すると、個人事業主のときと比べて経理事務の負担が大きくなります。
個人事業主は、年に1回の確定申告によって、所得税額の確定・精算を行います。
一方、マイクロ法人を含む法人が行う決算申告は、個人事業主と比べて手続きが煩雑で、かつ多くの書類を作成しなければなりません。また、従業員がいないマイクロ法人でも、給与計算が必要です。
作成する書類が複雑で、専門知識も求められることから多くの場合、税理士に依頼することが一般的です。ただし、税理士に依頼する場合は費用がかかります。
法人の設立費用や維持費用がかかる
マイクロ法人を設立する際には、登録免許税や定款の認証を受けるための手数料等が必要です。
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 登録免許税 |
株式会社:最低15万円 |
| 定款の認証手数料 |
3万円~5万円
|
| 収入印紙(紙の定款) |
4万円 |
また、法人住民税(均等割)や税理士等の専門家への報酬等、マイクロ法人を維持するための費用も把握する必要があります。
赤字でも納めなければならない税金がある
個人事業主の場合、赤字なら所得税や住民税がかかりません。
しかし、マイクロ法人の場合は、赤字でも法人住民税(均等割)を納めなければなりません。均等割は資本金の額や従業員数に応じて決まっており、資本金1,000万円以下のマイクロ法人の場合は、最低でも年間7万円を納める必要があります。
なお、法人住民税とは、法人が自治体の行政サービスを受けるために納める地方税で、税額は均等割と法人税割(法人税額に応じて負担するもの)の合計金額です。
マイクロ法人を設立する際にぶつかるよくある質問
マイクロ法人の設立を検討する際、個人事業主のまま事業を行う方が良いか、会社員でも法人を設立できるか等の疑問が生じることがあります。
十分に理解しないままマイクロ法人を設立し、後悔しないためにも、以下のポイントを押さえましょう。
法人設立がおすすめなのは年収いくらから?
一般的に、税務上のメリットを享受する目的の場合、法人化を検討したい年収の目安は所得800万円~900万円程度といわれます。所得が800万円を超えると、個人事業主の所得税率が法人税率を上回り始めるためです。
また、社会保険料の負担額の軽減を目的とする場合は、一般的に扶養家族がいなければ所得200万円程度、扶養家族がいる場合は年収に関わらずマイクロ法人設立を検討するのが良いとされます。
ただし、上記はあくまでも目安の一つで、実際には個人や事業の状況によって異なります。法人を設立するための費用や維持費等も含め、税理士等に相談しながらご自身の状況に応じて検討することが重要です。
サラリーマンが法人を設立するのは違法?
サラリーマン(会社員)が法人を設立することは、法的に問題ありません。副業の所得が多い場合、法人化によって税務上のメリットを享受できる可能性があります。
なお、法人化するかどうかに関わらず、勤務先が就業規則等で禁止している場合は副業ができません。規則違反として懲戒処分を受ける可能性もあるため、事業を始める前に確認しましょう。
売上なしでも法人を設立できる?
売上なしや赤字でも、法人の設立は可能です。ただし、売上のない状態が長く続くと、事業実態がないペーパーカンパニーだと判断されるリスクがあります。
ペーパーカンパニーとみなされると、犯罪への悪用等の嫌疑をかけられる可能性があるため、適切な事業運営が求められます。
また、売上なしでも決算・申告を行う必要があるほか、赤字でも法人住民税の均等割を支払わなければならないことも踏まえ、法人の設立を検討しましょう。
マイクロ法人におすすめの事業
一般的に、マイクロ法人に向いているのは、小規模で運営でき、初期費用を抑えやすい以下のような事業です。
- 大きな設備投資が必要ない
- 在庫の仕入れが少ない
- オフィスを持たずに運営できる
初期投資が少なく済む事業を選べば、比較的リスクを抑えて設立でき、キャッシュ・フローが安定しやすくなります。以下は、マイクロ法人に向いている事業の一例です。
- フードデリバリー
- 動画配信
- ソフトウェア開発
- マッサージ業
- 士業等
マイクロ法人の作り方・手順
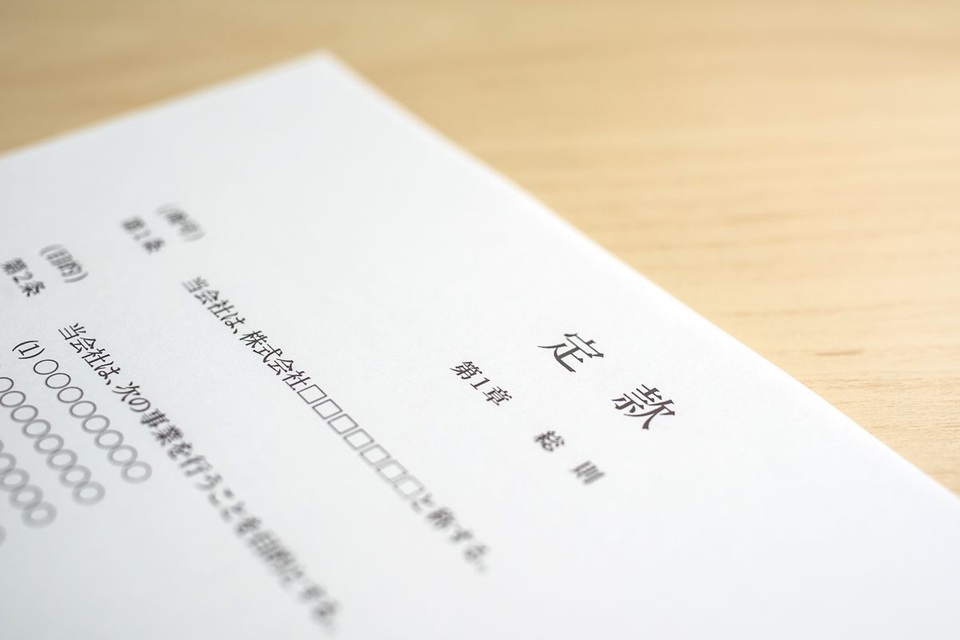
マイクロ法人を設立する際は、個人事業主とは違い、定款の作成や登記申請等の手続きが必要です。一般的な法人と同様に、以下の流れで設立します。
- ①商号等の基本事項を決める
- ②定款を作成して認証を受ける
- ③法人の印鑑を作成する
- ④出資金を払い込む
- ⑤法務局で登記申請を行う
- ⑥マイクロ法人設立後の各種手続きを行う
①商号等の基本事項を決める
マイクロ法人の基本的な事項を決定します。
- 法人形態
- 事業の目的
- 商号
- 事業内容
- 本店所在地
- 資本金の額
- 決算期等
マイクロ法人の法人形態は、現在設立できる4種類のうち、株式会社、合同会社、合名会社の3種類から選択できます。合資会社は2人以上の社員(出資者)が必要であるため、一人では設立できません。
②定款を作成して認証を受ける
法人を設立する際は、定款(法人の根本となる規則)を作成しなければなりません。
定款の記載事項には、法律上必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」があります。絶対的記載事項が記載されていないと、定款自体が無効となるため注意が必要です。
株式会社を設立する場合の絶対的記載事項は、以下の5つの項目です。
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
- 発起人の氏名または名称および住所
定款の作成後、必要書類や認証に必要な費用を用意のうえ、公証役場で認証を受けます。ただし、認証が必要なのは株式会社を設立する場合で、合同会社・合名会社・合資会社の定款は認証が不要です。
関連記事:「定款とは?作り方・記載内容から認証の方法まで分かりやすく解説」
③法人の印鑑を作成する
法人の登記申請を書面で行う場合、実印(法務局に提出している印鑑)を登記申請書に押印する必要があるため、社名が決まったら早めに実印を作成しましょう。
登記申請をオンライン上で行う場合、印鑑の提出は任意ですが、融資や不動産取引の契約書等、実印を求められるケースは少なくありません。
また、金融機関に届け出る銀行印や、領収書や請求書等の各種書類に捺印するための角印も併せて作成しましょう。
④出資金を払い込む
金融機関に出資金を払い込みます。まだ法人を設立しておらず、法人名義での口座は作れないため、個人口座に振り込むことが一般的です。
払込後、払い込まれたことが分かる口座の通帳のコピーを取りましょう。
- 表紙
- 裏表紙(支店名・口座番号・口座名義人が分かるページ)
- 払い込まれた日や金額が分かるページ
通帳の写しに代わるものとして、インターネットバンキングの取引状況に関する画面等(金融機関名、口座名義人名、振込日、振込金額が記載されているもの)をプリントしたものでも問題ありません。
これらのコピーは登記手続きの際に添付する必要があるため、大切に保管してください。
⑤法務局で登記申請を行う
必要な書類を作成・準備し、本店所在地を管轄する法務局で法人設立の登記申請を行います。主な必要書類は以下の通りです。
- 登記申請書
- 定款
- 発起人の同意書
- 設立時代表取締役を選定したことを証する書面
- 設立時取締役の就任承諾書
- 本人確認証明書
- 払込を証する書面
- 印鑑届書等
定款の記載内容等によって添付書類が異なるため、事前に確認しましょう。
申請後、法務局による審査が実施されるため、登記が完了するまでには数日~数週間の時間を要します。不備があると訂正または書面の再作成が必要となり、さらに時間がかかるため、十分に注意しましょう。
なお、マイクロ法人を設立する際は、オンライン完結による申請が便利です。完全オンライン申請で一定の条件を満たした場合、登記申請が多い時期を除き、原則として24時間以内に登記が完了します。
⑥マイクロ法人設立後の各種手続きを行う
マイクロ法人の設立後は、法人税や健康保険・年金保険等の手続きが必要です。
| 手続き先 | 主な手続き |
|---|---|
| 税務署 |
|
| 年金事務所 |
|
また、マイクロ法人の設立後、事業を始めるための許認可の手続きや取引先への請求等をスムーズに行うために、なるべく早い段階で法人口座を開設することをおすすめします。
法人口座の開設にも日数を要するため、マイクロ法人設立と同時に準備を進めるのが望ましいでしょう。
法人口座を開設すると、資金管理を効率化できるだけでなく、取引先から不信感を抱かれたり、税務署から不正を疑われたりするリスクを低減できるメリットもあります。
関連記事:「法人口座の開設方法は?メリットや金融機関の選び方、必要書類を解説」
法人口座の開設はみずほ銀行がおすすめ
みずほ銀行の法人口座開設は、休日・夜間でもお申し込みができ、ウェブ面談のため来店不要で手続きを完結できます。登記事項証明書・印鑑証明書の提出が原則不要なので、書類を準備する手間も減らすことができます。
また、法人形態関係なく会社設立3年以内のお客さまは、インターネットバンキング(みずほビジネスWEB)の月額利用料が最大5年間無料になります。
さらにみずほ銀行の法人口座では、年会費永年無料の法人向けデビットカード「みずほビジネスデビット」を発行できる等、ビジネスを支えるサービスが充実しています。
マイクロ法人の設立を検討している方は、ぜひみずほ銀行の法人口座をご検討ください。
まとめ
マイクロ法人とは、代表者一人で事業を行う法人のことです。マイクロ法人を設立すると、税務上のメリットを享受できる、社会的信用度が高まる等の効果が期待できます。
事業が軌道に乗ってきた、あるいは税金や社会保険料の負担が重いと感じる等のタイミングで、マイクロ法人の設立を検討しましょう。
マイクロ法人設立の手続きには一定の時間が必要なため、早めから計画的に準備を進める必要があります。また、法人設立後はなるべく早い段階で法人口座を開設しましょう。
<最短翌営業日に開設>来店不要で休日・夜間も受付中!
法人口座開設のお申込方法やお得な特典等の詳細は、以下のページをご確認ください。
監修者

安田 亮
- 公認会計士
- 税理士
- 1級FP技能士
1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。