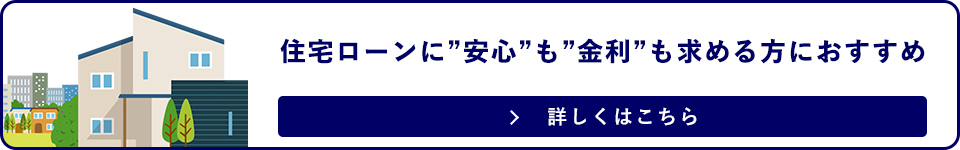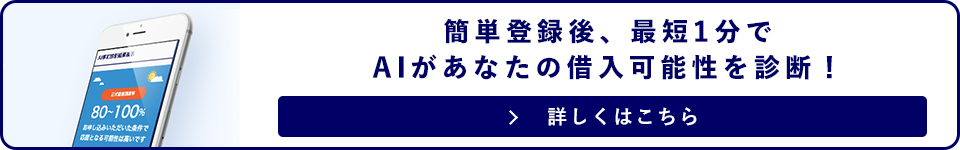35年ローンを組むメリット・デメリット│
利用するなら何歳まで?
掲載日:2021年7月2日

目次
ようやく収入が安定してきたけれど、今から住宅ローンを最長35年で組んでも大丈夫?と不安に感じていませんか?金融機関の多くは、申込時点での年齢と、最終返済時の年齢を定めているため、ローンがきちんと組めるかどうかは非常に気になるところかもしれません。この記事では、35年で住宅ローンを利用した場合のメリットとデメリット、注意点について解説します。住宅ローンを35年間の利用で検討している方は、ぜひ参考にしてください。
1. 35年ローンを組むメリット・デメリット
近年では50年ローンを取り扱う金融機関も出てきましたが、ほとんどの金融機関では、返済期間は最長35年となっています。住宅ローン組む場合のメリットとデメリットは以下の通りです。
メリット
- 1.毎月の返済額が少なくなる
- 2.返済期間が長いほど借入可能額が増加(※)
デメリット
- 1.返済期間が長くなるほど返済総額は増える
- 2.退職後も住宅ローンの返済が残るケースがある
- ※一般的な場合となります。金融機関ごとに審査基準が異なるため実際の借入可能額は金融機関へご確認ください。
それでは、それぞれの項目について解説していきます。
メリット1. 毎月の返済額が少なくなる
借入金額3,000万円、変動金利年率0.625%の住宅ローンを利用した場合の毎月の返済額を見てみましょう。
| 借入期間 | 毎月の返済額 |
|---|---|
| 10年 | 257,958円 |
| 20年 | 133,007円 |
| 35年 | 79,543円 |
計算条件:借入金額3,000万、元利均等返済、ボーナス返済なし、金利は0.625%のまま推移するものとする
このように、借入金額は同じでも、借入期間を延ばすほど毎月の支払額が小さくなります。
メリット2. 返済期間が長いほど借入可能額が増える
毎月の返済額10万円、変動金利年率0.625%で返済期間ごとに借入可能額を計算した結果は以下のようになります。
| 返済期間 | 借入可能額 |
|---|---|
| 10年 | 11,620,000円 |
| 20年 | 22,550,000円 |
| 35年 | 37,710,000円 |
計算条件:毎月の返済額10万円、元利均等返済、ボーナス返済なし、金利は0.625%のまま推移するものとする
返済期間は短くするよりも長く設定した方が、借入可能額が増加していることがお判りいただけるでしょう。
デメリット1. 返済期間が長くなるほど返済総額は増える
返済期間を長くすると、毎月の返済額は少なくなりますが、返済総額は増えてしまうというデメリットがあります。メリット1.で紹介した借入期間と毎月の返済額の表に、返済総額の項目を加えた結果が以下の通りです。
| 借入期間 | 毎月の返済額 | 返済総額 |
|---|---|---|
|
10年 |
257,958円 |
30.954,960円 |
|
20年 |
133,007円 |
31,921,680円 |
|
35年 |
79,543円 |
33,408,060円 |
デメリット2. 退職後も住宅ローンの返済が残るケースがある
仮に35歳で35年の住宅ローンを組んだ場合、完済年齢は70歳。しかし、お勤めの方の場合は、ほとんどの方が60歳から65歳で定年退職を迎えるため、定年退職後は公的年金を主な収入源としながらも、住宅ローンの返済を継続していくことになります。
昨今は、公的年金だけでは必要最低限の生活費をまかなっていくことに不安があるといわれる時代です。定年退職後も、住宅ローンの返済が継続する場合は、ゆとりのある貯蓄額を残しておく、引き続き働いて公的年金以外の収入を確保する、または定年退職による収入減を見込んだゆとりある返済計画にする等の対策が必要になります。
2. 35年ローンは何歳まで組める?

金融機関の多くは、住宅ローンを利用する際には申込時の年齢と、完済時の年齢について制限を設けています。各金融機関によって年齢要件は異なりますが、いずれにしても何歳からでも利用できるわけではなく、利用できたとしても返済が難しくなるケースもあるので慎重に検討することが必要です。
【住宅ローンの利用条件の例】満20歳以上71歳未満で、最終返済の年齢が満81歳未満
- 20歳で35年ローンに申込→完済時は55歳 利用可能
- 35歳で35年ローンに申込→完済時の年齢は70歳 利用可能 ただし定年退職後も残債を支払う必要がある。
- 50歳で35年ローンに申込→完済時の年齢は85歳 利用できません 最終返済の年齢が満81歳未満の要件を満たさないため。
- 50歳で25年ローンに申込→完済時の年齢は80歳 利用できます ただし、返済期間が短いため、毎月の返済額が多いうえ、定年退職後の返済期間も長い点に注意。
合わせて読みたい
3. 【借入額別】35年ローンの返済額シミュレーション
借入額ごとに、毎月の返済額、総返済額の試算例を見ていきましょう。なお、計算条件は元利均等返済、ボーナス返済はなしとします。
【借入金額2,000万円】
| 借入金利(年率) | 毎月の返済額 | 年間返済額 |
|---|---|---|
|
変動金利 0.625% |
53,029円 |
636,348円 |
|
固定5年 0.700% |
53,703円 |
644,436円 |
|
固定7年 0.800% |
54,611円 |
655,332円 |
|
固定10年 0.850% |
55,069円 |
660,828円 |
|
固定15年 1.25% |
58,816円 |
705,792円 |
|
固定20年 1.3% |
59,296円 |
711,552円 |
| 金利上昇時の場合 | ||
|
3.000% |
76,970円 |
923,640円 |
|
5.000% |
100,936円 |
1,211,232円 |
|
7.000% |
127,770円 |
1,533,240円 |
【借入金額3,000万円】
| 借入金利(年率) | 毎月の返済額 | 年間返済額 |
|---|---|---|
|
変動金利 0.625% |
79,543円 |
954,516円 |
|
固定5年 0.700% |
80,555円 |
966,660円 |
|
固定7年 0.800% |
81,917円 |
983,004円 |
|
固定10年 0.850% |
82,604円 |
991,248円 |
|
固定15年 1.25% |
88,224円 |
1,058,688円 |
|
固定20年 1.3% |
88,944円 |
1,067,328円 |
| 金利上昇時の場合 | ||
|
3.000% |
115,455円 |
1,385,460円 |
|
5.000% |
151,404円 |
1,816,848円 |
|
7.000% |
191,656円 |
2,299,872円 |
【借入金額4,000万円】
| 借入金利(年率) | 毎月の返済額 | 年間返済額 |
|---|---|---|
|
変動金利 0.625% |
106,058円 |
1,272,696円 |
|
固定5年 0.700% |
107,407円 |
1,288,884円 |
|
固定7年 0.800% |
109,222円 |
1,310,664円 |
|
固定10年 0.850% |
110,138円 |
1,321,656円 |
|
固定15年 1.25% |
117,632円 |
1,411,584円 |
|
固定20年 1.3% |
118,592円 |
1,423,104円 |
| 金利上昇時の場合 | ||
|
3.000% |
153,940円 |
1,847,280円 |
|
5.000% |
201,873円 |
2,422,476円 |
|
7.000% |
255,541円 |
3,066,492円 |
【借入金額5,000万円】
| 借入金利(年率) | 毎月の返済額 | 年間返済額 |
|---|---|---|
|
変動金利 0.625% |
132,572円 |
1,590,864円 |
|
固定5年 0.700% |
134,259円 |
1,611,108円 |
|
固定7年 0.800% |
136,528円 |
1,638,336円 |
|
固定10年 0.850% |
137,673円 |
1,652,076円 |
|
固定15年 1.25% |
147,041円 |
1,764,492円 |
|
固定20年 1.3% |
148,240円 |
1,778,880円 |
| 金利上昇時の場合 | ||
|
3.000% |
192,425円 |
2,309,100円 |
|
5.000% |
252,341円 |
3,028,092円 |
|
7.000% |
319,426円 |
3,833,112円 |
計算条件:元利均等返済、ボーナス返済なし、金利は借入金利のまま推移するものとし、金利上昇時
想定の借入額や、月々の返済額から返済計画を確かめてみませんか
4. 35年ローンを組むときの注意点

35年ローンを利用すると、月々の返済額の負担を減らすことができるので、上手に利用すれば自分の理想の物件を購入することも可能です。しかし、35年ローンを利用する場合は以下の点に注意をして利用することを心がけましょう。
- 退職金をあてにし過ぎない
- 無理のない長期の返済計画を考える
退職金をあてにし過ぎない
35年で住宅ローンを組んで、完済年齢が定年退職後になってしまう場合の対策として、退職金の多くを住宅ローンの返済原資に充てるという選択肢があります。しかし、この方法は慎重に検討しなければなりません。
厚生労働省がモデルケースでも提示しているように、退職後の生活費は公的年金よりも、貯蓄を取り崩しながら生活していくことが一般的です。したがって、退職金は老後に生活していくうえでの大きな心の支えになります。退職金の多くを住宅ローンの返済に費やすと、手元の貯蓄が大きく減少しますので、慎重に考える必要があるでしょう。
極力、退職金に頼り過ぎず、定年までに完済できるよう、将来に向けての返済計画を立てておくことが望ましいです。もちろん、十分な貯蓄がある場合はこの限りではありません。
無理のない長期の返済計画を立てる
生活をしていくうえでの必要となる支出は、住宅ローンの返済だけではありません。食費や光熱費、保険料、教育費といった支出も住宅ローンの返済に並行して係ってきます。特に子供が高校生、大学生になり教育費のピークになる時期に差しかかると、住宅ローンの返済と重なり家計の負担は大きくなりがちです。
この不安を解消するためには、事前に住宅ローンを利用した場合のライフプランを作成して、現状の収入で、利用したい住宅ローンのシミュレーションをしておくことが重要です。
あらかじめ、支出が大きい時期が予測できているのであれば、その時期に向けて別枠で貯蓄をしておく等の対策を立てることができるでしょう。
また、ライフプランを作っておくことによって、長期の返済計画を立てやすくなります。子供が独立して教育費が落ち着いてきたら、繰上返済を検討することもできるので、定年退職後の住宅ローン対策にもなるでしょう。
住宅ローンは、金利や借入期間で総返済額は大きく異なってきますが、繰上返済を利用すれば利息負担を減らすことが可能です。
一方、住宅ローン利用時に100万円、200万円といった頭金を用意することで、借り入れる元金は少なくなるため、総返済額を減少させる効果があります。
住宅ローンを利用する際は、ライフプランを作成し、長期の返済計画を立てることで、自分に合った住宅ローンが見つかるはずです。
5. 返済総額を意識して返済計画を立てましょう
年齢の制約はありますが、多くの金融機関で最長35年の住宅ローンを利用することができます。しかし、住宅ローンは返済期間が長いほど、毎月の返済額は少なくなりますが、返済総額は逆に減らすことができません。また、公的年金の収入が大半を占める定年退職後に、住宅ローンの返済が終わらなければ、貯蓄の取り崩し額も大きく、お金のストレスを常に抱えたまま老後を過ごすことになります。
そうならないためにも、35年で住宅ローンを利用する際には、頭金を用意したり、将来的に家計にゆとりができた段階で繰上返済を行ったりする等、極力早めに返済できるよう心がけましょう。

金子 賢司
(かねこ けんじ)
ファイナンシャルプランニング技能士1級と同等資格のCFP®や、生命保険資格の最高峰であるTLCを持ち、日本FP協会道央支部に幹事として所属。2017年以降は、確定拠出年金・生命保険・ライフプランに関するセミナーを年間50~100件開催。北海道新聞にもコラム掲載の経験があり、執筆活動にも力を入れている。
ファイナンシャルプランニング技能士1級と同等資格のCFP®や、生命保険資格の最高峰であるTLCを持ち、日本FP協会道央支部に幹事として所属。2017年以降は、確定拠出年金・生命保険・ライフプランに関するセミナーを年間50~100件開催。北海道新聞にもコラム掲載の経験があり、執筆活動にも力を入れている。