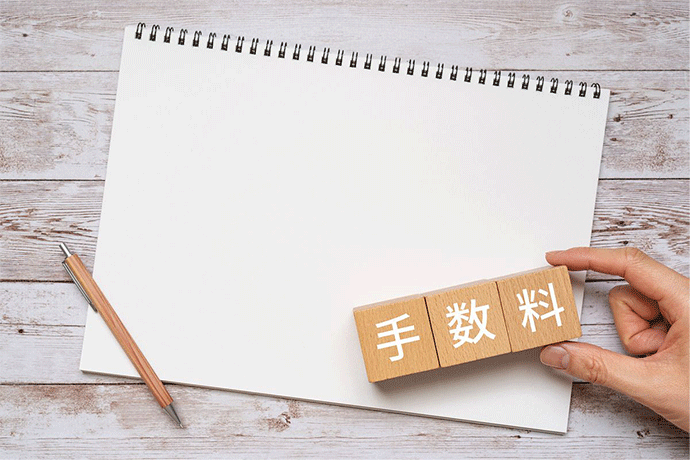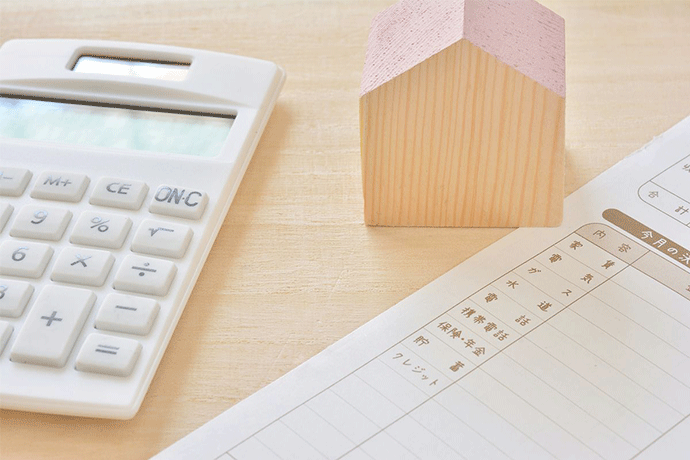年収1,000万円の方の割合は?手取り額や生活レベル、資産運用や節税対策も解説
掲載日:2024年11月29日

年収1,000万円は一般的に高収入と言われ、多くの方の憧れでもあります。
しかし、実際は年収から税金や社会保険料等が差し引かれ、手取り額は大きく下回ります。その金額でゆとりを持って暮らしている方もいれば、お金のやりくりが大変だと感じている方もいるかもしれません。
各世帯の背景を踏まえたうえで、年収1,000万円の場合の生活レベルや、これから始められる節約方法、資産運用や節税対策を確認します。
年収1,000万円の方の割合は?
まず、年収1,000万円の方の割合を、国税庁「令和4年分 民間給与実態統計調査」のデータから紐解きます。1年を通じて勤務した民間の事業所の給与所得者約5,078万人(男性2,927万人、女性2,151万人)への調査結果です。
データから、年収1,000万円前後の給与階級「年収900万円超から1,000万円以下」と、「年収1,000万円超から1,500万円以下」の方の割合をまとめました。
- 年収900万円超1,000万円以下 …… 2.2%(約111万6,000人)
- 年収1,000万円超1,500万円以下 …… 4.0%(約201万9,000人)
上記の結果から、年収1,000万円の方の割合は2.2%+4.0%=6.2%で、給与所得者の「100人に6人」程度と分かります。
さらに、内訳では、男女別、業種別で違いが見られました。
男女別年収1,000万円の方の割合
近年、日本の給与所得者の年収は多様化していますが、男女間での年収差は依然として問題になっています。年収が1,000万円前後の方の男女別統計データは、次の通りです。
<男性>
- 年収900万円超1,000万円以下 …… 3.4%
- 年収1,000万円超1,500万円以下 …… 6.2%
- 合計 …… 9.6%
男性は、年収が900万円以上1,500万円以下に分類される割合が9.6%です。「100人中約10人」が年収1,000万円前後です。
<女性>
- 年収900万円超1,000万円以下 …… 0.6%
- 年収1,000万円超1,500万円以下 …… 1.0%
- 合計 …… 1.6%
一方で、女性の場合は年収900万円以上の方はわずか0.6%、1,000万円を超える層に至っては1.0%にとどまり、年収1,000万円前後の女性は100人中約2人です。男性に比べて圧倒的に少ないことが分かります。
出典:国税庁「民間給与実態統計調査 令和5年」
給与が高い方の割合が多い業種
業種別の給与階級別分布調査では、年収が800万円を超える方が一括りにされており、高給与を得やすい業種が分かります。
最も割合が高い業種は、「電気・ガス・熱供給・水道業」で、全体の43.5%を占めています。
次いで「金融業・保険業」が28.1%、さらに「情報通信業」が23.7%と続きます。
上記の結果では、業界ごとの特性や市場の需要による影響が窺えます。特に電力や金融等インフラに関わる業種は、高度な専門性や責任が伴うため、比較的高い報酬が設定されていると考えられます。
出典:国税庁「民間給与実態統計調査 令和5年」
年収1,000万円の方の手取り額は?
年収1,000万円は高収入と言われますが、税金や保険料が引かれるため、すべてが手もとに入るわけではありません。具体的には、所得税や住民税等が差し引かれた後に残る金額が手取り額になります。
日本の所得税は段階的に課税され、税率は5%から45%までの7段階があります。年収が増えると税率も上がるため、課税される所得金額が高くなると、実際の手取り額は大きく変動します。
一般的に、年収1,000万円の手取りは約700万円から800万円が相場とされますが、会社員か個人事業主かの違い、ボーナスの状況、扶養家族の有無等によっても異なります。
手取り額を正確に把握するためには、個々の状況を考慮する必要があります。
年収1,000万円の方の生活レベルは?
年収1,000万円の生活レベルは、世帯構成によって大きく変わります。
以下は、単身世帯と二人以上の世帯のモデルケースです。
| 項目 | 単身世帯のモデルケース | 二人以上の世帯のモデルケース(子ども1~2人) |
|---|---|---|
|
収入 |
年収1,000万円(手取り約800万円) |
年収1,000万円(手取り約790万円) |
|
月収 |
約66万円 |
約65万円 |
|
家賃 |
15万円(都内の1LDK) |
20万円(都内の2LDK) |
|
食費 |
6万円 |
8万円 |
|
光熱費 |
1.5万円 |
2万円 |
|
交際費 |
5万円 |
5万円 |
|
保険・年金 |
2万円 |
3万円 |
|
子ども教育費 |
- |
10万円 |
|
趣味・娯楽 |
4.5万円 |
4万円 |
|
貯蓄・資産運用 |
32万円 |
13万円 |
例えば、単身世帯の場合、家賃や交際費等の支出が高いものの、手取り額を考慮すると月々の生活費には余裕があり、貯蓄や資産運用に回す余地も生まれます。
一方、二人以上の世帯では、教育費や子育てに関する費用が加わるため、支出が増える傾向にあります。子どもがいる場合、安心して育てるために必要な生活費が高くなることが多く、教育費が月に数万円から数十万円かかるケースもあります。
また、収入が高いと、身なりやスキルアップ、子どもの養育にかける支出が増える傾向があるため、年収1,000万円でも経済的な余裕を感じられないかもしれません。ただし、余った金額を貯蓄や資産運用に回せば、将来の老後資金等必要な費用の準備は可能です。
以上を考慮すると、年収1,000万円は一見高収入に思えるものの、実際の生活レベルは様々な要因が影響し、一律ではありません。
生活維持と将来に備えるための方法

年収1,000万円でも、各種税金や保険料を差し引くと、実際に使えるお金は約2割から3割少なくなります。生活を維持しながら将来に備えるためには、計画的な資金管理が不可欠です。
各世帯の状況に応じて、実践できる方法はいくつかあります。
- 固定費を見直す
- 資産運用を行う
- 節税対策を行う
固定費を見直す
固定費の見直しは、生活費の大幅な削減につながります。
具体的には、家賃や住宅ローン、水道光熱費、通信費、車に関する費用や動画・音楽の配信サービス等のサブスクリプション料金です。
これらの費用を定期的に見直すと、継続的なコスト削減が期待でき、浮いた資金を貯蓄やローンの繰上返済に充てられます。
例えば、家賃を抑えるために、賃貸住宅の引越や、より安い地域への移住等の方法もあります。ただし、引越費用もかかるので注意が必要です。また、住宅ローンは金利の見直しや借換を行うと、月々の支払を軽減できる可能性があります。水道光熱費は、節水や省エネ家電の使用を心がけると削減できるでしょう。
通信費も、料金プランの見直しや格安SIMへの変更でコストを抑えられます。サブスクリプションサービスは、使用頻度を確認して、本当に必要なサービスだけを残すと節約になります。
資産運用を行う
資産運用とは、お金を預貯金や株式、債券、投資信託等の金融商品に分配し、効率的に資産を増やす方法です。
具体的な選択肢には、円預金や外貨預金、株式、債券、保険、投資信託、さらに後述するiDeCo(個人型確定拠出年金)やNISA(少額投資非課税制度)があります。
利用すると、将来の資金を増やせる可能性があります。ただし、元本割れのリスクも伴うため、投資を行う際には慎重な判断が求められます。
それぞれのおおまかな傾向やメリット、デメリットは、次の通りです。
- 円預金……安全性が高い反面、金利は低くなりがち
- 外貨預金……為替リスクがあるが、金利が高い通貨に投資すると利回りを向上させる可能性がある
- 株式投資……リスクが高いものの、長期的には高いリターンを期待できる
- 債券……比較的安全だが、原則として利回りもそれに比例して低くなる
- 投資信託……専門家に運用を任せられる一方で、手数料がかかる
節税対策を行う
節税とは、税制上の制度を活用して支払う税金を抑える手段です。資産運用の一環として、節税対策ができる制度がいくつかあります。
- iDeCo(個人型確定拠出年金)
- NISA(少額投資非課税制度)
これらの制度を利用すると、税負担を軽減しつつ資産を効率的に増やすことが可能です。計画的に活用し、将来の経済的安定につなげましょう。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoとは、自分で申し込み、掛金を拠出して運用する私的年金制度です。この制度では、掛金が全額所得控除の対象となり、運用益も非課税です。また、受け取る際の給付金も一定額まで控除対象となるため、老後資金の準備に役立ちます。
NISA(少額投資非課税制度)
少額投資非課税制度のNISAには、つみたて投資枠と成長投資枠があり、投資を行った際の利益が非課税となります。つまり、資産を増やす際の税負担が軽減され、効率的に資産運用が可能です。年間投資上限額があります。
NISAは2024年から制度が一新され、非課税期間が無期限になり、年間投資上限額が拡大される等、旧NISAに比べて利用者が利用しやすい仕組みになりました。
まとめ
年収1,000万円前後の方は、給与所得者の約6%にあたります。
しかし、年収が1,000万円程度あっても、税金の比率が上がるため、手取りは700万円から800万円程度にとどまります。生活を維持し、将来に備えるためには、日頃の節約や資産運用、節税対策が有効です。
資金が必要な場合は、カードローンの利用を検討しても良いでしょう。みずほ銀行カードローンは、年2.0%から14.0%の金利*でお借入が可能で、ご利用限度額が大きくなるほど金利は低くなります。例えば800万円借入の場合は年2.0%で利用できます。
さらに、みずほ銀行の住宅ローンを利用している方は、特典により基準金利が年0.5%引き下げられ、金利は年1.5%から13.5%になります*。
将来への備えや急な資金ニーズに対応したい方には、低金利で資金調達が可能な選択肢としておすすめです。
また、お手持ちのキャッシュカードにカードローン機能を追加し、手軽に利用できる点も魅力です。ぜひ、みずほ銀行カードローンをご検討ください。
- *お借入金利はご利用限度額に応じて異なります。
カードローンのお申込は
こちら
-
- *ご利用いただける方:ご契約時の年齢が満20歳以上満66歳未満の方で、安定した収入があり、みずほ銀行指定の保証会社である株式会社オリエントコーポレーション(以下オリコ)またはアイフル株式会社(以下アイフル)の保証を受けることができる方
- *カードローンのお申込に際してはみずほ銀行およびみずほ銀行指定の保証会社であるオリコまたはアイフルの審査があります。審査の結果によっては、カードローンご利用のご希望に沿えない場合があります。
- *カード種類は「キャッシュカード兼用型」となります。「キャッシュカード兼用型」には自動貸越機能が付与されます。
- *みずほ銀行、オリコまたはアイフルより申込内容の確認のため、ご本人さまやお勤め先にお電話を差しあげる場合があります。申込時間により、ご連絡が翌日以降(土・日曜日、祝日の場合は翌営業日以降)になる場合があります。なお、ご連絡がとれなかった場合はお申込を取り下げさせていただく場合もあります。
- *お申込の時間帯により、申込後のお手続きのご連絡が翌日以降(土・日曜日、祝日の場合は翌営業日以降)になる場合があります。
- *審査結果の最短当日回答は、みずほ銀行の普通預金口座をお持ちの方に限ります。
- *お申込の際に、パソコンまたは携帯電話のメールアドレスが必要です。必要書類のご登録や審査結果、ご契約内容のご連絡はメールのみとなります。メールアドレスの誤登録にはご留意ください。
- *みずほ銀行のドメイン(@clpf.mizuhobank.co.jp)からのメールを受信できるよう設定してください。
- *メールサービス提供会社が、迷惑メールに関する対応の厳格化を進めているため、お申込時にご登録いただいたメールアドレスにご連絡メールが届かない可能性がございます。ご留意ください。
- *お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、過去にご確認させていただいた、お客さまの氏名・住所・生年月日や、お取引の目的等を、再度ご確認させていただく場合がございます。また、その際に各種書面等のご提示をお願いする場合がございます。
確認にご協力いただけない場合は、カードローンを含めるすべてのお取引が制限される可能性がございますのでご留意ください。
推奨環境
お申込や申込後のお手続きの際は、各ブラウザの最新バージョンを推奨します。
デバイス 対応ブラウザ iOS(モバイル)
Apple Safari
Android(モバイル)
Google Chrome
Windows
Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla FirefoxmacOS
Google Chrome
Apple Safari
Mozilla Firefox- *上表は動作保証をするものではありません。推奨環境でも使用する機種やブラウザによってはご利用いただけない場合や正しく表示されない場合があります。
普通預金口座の開設におけるご注意事項
- *2021年1月18日 月曜日より、普通預金口座は通帳を発行しない「みずほe-口座」での開設となります。(詳しくはこちら)
- *口座開設後、「キャッシュカード」は「簡易書類」「転送不要」にてお送りします。
お受取に際し、以下の事項にご留意ください
- *マンションやアパート等の集合住宅にお住まいのお客さまへ
本人確認書類に部屋番号まで記載があることをご確認ください。本人確認書類に部屋番号まで記載がない場合は、記載のある本人確認書類をご用意のうえ、お申し込みください。
- *「転居・転送サービス」をご利用中のお客さまへ
「転送不要」の郵便物は、「転居・転送サービス」をご利用中の場合でも配達されません。転居されている場合は、現在お住まいの住所の記載がある本人確認書類をご用意のうえ、お申し込みください。
- *表札が出ていない場合、配達されないことがあります。
- *本人確認書類のお名前にある旧字体・異体字でお申し込みされた場合は、新字体のお名前での口座開設となりますので、あらかじめご了承ください。
- *本人確認書類はみずほ銀行が申込内容を確認した時点で有効なものに限ります。有効期限等にご注意ください。
- *年末年始・ゴールデンウィーク等、銀行休業日の関係で通常よりお手続きに日数を要する場合がありますのであらかじめご了承ください。
- *その他にもご利用にあたってのご注意事項があります。お申込の前に必ずご確認ください。
全国銀行協会の全国銀行個人信用情報センターにおいて、2019年3月29日より「貸付自粛制度」がスタートしました。
詳しくは貸付自粛制度のご案内よりご確認ください。
ギャンブル等依存症に関する注意事項や、対処に困った場合の相談窓口はこちらから
監修者情報

内山貴博(うちやま・たかひろ)
- ファイナンシャルプランナー
大学卒業後、証券会社で5年半勤務。その後FPとして独立。日本人のお金に対する知識向上に寄与すべく、相談業務やセミナー、執筆等を行っている。
日本証券業協会主催イベントや金融庁主催シンポジウムで講師等を担当。2018年にはFPの役割について探求した論文を執筆。