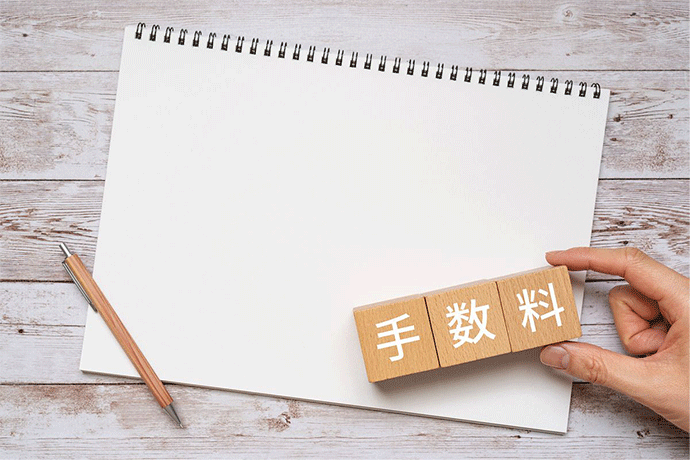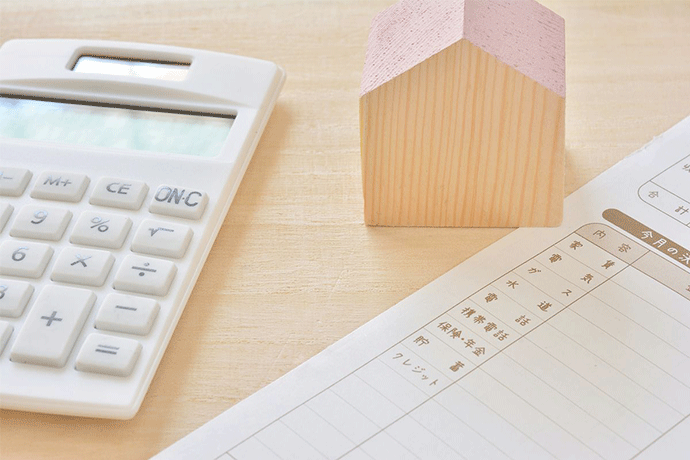引越料金の相場はいくら?見積もりの目安や内訳、抑える方法を解説
掲載日:2024年11月29日

引越料金は世帯の人数や移動距離、シーズン等で変動します。
金額を抑えたいなら、引越料金が高くなる要素を避けましょう。繁忙期や料金が高くなる日時を避ける、運ぶ荷物を減らす、複数の業者から見積もりを取って比較する等の方法が考えられます。
また、引越業者に支払う料金以外にも、引越に際しては様々な出費が発生する点にも注意しましょう。
本記事では引越料金の相場や料金を抑える方法、引越に際して発生する他の費用を解説します。
【人数別】引越料金の相場
引越料金は世帯の人数や移動距離、シーズン、運ぶ荷物の量等で変動するため、一概にいくらとは断定できません。家電設置や梱包・荷解きのサービス等のオプション、時間指定等で、相場よりさらにアップするケースもあります。
新年度からの生活に備えて引越の需要が高まる2月~4月は繁忙期となり、引越料金も割高になりがちです。一方、5月~1月は引越需要が落ち着く通常期なため、繁忙期よりも費用が抑えやすい時期です。引越料金の相場は、繁忙期と通常期で分けて考える必要があります。
【単身者】引越料金の相場
単身者の引越料金相場
| 引越距離 | 通常期 | 繁忙期 |
|---|---|---|
|
~15km未満 |
26,000円~ |
29,000円~ |
|
15km~ |
27,000円~ |
31,000円~ |
|
50km~ |
38,000円~ |
43,000円~ |
|
200km~ |
58,000円~ |
67,000円~ |
|
500km~ |
71,000円~ |
79,000円~ |
単身者は同居家族の都合を考慮しなくて良いため、引越料金を抑えやすい傾向があります。自身の都合が許すなら、繁忙期を避けるだけで大きく節約できるケースもあるでしょう。
【2人暮らし】引越料金の相場
2人暮らしの引越料金相場
| 引越距離 | 通常期 | 繁忙期 |
|---|---|---|
|
~15km未満 |
26,000円~ |
45,000円~ |
|
15km~ |
44,000円~ |
51,000円~ |
|
50km~ |
56,000円~ |
64,000円~ |
|
200km~ |
80,000円~ |
112,000円~ |
|
500km~ |
90,000円~ |
150,000円~ |
世帯の人数が増えると運ぶ荷物も増加するため、単身者よりも2人暮らしの方が引越料金は高くなります。
同居家族の都合も考慮しなければならず、引越時期をずらして料金を下げる方法が使えないケースもあるでしょう。繁忙期の引越を避けられないなら、引越時期以外の部分で料金を抑える工夫が必要です。
【3人以上】引越料金の相場
3人家族の引越料金相場
| 引越距離 | 通常期 | 繁忙期 |
|---|---|---|
|
~15km未満 |
45,000円~ |
53,000円~ |
|
15km~ |
54,000円~ |
62,000円~ |
|
50km~ |
66,000円~ |
82,000円~ |
|
200km~ |
113,000円~ |
117,000円~ |
|
500km~ |
140,000円~ |
202,000円~ |
4人家族の引越料金相場
| 引越距離 | 通常期 | 繁忙期 |
|---|---|---|
|
~15km未満 |
75,000円~ |
90,000円~ |
|
15km~ |
86,000円~ |
100,000円~ |
|
50km~ |
87,000円~ |
12,000円~ |
|
200km~ |
114,000円~ |
180,000円~ |
|
500km~ |
140,000円~ |
229,000円~ |
5人家族の引越料金相場
| 引越距離 | 通常期 | 繁忙期 |
|---|---|---|
|
~15km未満 |
80,000円~ |
90,000円~ |
|
15km~ |
90,000円~ |
95,000円~ |
|
50km~ |
110,000円~ |
150,000円~ |
|
200km~ |
125,000円~ |
200,000円~ |
|
500km~ |
150,000円~ |
230,000円~ |
引越をする世帯の人数が増えるほど、基本的に料金は増加します。引越時期も家族全員の都合を考えなければならず、引越に使える日が限られてしまいます。
小さな子どもや高齢者がいる家庭では、自分たちだけでは荷造り・荷解きが難しく、引越業者のサービスを利用するケースもあるでしょう。
人数の多い引越で料金を下げるには、荷物を減らす、複数の業者から見積もりを取って交渉する等の工夫が大切です。
出典:引っ越し見積もり比較サイト SUUMO「引越し費用・料金の相場」
出典:引越し見積もりサイトLIFULL引越し(旧HOME'S引越し) 「引越し費用の料金相場を調べる」
出典:ミツモア「引越し費用の相場はいくら?業者の見積もり額は人数・距離・時期で増減する」
引越料金の内訳
引越料金は、基本運賃、料金、実費、付帯サービス料で構成されています。
| 概要 | |
|---|---|
| 基本運賃 |
実際にかかった時間または距離から請求される費用 |
| 料金 |
依頼者の都合で車両を留め置く際の料金、休日や深夜・早朝に輸送する際の割増料金等 |
| 実費 |
作業員の人件費、輸送時に発生した高速料金等 |
| 付帯サービス料 |
機器の取り外し・取り付け、防虫、消毒等のサービス利用料 |
| 基本運賃 | |
|---|---|
| 概要 |
実際にかかった時間または距離から請求される費用 |
| 料金 | |
| 概要 |
依頼者の都合で車両を留め置く際の料金、休日や深夜・早朝に輸送する際の割増料金等 |
| 実費 | |
| 概要 |
作業員の人件費、輸送時に発生した高速料金等 |
| 付帯サービス料 | |
| 概要 |
機器の取り外し・取り付け、防虫、消毒等のサービス利用料 |
引越料金を構成する要素のうち、基本運賃は大幅な値下げができません。物流ドライバーの労働条件改善に向けて、国土交通省が標準的な運賃を示しているためです。
休日や深夜・早朝の時間帯は基本的には2割増しの料金が発生するため、これらの時間帯を避けて引越をすれば、料金の節約につながります。なお、割増し料金は事業者独自で設定している場合もあるので、事前に確認しておきましょう。
引越で運ぶ荷物を減らし、少人数で作業を完了できれば実費を抑えられます。引越業者が用意する便利なサービスでも、不要な物は外して自分で行えば付帯サービス料は削減可能です。
引越料金を抑える方法
引越料金の増減に影響する要素のうち、世帯の人数は変更できない部分です。移動距離も仕事や家庭の事情で引越先が決まっているなら、変えようがありません。
一方、引越の時期や荷物の量は、調整可能な要素です。また、時期や荷物量の他にも、工夫次第で引越料金を抑えられます。
以下で紹介する方法を取り入れて、引越料金を抑えましょう。
繁忙期を避けて引越をする
料金相場で紹介しましたが、世帯人数・移動距離に関わらず、繁忙期は全体的に料金が割高です。可能ならば通常期に引越をする方が、料金を節約できます。
予定を合わせられるなら繁忙期に入る前の1月まで、または繁忙期が過ぎた5月以降に引越すると料金は下がります。
ただし、新年度からの勤務に合わせての転居では、繁忙期を避けて引越をするのは困難です。繁忙期を避けられない場合は、他の方法で引越料金を下げる工夫をしましょう。
料金が高くなる日時を避けて引越をする
引越の時期を変えられない場合は、料金が高くなる日・時間帯を避け、引越料金の節約を考えましょう。月末・月初や休日(土日祝日)、引越に縁起の良い「大安」等は引越需要が高く、割増料金が発生する場合があります。
月末・月初からずらしたり、平日に休暇を取って引越ができないか検討しましょう。朝一指定で引越をすれば、引越作業に丸1日使えますが、時間指定料が発生する恐れがあります。午後便やフリー便等を使うと割り引きしてもらえるケースもあるため、活用しましょう。
引越先へ持っていく荷物を減らす
荷物量が多いとトラックの大きさや台数、作業員の人数を増やす必要があるため、引越料金は高くなります。反対に荷物を少なくできれば、必要なトラックを小さくしたり、台数を減らしたり、作業員が少なくても作業を終えられるため、引越料金の値下げにつながります。
引越を機に、身の回りの物を断捨離して荷物を減らせないか考えましょう。また、家具や家電の買い替え予定があるなら引越に合わせて処分すると、運ぶ荷物を効果的に減らせます。
引越業者に荷物の量を正確に伝える
引越先へ運ぶ荷物の量が正確に伝わっていないと、量に対して大きなトラックが手配されたり、運びきれずに追加費用が発生したりする原因です。
余計な費用を払わなくて済むよう、見積もりの際は引越業者に正確な荷物の量を伝えましょう。必要ならば、訪問見積もりしてもらうと引越のプロの目線で荷物の量を把握してもらえます。
引越業者のオプションを減らす
引越業者は競合との差別化を図るため、様々なサービスを用意していますが、自分でできる内容のオプションは外した方が料金を下げられます。
有料オプションの例
- 家電の取り外し・取り付け
- 家具の組み立て
- 荷造り・梱包、荷解き
- 清掃
見積もり内容を確認し、外せるオプションがないか検討しましょう。また、梱包材も引越業者が無償提供してくれるか、有償かを確認し、有償の場合は自分で用意した方が安く済むケースもあります。
引越料金の相見積もりを取る
引越料金の見積もりは、2~5社程度から相見積もりを取り、値引き交渉してみましょう。
訪問見積もりに来てもらう場合、1社目が提示した見積もりで契約を決めず、他社の見積もり結果を見たうえで判断します。他社料金を引き合いに出すと、値引きしてくれる可能性もあります。
引越費用の補助制度を活用する
転勤や通勤時間短縮が目的の引越なら、福利厚生の一環として費用を補助している会社もあります。勤め先が引越費用の補助制度を用意しているなら、活用しましょう。ただし、利用に際して条件が課せられるケースもあるため、確認が必要です。
また、転居先の自治体が条件を満たす世帯に対して、引越費用を補助する制度を設けているケースもあります。引越先に該当する制度がないか、自分たちは対象者に含まれるか確認してみましょう。
引越をするときに発生する他の費用

引越の際は、引越業者に支払う料金の他にも様々な費用が発生します。引越料金だけでなく、他の費用がいくらかかるかも注意しましょう。
もし手持ち資金では費用が不足するなら、何らかの対処法が必要です。クレジットカードの分割払いやカードローンの利用等、自分に合う方法を考えましょう。
退去時にかかる原状回復費
賃貸物件から引越をする場合、明け渡し時に原状回復やクリーニング費用等が発生します。経年劣化ではなく故意や過失で発生させた不具合は、借主側が修繕費用を負担する必要があります。
原状回復にかかる費用は、入居時の敷金でまかなわれるケースが一般的です。しかし、敷金がない物件や、敷金ではまかないきれない大きな損傷がある場合は、費用を請求される恐れがあります。
新居の契約・取得にかかる費用
引越先の新居が賃貸物件なら、敷金・礼金や不動産仲介料等が発生します。他にも、鍵交換や家賃保証会社への保証料の支払が必要なときもあり、まとまった費用が必要です。
マイホームを取得した場合は、購入費用やローンの頭金、登記費用等が発生します。
不用品の処分費用
引越費用を抑えるために家具や家電、持ち物を処分するなら、処分費用も考えましょう。
自治体のごみ回収に出す他、まだ使える物は不用品買取やフリマアプリで売却、または欲しい方に譲る等すれば、処分費用を抑えられます。
家具家電や備品の購入費用
引越に合わせて家具や家電、新居で使う備品を購入するなら、購入費用も必要です。実家から独立して一人暮らしを始めるときは、家財道具を一式そろえるため、購入費用が大きくなります。
資金が足りない場合は買いそろえる物を取捨選択し、必要に応じて分割払いやローンの利用も検討しましょう。
みずほ銀行カードローンは引越にかかる費用にも使えます
引越をするときは、引越業者に支払う料金の他、様々な費用が発生します。引越料金を抑える工夫をしても、手持ちが不足するならば、何らかの方法で補いましょう。
不足資金の補てんには、カードローンの活用も有効です。みずほ銀行カードローンは24時間お申込可能で、幅広い用途に使えます。
審査結果は最短当日でお知らせできます*1。利用限度額は10万円から800万円、金利は年2.0%~14.0%です*2。みずほ銀行で住宅ローンを利用中の方は、年1.5%~13.5%に金利が下がる制度もあります。
- *1審査結果の最短当日回答は、みずほ銀行の口座をお持ちの方に限ります。
- *2お借入金利はご利用限度額に応じて異なります。
みずほ銀行のATMの他、提携コンビニATMからも利用でき、必要なときに素早く借りられるカードローンです。
まとめ
引越料金は、人数と移動距離、シーズン、荷物の量等で変動します。人数や移動距離は変えようのない要素ですが、他の部分は工夫次第で引越料金の節約につながります。
料金を抑えたい場合には、繁忙期を外すと料金が下がります。また、荷物の量を減らしたり、複数の業者から見積もりを取って交渉したりするのも効果的です。
また、引越の際は引越業者に支払う料金の他にも、退去費用や新居にかかる費用、不用品処分等でもお金がかかります。手持ち資金では不足するなら、分割払いやカードローン等、自分に合う方法を考えて対処しましょう。
カードローンのお申込は
こちら
-
- *ご利用いただける方:ご契約時の年齢が満20歳以上満66歳未満の方で、安定した収入があり、みずほ銀行指定の保証会社である株式会社オリエントコーポレーション(以下オリコ)またはアイフル株式会社(以下アイフル)の保証を受けることができる方
- *カードローンのお申込に際してはみずほ銀行およびみずほ銀行指定の保証会社であるオリコまたはアイフルの審査があります。審査の結果によっては、カードローンご利用のご希望に沿えない場合があります。
- *カード種類は「キャッシュカード兼用型」となります。「キャッシュカード兼用型」には自動貸越機能が付与されます。
- *みずほ銀行、オリコまたはアイフルより申込内容の確認のため、ご本人さまやお勤め先にお電話を差しあげる場合があります。申込時間により、ご連絡が翌日以降(土・日曜日、祝日の場合は翌営業日以降)になる場合があります。なお、ご連絡がとれなかった場合はお申込を取り下げさせていただく場合もあります。
- *お申込の時間帯により、申込後のお手続きのご連絡が翌日以降(土・日曜日、祝日の場合は翌営業日以降)になる場合があります。
- *審査結果の最短当日回答は、みずほ銀行の普通預金口座をお持ちの方に限ります。
- *お申込の際に、パソコンまたは携帯電話のメールアドレスが必要です。必要書類のご登録や審査結果、ご契約内容のご連絡はメールのみとなります。メールアドレスの誤登録にはご留意ください。
- *みずほ銀行のドメイン(@clpf.mizuhobank.co.jp)からのメールを受信できるよう設定してください。
- *メールサービス提供会社が、迷惑メールに関する対応の厳格化を進めているため、お申込時にご登録いただいたメールアドレスにご連絡メールが届かない可能性がございます。ご留意ください。
- *お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、過去にご確認させていただいた、お客さまの氏名・住所・生年月日や、お取引の目的等を、再度ご確認させていただく場合がございます。また、その際に各種書面等のご提示をお願いする場合がございます。
確認にご協力いただけない場合は、カードローンを含めるすべてのお取引が制限される可能性がございますのでご留意ください。
推奨環境
お申込や申込後のお手続きの際は、各ブラウザの最新バージョンを推奨します。
デバイス 対応ブラウザ iOS(モバイル)
Apple Safari
Android(モバイル)
Google Chrome
Windows
Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla FirefoxmacOS
Google Chrome
Apple Safari
Mozilla Firefox- *上表は動作保証をするものではありません。推奨環境でも使用する機種やブラウザによってはご利用いただけない場合や正しく表示されない場合があります。
普通預金口座の開設におけるご注意事項
- *2021年1月18日 月曜日より、普通預金口座は通帳を発行しない「みずほe-口座」での開設となります。(詳しくはこちら)
- *口座開設後、「キャッシュカード」は「簡易書類」「転送不要」にてお送りします。
お受取に際し、以下の事項にご留意ください
- *マンションやアパート等の集合住宅にお住まいのお客さまへ
本人確認書類に部屋番号まで記載があることをご確認ください。本人確認書類に部屋番号まで記載がない場合は、記載のある本人確認書類をご用意のうえ、お申し込みください。
- *「転居・転送サービス」をご利用中のお客さまへ
「転送不要」の郵便物は、「転居・転送サービス」をご利用中の場合でも配達されません。転居されている場合は、現在お住まいの住所の記載がある本人確認書類をご用意のうえ、お申し込みください。
- *表札が出ていない場合、配達されないことがあります。
- *本人確認書類のお名前にある旧字体・異体字でお申し込みされた場合は、新字体のお名前での口座開設となりますので、あらかじめご了承ください。
- *本人確認書類はみずほ銀行が申込内容を確認した時点で有効なものに限ります。有効期限等にご注意ください。
- *年末年始・ゴールデンウィーク等、銀行休業日の関係で通常よりお手続きに日数を要する場合がありますのであらかじめご了承ください。
- *その他にもご利用にあたってのご注意事項があります。お申込の前に必ずご確認ください。
全国銀行協会の全国銀行個人信用情報センターにおいて、2019年3月29日より「貸付自粛制度」がスタートしました。
詳しくは貸付自粛制度のご案内よりご確認ください。
ギャンブル等依存症に関する注意事項や、対処に困った場合の相談窓口はこちらから
監修者情報

内山貴博(うちやま・たかひろ)
- ファイナンシャルプランナー
大学卒業後、証券会社で5年半勤務。その後FPとして独立。日本人のお金に対する知識向上に寄与すべく、相談業務やセミナー、執筆等を行っている。
日本証券業協会主催イベントや金融庁主催シンポジウムで講師等を担当。2018年にはFPの役割について探求した論文を執筆。