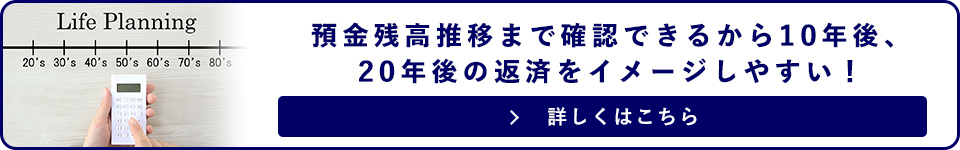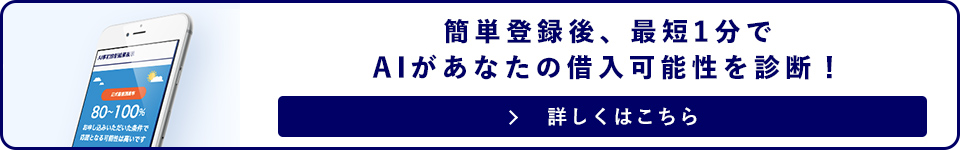住宅ローンの借入期間は何年まで組める?年数を決めるポイント
掲載日:2021年8月6日(2025年9月12日更新)

目次
住宅を購入する際は多額の資金を必要とするため、住宅ローンを契約して購入するのが一般的ですが、借入期間を最長何年まで設定できるのか気になっている方も多いのではないでしょうか?
住宅ローンは借入期間が長ければ良いというものではないため、最長どれだけ借り入れできるかだけでなく借入期間を決めるポイントを事前に理解しておくことが重要です。
この記事では、ファイナンシャルプランナーの矢野 翔一さんに住宅ローンの最長借入期間や平均、借入期間を決めるポイントなどを解説していただきました。
1. 住宅ローンの借入期間は何年まで?
住宅ローンの借入期間は契約者が自由に設定できるものではありません。金融機関によって最長期間が定められており、その範囲内で借入期間が決まります。
借入期間が長く設定されている場合は、一回の返済負担を抑えられる一方、借入期間が長くなるので返済額が大きくなるという点に注意が必要です。
借入期間が短く設定されている場合は、借入期間が短くなるので最終的な返済額は小さくなる一方、一回の返済負担が大きくなるということを理解しておく必要があります。
住宅ローンの借入期間は最長何年まで設定できるのでしょうか?住宅ローンの最長の借入期間について詳しく見ていきましょう。
住宅ローンの最長の借入期間
住宅ローンの一般的な最長の借入期間は35年となっています。しかし、金融機関によっては他の金融機関との差別化を図るために50年まで借りられるプランを提供しているところもあります。
住宅ローンの借入期間は自分で自由に決められるものではありません。完済時の上限年齢を設けている金融機関が多く申込者の年齢が借入期間に影響します。
例えば、完済時の上限年齢が70歳に設定されている場合に40歳で申し込むと最長の借入期間は30年です。
申込時の年齢が高いと、上限年齢の制限によって希望の借入期間が通らないケースもあるので注意が必要です。
住宅ローンの平均の借入期間
実際に住宅ローンを契約している方は、どのくらいの借入期間となっているのでしょうか?
国土交通省住宅局が公表している「令和6年度 住宅市場動向調査 報告書」によると、新築住宅を購入した方の借入期間は、以下のように住宅の種類に関係なく平均30年以上となっています。
| 注文住宅(建築代) | 33.9年 |
|---|---|
| 注文住宅(土地代) | 35.6年 |
| 分譲戸建住宅 | 30.9年 |
| 分譲マンション | 28.2年 |
(出典:国土交通省「令和元年度 住宅市場動向調査報告書」)
中古住宅は新築に比べて借入期間が短めに設定されている傾向があります。
- 中古戸建住宅:25.5年
- 中古マンション:27.7年
平均値が正解というわけではありませんが、一つの目安として覚えておきましょう。
2. 住宅ローンの借入期間を決めるポイント

住宅ローンの借入期間は契約者の希望をある程度は考慮してくれますが、何年に設定すれば良いのか分からないという方も多いと思います。
住宅ローンの借入期間を決める際は、契約後の失敗を防ぐためにも以下の3つのポイントを押さえながら決めることが重要です。
- 毎月返済に充てられる金額はいくらか
- 返済中に発生し得る費用はどれくらいか
- 何歳までに住宅ローンを返し終わりたいか
それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。
毎月返済に充てられる金額はいくらか
現在の収入と支出を考慮して、毎月住宅ローンの返済に充てられる金額がいくらなのかを計算します。
住宅を購入する前は賃貸物件に住んでいるケースが多いため、その家賃を一つの目安として毎月払える金額に収まるように借入期間を延ばしていきます。
借入期間を延ばすことによって毎月の返済額は減りますが、返済総額が増える点に注意が必要です。
返済中に発生し得る費用はどれくらいか
将来どの程度の費用が発生するか考慮しながら、そのタイミングで十分な貯蓄が作れるように借入期間を設定します。
住宅ローンの返済期間は長期間になることがほとんどで、返済中に子供の養育費や進学にかかる費用、結婚費用、自動車の買い替え費用などの費用が生じます。
住宅ローンの返済に重点を置きすぎた場合には、他の費用に回せなくなり生活の余裕がなくなる点にも注意しながら期間を設定しましょう。
何歳までに住宅ローンを返し終わりたいか
人生設計を考慮し、いつまでに返済を完了させたいかを踏まえながら借入期間を決めます。
例えば、定年後まで住宅ローンの返済が残っている場合には、年金や貯蓄から返済を行うことになるので老後資金が減って生活が苦しくなる可能性があります。
老後に安心して暮らすためには、老後に負担をかけないような借入期間を設定することも重要といえるでしょう。
- *60歳以上の方限定の住宅ローン(「リ・バース60」)もご利用いただけます。毎月のお支払いが利息のみで住宅ローンの返済負担を減らし、余暇を充実させることができます。
合わせて読みたい
3. 借入期間の違いによる住宅ローンの返済額シミュレーション

借入期間が長くなれば返済額が大きくなるということについては説明しましたが、具体的にどのくらいの差が生じるのかイメージができない方も多いのではないでしょうか?
自分に合った返済期間を設定するには、借入期間の違いによる住宅ローンの返済額のシミュレーションを行うことが重要です。
<計算条件>
金利:全期間固定 年率3%
返済方式:元利均等返済
ボーナス払い:なし
上記の計算条件に基づいて、借入額2,000万円~6,000万円(1,000万円間隔)、借入期間20年~35年(5年間隔)の毎月の返済額と総返済額をみずほ銀行のシミュレーションを使いながら確認してみましょう。
借入額2,000万円
| 借入期間 | 毎月の返済額 | 総返済額 |
|---|---|---|
| 20年 | 11万919円 | 2,662万560円 |
| 25年 | 9万4,842円 | 2,845万2,600円 |
| 30年 | 8万4,320円 | 3,035万5,200円 |
| 35年 | 7万6,970円 | 3,232万7,400円 |
借入額が2,000万円の場合は、借入期間が20年でも毎月の返済額は12万円を下回っているため、期間を短くして毎月の返済額を増やしても生活に与える影響は小さいと言えます。
返済総額を35年と比べて500万円程度抑えられることを踏まえると、なるべく借入期間を短くした方が良いでしょう。
借入額3,000万円
| 借入期間 | 毎月の返済額 | 総返済額 |
|---|---|---|
| 20年 | 16万6,379円 | 3,993万960円 |
| 25年 | 14万2,263円 | 4,267万8,900円 |
| 30年 | 12万6,481円 | 4,553万3,160円 |
| 35年 | 11万5,455円 | 4,849万1,100円 |
借入額が3,000万円の場合は、借入期間が短いと毎月の返済額が16万円を超えてきます。
共働きで収入が安定している場合は借入期間を短く設定しても問題ありませんが、専業主婦(夫)、産休に入る可能性がある場合は、それらを考慮して借入期間を設定しましょう。
借入額4,000万円
| 借入期間 | 毎月の返済額 | 総返済額 |
|---|---|---|
| 20年 | 22万1,839円 | 5,324万1,360円 |
| 25年 | 18万9,684円 | 5,690万5,200円 |
| 30年 | 16万8,641円 | 6,071万760円 |
| 35年 | 15万3,940円 | 6,465万4,800円 |
借入額4,000万円の場合、借入期間が短いと毎月の返済額が23万円に近づいてきます。
さすがに返済負担が重くのしかかってくるため、返済期間を延ばす方向で検討した方が良いと言えます。収入と支出を考えながら無理のない返済計画を立てましょう。
借入額5,000万円
| 借入期間 | 毎月の返済額 | 総返済額 |
|---|---|---|
| 20年 | 27万7,298円 | 6,655万1,520円 |
| 25年 | 23万7,105円 | 7,113万1,500円 |
| 30年 | 21万802円 | 7,588万8,720円 |
| 35年 | 19万2,425円 | 8,081万8,500円 |
借入額5,000万円の場合、借入期間が短いと毎月の返済額がついに27万円を超えてきます。
毎月の返済額が27万円を超えてくると、余程収入に余裕がなければ返済負担が大きいため、期間を延ばすだけでなく、頭金の割合を増やすことも視野に入れましょう。
借入額6,000万円
| 借入期間 | 毎月の返済額 | 総返済額 |
|---|---|---|
| 20年 | 33万2,758円 | 7,986万1,920円 |
| 25年 | 28万4,526円 | 8,535万7,800円 |
| 30年 | 25万2,962円 | 9,106万6,320円 |
| 35年 | 23万910円 | 9,698万2,200円 |
借入額6,000万円の場合、借入期間が短いと通常のサラリーマンは収入の大半を返済が占めるような状況になってきます。
そのため、5,000万円のケースと同様に、期間を延ばす、頭金の割合を増やすことも視野に入れるほか、購入する住宅の見直しも検討した方が良いでしょう。
4. 住宅ローンの借入期間はシミュレーションしながら決めよう
住宅ローンの借入期間が長ければ、毎月の返済負担を軽減できるため、借入期間を長く設定したいと考えている方も多いのではないでしょうか?
しかし、借入期間を長く設定すると、期間に応じて支払う利息が増えるため、返済総額が大きくなる点に注意が必要です。
そのため、適切な借入期間を設定するには、収入と支出を踏まえてシミュレーションを行いながら毎月の返済額に無理がないかを確認することが重要です。
シミュレーション結果と将来の生活にかかる費用などを踏まえながら、借入期間を決めましょう。

矢野 翔一
(やの しょういち)
2級ファイナンシャルプランニング技能士(AFP)/宅地建物取引士/管理業務主任者の資格を保有し、不動産賃貸業、学習塾の経営に携わりながら自身の経験と保有資格の知識を活かしながら専門家ライターとして金融関係、不動産全般の記事執筆に携わる。
2級ファイナンシャルプランニング技能士(AFP)/宅地建物取引士/管理業務主任者の資格を保有し、不動産賃貸業、学習塾の経営に携わりながら自身の経験と保有資格の知識を活かしながら専門家ライターとして金融関係、不動産全般の記事執筆に携わる。