法人設立費用の相場はいくら?安く抑える方法や設立後の維持費も紹介
掲載日:2025年9月29日起業準備
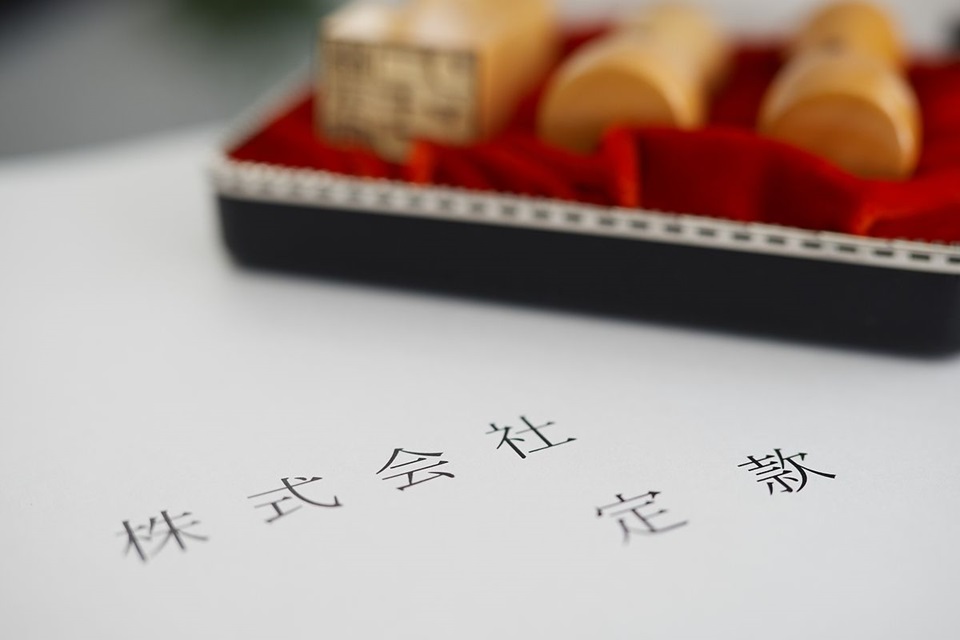
法人の設立費用は、数十万円程度が相場です。ただし、設立する法人の種類や、専門家への依頼の有無によって費用は変動します。
個人事業主から法人化を検討している方や初めて起業する方は、計画的に法人設立費用を用意しなければなりません。
本記事では、法人設立費用の相場や、費用を抑える方法等を詳しく解説します。方法次第で法人設立費用を抑えることも可能であるため、費用を抑えたいと考えている方は参考にしてください。
来店不要でいつでも開設可能(メンテナンス時間:日曜日 0時00分~9時30分を除く)
法人設立時に発生する費用

法人を設立する際に発生する費用は、大きく「法定費用」と「任意費用」に分類されます。
具体的にどのような費用が発生するのか、以下で詳しく解説します。
定款の認証費用
法人設立にあたって、定款の作成が必要です。さらに、株式会社の場合は、作成した定款について公証人の認証を受けなければなりません。
| 紙の定款 |
|
|---|---|
| 電子定款 |
同一情報の交付費用1通700円+(用紙1枚につき20円) |
電子定款の場合、収入印紙代は不要なため、4万円の費用を削減できます。設立費用を抑えたい場合は、電子定款を選択しましょう。
なお、合同会社は定款を作成する必要はありますが、公証人の認証を受ける必要はありません。
関連記事:「定款とは?作り方・記載内容から認証の方法まで分かりやすく解説」
法人の設立登記費用
登記は法人の存在を法的に証明する重要な手続きで、設立登記費用は必ず発生します。設立登記費用は、資本金の額に応じて以下のように変動し、いずれか高い金額が適用されます。
| 株式会社の場合 |
15万円または資本金額×0.7% |
|---|---|
| 合同会社の場合 |
6万円または資本金額×0.7% |
例えば、資本金500万円の株式会社を設立する場合、必要な費用は「15万円」または「500万円×0.7%=3.5万円」です。この場合は高い金額である15万円の支払いが必要となります。
関連記事:「登記とは?法人登記に必要な手続きと必要書類を解説」
資本金
法人を設立するには、1円以上の資本金を用意する必要があります。資本金は「企業の体力」とも呼ばれ、事業に対する意欲や財務健全性の評価に直結する重要な要素です。
今後の事業計画やビジョン等に基づいて、適切な資本金額を決定する必要があります。法人設立時の資本金は、事業が安定するまでの運転資金や初期投資費用、予備費等を考慮しましょう。
また、資本金は対外的な信用度にも影響を与えるため、取引先や金融機関からの信頼を得るには、適切な金額を設定することが求められます。同業他社の資本金を参考にするのも、有効な判断材料の一つです。
関連記事:「資本金とは?その役割と金額を決める際の基準について解説」
会社印の作成費用・印鑑証明書取得費用
法人登記に際し、法務局に書面で申請を行う場合は、会社実印の作成が必要となります。会社の銀行印を実印と併用することも可能ですが、紛失リスクに備えるためにも、「実印・銀行印・角印」の3種類を作成するのが一般的です。
費用は依頼する店舗により異なりますが、低価格で作成したい場合は、3本セットで1万円程度から作成することが可能です。高品質な印鑑を求める場合、材質や彫刻の精度によって数万円かかることもあります。
印鑑証明書を取得するには、法務局へ印鑑登録をしたうえで発行を依頼する必要があります。発行手数料は、請求方法により1枚あたりオンライン請求は420円、窓口での交付請求は500円です*。なお、印鑑証明書は銀行口座開設時等にも必要となるため、複数枚取得しておくと安心です。
- *2025年4月1日時点での手数料です
関連記事:「法人の印鑑証明書を取得するには?印鑑登録の方法から詳しく解説」
専門家への依頼費用
会社設立にあたっては、司法書士に手続きを依頼するケースがあります。依頼する司法書士や業務範囲によって費用は異なりますが、一般的に5~20万円程度の費用が発生します。
法人登記以外にも、営業に必要な許認可を得るときには行政書士に、社会保険や労働保険関連の手続きを社会保険労務士に依頼するケースもあります。依頼する専門家の範囲が広がるほど費用も増加するため、どこまで依頼するかを慎重に検討しましょう。
株式会社と合同会社の法人設立費用を比較
株式会社と合同会社でどの程度の差があるのか、主要な費用項目を比較してみましょう。
| 費用 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 定款認証費 |
3~5万円 |
不要 |
| 収入印紙代(紙定款) |
4万円(電子定款の場合0円) |
|
| 登録免許税 |
資本金額×0.7%または15万円を比較して高い方 |
資本金額×0.7%または6万円を比較して高い方 |
| 印鑑作成費 |
1万円~ |
1万円~ |
| 合計(紙定款) |
23~30万円 |
11~12万円 |
| 合計(電子定款) |
19~26万円 |
7~8万円 |
合同会社は定款認証費用が不要で、登録免許税も低いため、株式会社よりも設立費用を抑えることができます。社会的信用や出資形態に特に制約がない場合、合同会社は有力な選択肢となります。
ただし、費用面のみで法人形態を決めるのは適切ではありません。社会的信用や将来的な資金調達等も含めて、適した法人形態を選択しましょう。
法人設立後に発生し続ける維持費
法人設立時だけでなく、設立後にも様々な費用が発生します。継続的に発生する維持費を把握し、長期的な資金計画を立てましょう。
社会保険料
法人の代表者や役員は、原則として社会保険に加入します。従業員を雇う場合、就業条件次第では社会保険に加入しなければなりません。
健康保険料(介護保険料含む)と厚生年金保険料は労使折半となり、雇用保険は6割程度が会社負担、さらに労災保険料は全額会社負担です。従業員が多くなるほど、これらの社会保険料の負担が重くなるため、人事計画と連動して費用を見積もりましょう。
例えば、月給30万円の従業員1人を雇用した場合、会社負担分だけで月額約4.5万円の社会保険料が発生します。これは年間で約54万円の負担となるため、採用計画を立てる際には採用コストや一連の人件費も考慮しましょう。
関連記事:「会社設立時に必要な社会保険・労働保険の手続きは?基礎から解説」
税金
会社設立後は法人に関連する税金の納付義務が生じ、主な税目は以下の通りです。
- 法人税
- 法人住民税
- 法人事業税
- 消費税
- 地方消費税
- 固定資産税
これらの税金は、年間の利益や資本金額等に応じて納付しなければなりません。特に法人住民税の均等割は、赤字であっても支払う義務があるため注意が必要です。
法人住民税の均等割は、会社の規模(資本金額と従業員数)によって決まります。東京都23区内の場合、資本金1,000万円以下かつ従業員50人以下の会社の法人住民税(均等割)は、年額7万円に設定されています。
この税金は利益の有無に関わらず毎年発生するため、事業計画を立てる際には固定費として必ず考慮しましょう。
消費税は、設立時の資本金が1,000万円未満の場合、設立から2年間は免税事業者となることが可能です。ただし、前々年度の売上が1,000万円を超えた場合や、インボイス発行事業者として登録した場合は課税事業者となります。
店舗や事務所の運営費
店舗や事務所を構える場合、毎月テナント料が発生します。エリアによって費用は異なり、立地が良いほどコストも増大する点に注意しましょう。
利益の有無に関わらず毎月発生する固定費であるため、キャッシュ・フローを圧迫する可能性があります。近年では、コワーキングスペースやバーチャルオフィス等、コストを抑えた事務所の選択肢が広がっています。
仕入れや備品にかかる経費
変動費の代表的として、仕入れ費用や備品購入費が挙げられます。商品やサービスを販売し、利益を得るために欠かせない費用です。
売上に連動して変動するため、常に適切な仕入れの量を管理する必要があります。
福利厚生費
従業員を雇用し、福利厚生制度を導入する場合に発生します。代表的な福利厚生費は、以下のような費用の補助などです。
- 食事手当
- 弁当代補助
- 法定健康診断を超える人間ドック費用の補助
- インフルエンザ予防接種費用
- フィットネスクラブ利用料補助
- 業務に関連する資格取得支援
- 書籍購入費補助
福利厚生の充実は、従業員にとって魅力的な職場を構築するうえで重要です。一方で、会社にとってはコストとなるため、導入の際には持続可能性を検討しましょう。
他にも、在宅勤務制度やフレックスタイム制度等、働き方の柔軟性を提供する福利厚生もあります。
税理士や弁護士等に支払う顧問料
専門家と顧問契約を締結する場合、顧問料が発生します。例えば、税務申告を税理士、法務を弁護士、社会保険手続きを社会保険労務士に依頼する場合等が該当します。
専門的な知識を持たない状況ですべての手続きを行うのは困難なため、必要に応じて専門家に相談しましょう。月々の報酬額は、依頼相手や業務範囲によって異なるため、事前に見積もりを取ることをおすすめします。
法人設立費用を節約する方法

定款を電子化することや、法人形態を合同会社にすること等、法人設立費用を節約する方法は複数あります。
電子で定款を作成する
定款を紙媒体ではなく電子データとして作成すれば、4万円の収入印紙代を節約できます。電子定款作成から受領までの流れは以下の通りです。
- 1.定款を作成する
- 2.定款をPDFに変換する
- 3.電子証明書を取得する
- 4.オンラインで定款の申請を行う
- 5.ウェブ会議で公証人と面談実施・電子署名を行う
- 6.定款を受け取る
なお、電子定款の作成に必要な電子証明書として、マイナンバーカードに付与されている電子証明書を使うことができます。そのため、マイナンバーカードの電子証明書が有効になっていることを事前に確認しておきましょう。
法人形態を合同会社にする
合同会社は定款の認証を受ける必要がないため、認証にかかる手数料や謄本手数料が発生しません。
登記申請の際に納付する登録免許税は、株式会社が最低15万円である一方、合同会社は最低6万円です。資本金の額次第では、9万円の節約につながる場合があります。
資本金を1,000万円未満にする
資本金が1,000万円未満の場合、設立から2年間は原則として消費税が免税となります。ただし、免税事業者がインボイス(適格請求書)発行事業者の登録を受けると、登録日から課税事業者となる点に注意が必要です。
また、自治体によっては資本金と従業員数に応じて、法人住民税の均等割額が変わります。一般的には、資本金および従業員数が少ないほど、均等割額の負担は軽くなります。
雇用ではなく業務委託やアウトソーシングを活用する
従業員を雇用すると、会社には以下の社会保険料の納付義務が生じます。
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 介護保険料
- 雇用保険料
- 労災保険料
業務委託を活用すれば、雇用関係ではなく事業主間の業務委託契約となるため、社会保険料の負担が発生せず、コスト削減につながります。
社内の事務に関しても、事務員を雇用するのではなく専門家にアウトソーシングすることで、コストを抑えられる可能性があります。
ただし、長期的な関係を築く必要がある重要なポジションについては、雇用契約の方が適している場合があります。状況に応じて、雇用と業務委託を使い分けましょう。
法人口座の開設を検討中の方はみずほ銀行へ
法人口座の開設を検討している経営者の方は、みずほ銀行をご検討ください。
みずほ銀行では、原則来店不要の「法人口座開設ネット受付」を行っており、以下の流れで口座を開設できます。
【法人口座開設のお手続き】
- 1.インターネットからお申し込み
- 2.一次審査結果のご連絡と面談日程調整
- 3.ウェブ面談(来店も可能)
- 4.申込書類に必要事項を記入・押印して返送→通帳・キャッシュカード等が届く
みずほ銀行では、インターネット上で24時間365日、法人口座開設の申し込みが可能です。休日深夜を問わずお申し込みでき、移動の手間と時間を省けます。ただし、お客さまによっては、みずほ銀行の店舗にご来店いただく場合がございます。
みずほ銀行で法人口座を開設すると、インターネットバンキング(みずほビジネスWEB)がお申込月から3ヵ月間、月額基本料金が無料で利用できます。さらに、創業期限定特典として、会社設立3年以内かつ「法人口座開設ネット受付」でお申し込みいただいた法人のお客さまは、最大5年間無料になります。
また、みずほ銀行の法人口座を開設すると、事業に役立つ様々なサービスをご利用いただけます。例えば、法人口座からのリアルタイム決済が可能なみずほビジネスデビットが無料で付帯します。みずほビジネスデビットの特典として、福利厚生会社の割引プランもご用意しています。
さらに、スタートアップ企業を支援する会員制サービス「M’s Salon」や人材・スキルマッチングサービスの特典等を提供しており、起業直後の法人をサポートします。
事業に関する様々な悩みを相談でき、事業発展のチャンスを得られるため、ぜひご利用ください。
まとめ
法人設立費用の相場は、設立する法人の形態や専門家へ依頼するかどうかにもよりますが、30~50万円程度の予算があれば十分でしょう。設立時だけでなく、設立後にも継続的にコストが発生する点を踏まえて、資金計画を立てましょう。
法人設立時の費用を節約するには、電子定款の活用や、合同会社の選択を検討してみてください。ランニングコストを抑えるためには、資本金を1,000万円未満にしたり、業務委託やアウトソーシングを活用したりする方法が有効です。
法人設立費用を抑えることも大切ですが、将来の事業展開を見据えた適切な選択も欠かせません。法人設立時だけでなく、その後の事業展開や発展を見据えて、専門家に相談しながら手続きを進めましょう。
来店不要でいつでも開設可能(メンテナンス時間:日曜日 0時00分~9時30分を除く)
監修者

安田 亮
- 公認会計士
- 税理士
- 1級FP技能士
1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。