スタートアップと起業の違いは?事業を成功させるコツも解説
掲載日:2025年7月1日起業準備

スタートアップとは、イノベーションのアイデアを有しており、急成長をめざす企業です。
スタートアップには「起業」という言葉が想起されがちですが、起業は「事業を起こす」という意味合いがあります。急成長をめざすかどうかに関係なく、法人を設立したり個人事業主として新たなビジネスを始める際に、幅広く「起業」という言葉が使われます。
なお、経済の新陳代謝を図り国力を高める必要性から、政府はスタートアップの創業と成長を後押ししています。スタートアップの設立を検討している方は、受けられる支援内容や事業を成功させるためのコツを確認しておきましょう。
目次
スタートアップと起業の違い
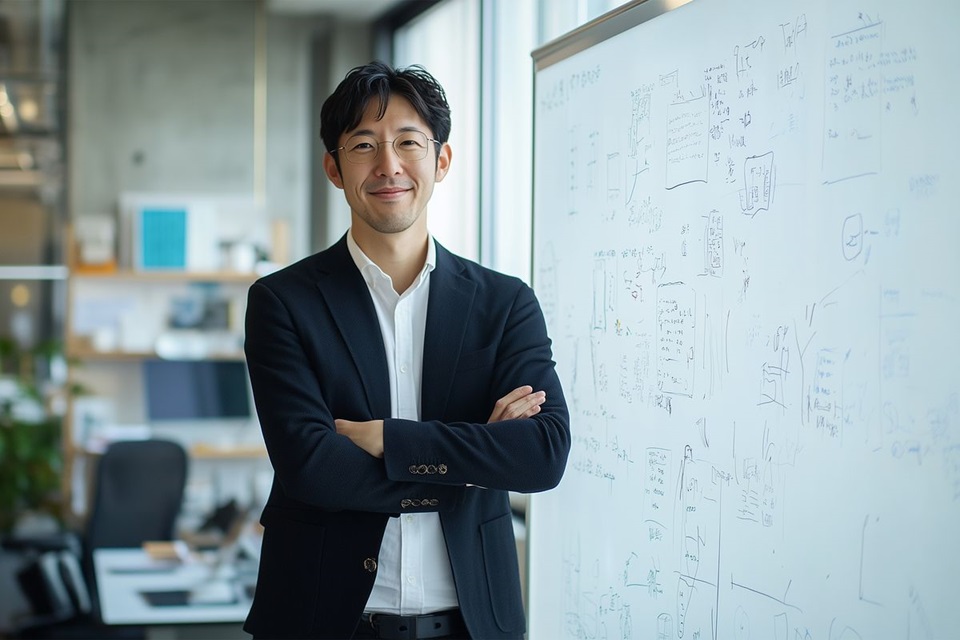
経済産業省によると、スタートアップとは一般的に「新しい企業であって」「新しい技術やビジネスモデル(イノベーション)を有し」「急成長をめざす企業」のことを指します。つまり、スタートアップは一般的に法人格を持つ事業体です。
一方で、起業は「事業を起こす」という意味があり、事業を起こす方法は法人か個人かは問いません。
そのため、新しい技術やイノベーションを有し、急成長をめざす法人を経営する場合は「スタートアップの責任者」といえます。
日本は生産性の低さや開業率の低さ、イノベーションが生まれにくい状況が大きな課題です。しかし、政府は、スタートアップに将来の所得や財政を支える新たな担い手となること、新たな社会課題を解決したり雇用を創出したりする役割を期待しています。
そこで、政府は2022年を「スタートアップ創出元年」と銘打ち、スタートアップ企業を支援するための枠組みの整備を進めています。
スタートアップとベンチャーとの違い
スタートアップと似た意味で使われる言葉に「ベンチャー」があります。「ベンチャー」は和製英語で法的な定義はないものの、革新的な事業をベースに新しい事業やビジネスモデルに挑戦する企業という意味合いで使用されるのが一般的です。
ただし、ベンチャーは外部投資家からの資金調達や、EXITの方法の選択肢がない頃から存在する言葉です。ベンチャーが世間一般的に認知される時点では、「急成長をめざす」という意味合いは含まれていませんでした。
スタートアップは、革新的な事業をベースに新しい事業やビジネスモデルに挑戦するという点ではベンチャーと共通していますが、「急成長をめざす」という要素が加わっている点が特徴です。
スタートアップでの起業を成功させるコツ
スタートアップには、新しい技術やイノベーションの創出が期待されています。政府もスタートアップの支援に力を入れているものの、実際に急成長を実現したり、イノベーションを起こしたりするのは簡単ではありません。
事業を経営する中で様々な障壁にぶつかることが考えられるため、スタートアップの起業を成功させるためのコツを見ていきましょう。
資金調達方法を考えておく
スタートアップが抱える課題の一つに、資金調達の方法があります。新しい技術やイノベーションの創出には、開発費や人件費など様々なコストが発生しますが、十分な資金がなければ計画が頓挫してしまいます。
そのため、持続可能な企業経営を実現し、また必要な資金を得るためにも資金調達方法を考えることは欠かせません。
主な資金調達の方法は以下の通りです。
| 調達方法 | 特徴・メリット |
|---|---|
| 自己資金 |
|
| 金融機関からの借り入れ |
|
| エンジェル投資家 |
|
| ベンチャーキャピタル(VC) |
|
| クラウドファンディング |
|
| 助成金・補助金 |
|
スタートアップが研究開発を始めてから実際に事業化し、投資資金を回収するまでの期間は10年以上かかるケースが少なくありません。スタートアップは、長期的な視野に立って、資金調達の方法を考えることが大切といえるでしょう。
関連記事:「創業時に使える補助金は?助成金・支援金や申請時の注意点も解説」
イノベーションを起こすためのビジネスモデルを明確にする
イノベーションを起こすためには、金融機関からの融資や投資家からの出資等を受けて、運転資金を用意しなければなりません。経済的な援助を受けるためには、自社のビジネスモデルを明確にして、将来性があることを伝える必要があります。
融資をする金融機関からすると、きちんと返済されなければ損失につながります。投資家は将来的なリターンの獲得をめざしているため、イノベーションの実現可能性や将来性がなければ、出資はしないでしょう。
特に自社の商品やサービスを開発している段階では、市場に提供していないため、売上を確保できないケースがほとんどです。赤字が続く状況で事業を継続するためにも、ビジネスモデルを明確にして、金融機関や投資家から「融資・出資する価値がある」と思われる必要があります。
事業計画書を綿密に作成する
事業計画書とは、ビジネスの設計や今後のロードマップをまとめたものです。自分のアイデアを整理し、実現可能かどうかを検証する際に役立ちます。
「自社がどのようなビジネスを展開するのか」「どのようなビジョンを持ってイノベーションをめざすのか」「どのようにマネタイズするのか」を整理するために、事業計画書を作成することをおすすめします。
作成の際には、経営に関する様々なリスクを織り込んだうえで、実現可能性の有無を検討しましょう。また、イノベーションを実現するために必要な資金や、どのように資金調達をするのかも事業計画書に落とし込みましょう。
なお、企業経営に際して、事業計画書の作成は必須ではありません。しかし、自社ならではの強みや今後の事業展開等を言語化すると、方向性を保てるメリットがあります。
融資や出資を受けるときに、事業計画書の提出を求められることもあります。金融機関や投資家へ自社の強みや魅力をアピールするためにも、事業を成功させるプロセスやロードマップ、中長期的な目標等を計画書で示すと良いでしょう。
関連記事:「事業計画書とは?主な記載項目と書き方のポイントを分かりやすく解説!」
スタートアップ・エコシステムに参画する
スタートアップ・エコシステムとは、政府や自治体がスタートアップ企業の創設やイノベーションの促進等を目的として進めている事業です。
スタートアップの起業家だけでなく、政府・自治体・大企業・投資家・専門家(メンター)・研究機関等が集まり、多様な面からビジネスの成長をサポートしています。
スタートアップ・エコシステムに参画することにより、以下のようなメリットが期待できるでしょう。
- 資金調達の選択肢が増える
- 弁護士や中小企業診断士等の専門家からアドバイスを受けられる
- 起業家仲間や先輩起業家等、人脈やネットワークを形成できる
日本は、欧米よりも開業率やユニコーン(時価総額 10億ドル億超の未上場企業)の数が少なく、経済の停滞や国力の低下が問題となっています。
そこで、政府は開業率を高めたり経営者を様々な面から支援したりするために、2022年よりスタートアップ・エコシステムを始めることとしました。スタートアップが陥りやすい課題や悩みを解消するためのアイデアを得られる可能性があるため、エコシステムへの参画は有意義でしょう。
スタートアップを起業するメリット

スタートアップを起業し、社会問題を解決する商品やサービスを開発したり、イノベーションをめざしたりする過程では様々なやりがいを感じられるでしょう。
事業の責任者としてアイデアの実現に注力でき、事業が成功したときに大きな経済的なリターンを得られる点は、スタートアップならではのメリットです。
革新的なアイデアの実現をめざせる
多くの人に役立つ商品やサービスの開発、革新的なアイデアの実現等をめざせる点は、スタートアップを起業するメリットです。企業の規模が小さくフットワークが軽いため、自分が形にしたいアイデアを実現するために注力できるでしょう。
スタートアップは、政府からも社会問題の解決やイノベーションを起こすことが期待されています。金融機関や投資家から、自社の商品やサービスが「革新的なアイデア」と評価してもらえれば、経済的な援助を受けながらアイデアの実現をめざせます。
将来的に大きなリターンを得られる可能性がある
スタートアップ企業にとって、一つの通過点となるのが株式上場(IPO)や事業売却(M&A)です。実際にイノベーションを実現し、新しい付加価値を生み出してIPOやM&Aを成功させると、投資資金以上のリターンを得られます。
株式や事業の評価額にもよりますが、投資資金の数百倍~数千倍ものリターンを得られる可能性もあります。スタートアップを経営する過程では様々な困難や障壁に直面しますが、世の中に大きな付加価値を提供することにより、爆発的に成長する可能性を秘めているのです。
ただし、既に大手企業が幅を利かせている領域では、イノベーションの実現性は低いと言わざるを得ません。競合他社が少なく、ニッチな領域で地位を確立できれば、事業の発展がスムーズに進みやすいでしょう。
組織がスリムで迅速な意思決定ができる
スタートアップ企業を開業したばかりの頃は、組織がスリムです。組織内の合意形成がスムーズに進みやすく、また迅速な意思決定ができるため、思い立ったアイデアを即行動に移せる強みがあります。
フットワークが軽く、インプットとアウトプットを高速で回せる点は、スタートアップの強みです。また、市場環境の変化に応じてすぐに戦略を見直し、他社よりも素早く行動することにより、先駆けとなる商品やサービスを提供できるでしょう。
スタートアップを起業するデメリット
スタートアップを起業した後、事業展開がスムーズに進むとは限りません。認知度の低さがネックになり、資金調達が思うようにいかないデメリットが考えられます。
また、経営者の負担が重くなりやすいデメリットもあるため、起業前にスタートアップの具体的な難しさを確認しておきましょう。
資金繰りで困る可能性がある
スタートアップは、事業実績がなく将来性も不透明であるため、思うように資金調達ができるとは限りません。金融機関からの融資や投資家からの出資は選択肢の一つではあるものの、自社の信用や将来性が評価されなければ、経済的支援を受けられないでしょう。
形にしたい商品やサービスのイメージができていても、資金がなければ事業の継続を断念せざるを得ません。政府としても、スタートアップへの融資や出資が少なく、十分な事業投資がままならずに終わってしまう現状を問題視しています。
スタートアップを起業した後は、収益が安定するまでに長期間の資金調達が必要となるため、「どのように資金調達すべきか」は常に抱える課題といえるでしょう。
経営者の負担が大きい
スタートアップ企業はフットワークが軽く柔軟な意思決定ができる一方で、経営者の負担が重くなりやすい特徴があります。
商品やサービスの開発だけでなく、以下のように様々な業務を行わなければなりません。
- 市場調査
- マーケティング
- 資金調達
- 営業活動
- 人脈作り
- 組織作り
幅広い業務を自ら行う必要があるため、かなりの労力がかかるでしょう。
開業して間もない頃は、少人数で事業を推進することが多いでしょう。各メンバーにかかる業務量が多いと、過重な負担になるかもしれません。
スタートアップを起業する際は法人口座を開設しよう
スタートアップを起業する際は、会社のお金を厳格に管理し、資金の流れを正確に把握するためにも法人口座を準備することをおすすめします。
法人口座があることで、「適切に事業を営んでいる法人である」という印象を受けやすくなり、取引先や顧客から事業理解を得たり、信頼の獲得や事業の拡大等に良い影響が出たりする可能性があります。
また、みずほ銀行では以下のような業務に役立つサービスを提供しています。
- 便利なインターネットバンキング「みずほビジネスWEB」
- 法人口座からのリアルタイム決済が可能な「みずほビジネスデビット」
- 電子帳票に対応した「みずほWEB帳票サービス」
- 人材を確保するために必要なスキルマッチングサービスの提供
- 提携している会計ソフト・電子契約ソフトを一定期間無料で利用できる特典
実際にみずほ銀行の法人口座を開設いただいた方からは、「スタートアップフレンドリーなメガバンク」というお声もいただいております。
スタートアップを起業する際に法人口座を開設したいとお考えの方は、ぜひみずほ銀行をご利用ください。
関連記事:「LinkX Japan株式会社/注目のAI業界スタートアップ!創業期を後押しする銀行サービスの数々」
関連記事:「新設法人が法人口座を開設するメリットは?口座開設の流れやポイントも紹介」
まとめ
スタートアップは、企業の一形態です。ベンチャー企業よりも狭義で、急成長やイノベーションをめざしている特徴があります。
スタートアップを起業する際に事業を発展させるためにも、資金調達方法やイノベーションを具現化するためのアイデアを考えましょう。
政府はスタートアップ・エコシステムの整備を進めて、スタートアップの成長と発展を支援しています。経営のノウハウを学んだり、専門家から客観的な意見を聞けたりするため、エコシステムへの参画も検討してみてください。
スタートアップ企業を設立する際は、法人口座の開設がおすすめです。みずほ銀行では、経営相談や業務に役立つサービスの提供を通じて、スタートアップを支援しています。
会員限定の「M’s Salon」では、会員企業に対してビジネスマッチングの機会や、経営力・事業遂行力に長けているメンターによる各種セミナーを開催しています。ベンチャーキャピタルとのマッチングも行っており、様々な面でスタートアップの急成長をサポートします。
監修者

内山 貴博
- 1級FP技能士
- CFP
大学卒業後、証券会社の本社で社長室、証券業務部、企画グループで5年半勤務。その後FPとして独立。金融リテラシーが低く、資産運用に保守的と言われる日本人のお金に対する知識向上に寄与すべく、相談業務やセミナー、執筆等を行っている。
日本証券業協会主催「投資の日」イベントや金融庁主催シンポジウムで講師等を担当。
2018年に日本人の金融リテラシー向上のためのFPの役割について探求した論文を執筆。