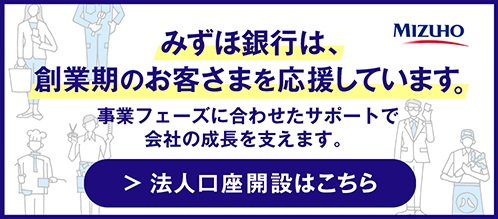LinkX Japan株式会社/注目のAI業界スタートアップ!創業期を後押しする銀行サービスの数々
「日本のAIインフラになる」というビジョンを掲げ、2023年に創立したLinkX Japan株式会社。AIを用いた研究開発、生成AIの基盤でもあるGPU*を駆使した新たなマーケティング手法等、AIを駆使して、ビジネスの立ち上げからグロースまでを支援するテクノロジーカンパニーです。無料の相談窓口である「AI総合研究所」のサービスでは、ローンチから半年足らずのうちに、誰もが知る大企業をはじめ既に400を超える企業から問い合わせが続いている状況とのこと。企業の課題解決にAIで挑む、代表取締役 坂本 将磨氏に、事業の展望やみずほ銀行との出会い、心が動いたエピソードなどをお伺いしました。
LinkX Japan株式会社 代表取締役 坂本 将磨
東京工業大学大学院技術経営修士取得(研究領域:自然言語処理、金融工学)。
NHK放送技術研究所でAI、ブロックチェーンを活用したメディア技術研究に従事。シンガポールでのIT、WEB3事業の創業と経営を経て、LinkX Japan株式会社を創業。
———起業のきっかけを教えてください。
私は、新卒で日本放送協会に入社し、その中にあるNHK放送技術研究所で研究者として勤務していました。当時、メディア活用を前提としたAI領域の研究をしていたのですが、ちょうどインターネット広告とTV広告が逆転する転換期だったこともあり、メディアの形について自問自答をしたり、「企業の発信やPRをTV以外のメディアやSNSでのアプローチに拡大していくことの可能性」について考えるようになりました。
また、近年「生成AI」が世間で非常に話題になり始めましたが、生成AIがあれば業務効率化が実現できるという単純なものではなく、正しい使い方やユースケース*を発信する存在がまずあって、それを実態に合わせながら取り込んでいった先に業務効率化や新しい事業が成り立つのだ、という強い想いがありました。
映像メディア出身だからこそできることがある、自分のAI技術と知識をいかしながら日本のIT技術の遅れを解消したい、と起業に至りました。
———御社の事業内容について教えてください。
大きく分けると二事業がありまして、「AI総合研究所」にて開発支援および研修事業など主としたAIを導入したい法人様向けの伴走事業とAIを活用したSaaS(サーズ)事業です。
———主要事業である「AI総合研究所」とは具体的にどんなサービスですか。
弊社の運営する「AI総合研究所」は最新のAIについて深掘り、分かりやすく発信するAI導入の総合窓口です。サービス開始から数か月でこの業界では国内で2番目にトラフィックの多い総合メディアになりました(取材日時点)。こちらは、無料の相談窓口として開放しており、AIを導入したい法人に対して、AIの使い方や研修、サービス選定、AI開発、コンサルティングまでEnd-to-Endで伴走支援を行なっています。ありがたいことに、大手企業をはじめとした多くの企業さまにこの窓口をご活用いただいています。

———生成AIコンサルティング事業の具体事例などを教えてください。
製造業や金融機関をはじめ、IT、観光、エンターテインメント業界など、上場企業を含む多くの企業から、AIに関する多数の引き合いをいただいております。具体的には、企業のワークフロー改善や、企業データのAIによる学習と活用、画像・動画生成の実活用を支援することで、業務効率の向上にとどまらず、マーケティングやプロモーション活動における効果も最大化しています。さらに、私たちは生成AIを活用したコンテンツ生成のみならず、生成されたコンテンツをどのように活用すべきかという視点からもマーケティング戦略の最適化支援を提供しています。これにより、企業が生成AIを通じてビジネスの成長を加速できるよう、包括的なサポートを行っています。
———SaaS(サーズ)事業*についても詳しく教えてください。
魅力的な企業を知ってもらう、知りたい人に情報を届けたいという思いから、「AI Marketer」という、AIを用いて多チャネルのマーケティングを自動化し、インバウンドマーケティングを支援するサービスを開発・運用しており、現在特許も申請中です。このサービスにより、いわゆるCMS*といわれるコンテンツを管理する機能と、コンテンツ生成、SNSマネジメントをトータルでご提供することができます。AIで文章のロジックを考え、裏側の検索アルゴリズム*との適合も考慮した自動化を実現することで、本来だったら10時間かかっていたような一本の記事を大体2、3時間で仕上げることができ、アルゴリズム面からもかなり質の高いものができることになります。自社運営メディア「AI総合研究所」が成功していることが、この「AI Marketer」の実力を証明しているとも思っています。
今後、GPU技術の進化により、コンテンツ生成やマーケティング自動化の精度とスピードが飛躍的に向上することが期待されています。特に、生成AIや自然言語処理の分野では、GPUの並列処理能力を活用することで、リアルタイムでより複雑なデータ解析が可能となり、個々の顧客行動を瞬時に予測・解析し、それに基づいたパーソナライズドコンテンツを提供できるようになります。これにより、企業はより迅速にターゲットに最適な戦略を展開し、マーケティング活動の効果を最大化することができるでしょう。さらに、現代においては、特にZ世代がSNSを主な情報源とし、そこから購買意欲が形成される傾向が顕著です。「AI Marketer」のSNSマネジメント機能は、オウンドメディア*で生成された記事コンテンツを、X(旧Twitter)、LinkedIn、Facebook、Instagramの4つの主要SNSプラットフォームに最適化されたテキストとビジュアルに自動変換します。これは、各プラットフォームごとに異なるユーザーの嗜好やアルゴリズムに対応するために、強力な処理能力を駆使してリアルタイムで最適化を行うことで可能にしています。
実際にXでバズる投稿とFacebookでバズる投稿というのは、刺さる言葉や画像など全く異なってくるんですよ。
———つまり、オウンドメディア用に生み出された一つのコンテンツが、自動的に各SNSの特徴に応じた形に展開されるということですね。
そうです。事前に学習したAIが各SNSプラットフォームでバズりやすい言葉などを自動的に考えてくれ、全てのSNSが連携されているので、SNS投稿や管理が圧倒的にラクになります。
———SaaS事業のクライアントさまは、BtoB法人からBtoC法人まで幅広くいらっしゃるのでしょうか?またBtoB法人であってもやはり、昨今はSNSの強みが必要とされるのですか?
はい、BtoBもBtoCもいずれもいらっしゃいます。BtoB企業は「SNSよりはコンテンツ生成とCMS」と言われることが多い一方で、BtoC企業だと「コンテンツ生成よりはSNSとCMS」という傾向があり、その企業さまに一番必要なものをご提案させていただいています。ただ最近では、BtoB企業においても、BtoC企業においてもインバウンドのリード獲得は非常に重要で、マーケティングの形態の変化してきています。商売の相手として個人を想定していないBtoB企業でもSNSの重要性を強く感じている、という声も多くなっており、トータルでご提案ができる当社サービスの意義を感じております。

———ここからは、みずほ銀行との出会いについて教えてください。数ある銀行の中で、みずほ銀行を選んだ理由はどんなところにあったのでしょうか。
前職の時から、近隣にみずほ銀行の店舗があり親しみを持っていたというのも大きいのですが、何より「スタートアップフレンドリーなメガバンク」の印象が、圧倒的に強かったというのが一番です。周りの起業家仲間からも、みずほ銀行で口座開設し融資を受けた、みずほグループのファンドから出資を受けた、という声を多く聞いていたので、親身に動いてくれる銀行なんだろうなというイメージがありました。
そんな中、渋谷区の創業融資支援の担当者さんから「スタートアップの状況を理解しながら動いてくれる銀行だ」とお聞きしたのも決め手の一つになりました。
———ウェブ面談で法人口座開設ができることを元々ご存知でしたか?
いえ、知らなかったですね。みずほ銀行に口座を開設したい、と調べる中で店舗に行かなくてもいいと知り、とにかく忙しい創業期にはありがたかったです。やりとりもスムーズで、先延ばしにしがちなタスクを着実に終わらせることができました。
「スタートアップではメガバンク口座を作りにくい」というイメージは、正直なところあったのですが、入り口から親身なやりとりをしていただき、事前の期待通りでした。
———みずほ銀行との取引で印象的だったことはありますか?
創業融資でお世話になったエンゲージメントオフィス*の担当者さんとのやりとりが印象に残っています。非常にスタートアップのことをよく理解されていて、その時に、スタートアップフレンドリーな銀行だなと改めて思いました。また、私達は協調融資という形で、日本政策金融公庫さんと一緒に融資をいただいたのですが、その際に担当者間でスピーディに連携いただき、両行とも希望通りの融資を受ける事ができました。私達も、やはりファイナンスの知見が足りていなかったので、みずほ銀行さんが主導して取り次いでくれたのは大変ありがたかったです。
- *エンゲージメントオフィス・・・中小企業のお客さまに伴走するリモート営業組織
———銀行と法人のお客さまとのやりとりは、「対面」のイメージがまだまだ根強いのかなと思います。実際に、口座開設から融資まで「リモート」での手続きを経験されてみて、ご感想はいかがですか?
スタートアップ企業はIT系が多いと思うので、ウェブ面談であること自体が、まずスタートアップフレンドリーそのものなのかなと感じます。初回融資の最後だけはオフィスにお邪魔して、実際に顔を合わせて実行を受けたのですが、中間の細かいやり取りは、全部ウェブ面談とメールでやり取りができました。創業期の多忙な時に、自分の事業に集中しながら進められたというのは、非常に大きかったと思っています。融資に関しても、一度実績ができてからのやりとりは非対面での完結が多いと聞いており、頼れる専門家につながる窓口として信頼しています。今後もエンゲージメントオフィスの皆さんに色々とご相談できればと思っています。
———「みずほビジネスデビット」をご活用いただいていますが、元々法人用のデビットカードの存在はご存知でしたか?
いえ、知らなかったです。もちろん、起業時に法人用のカードは絶対に必要だと考えていましたが、まずは口座を作らないと、と思っていたところで、口座開設と同時にデビットカードが作れることをご案内いただきました。使ったタイミングで口座からリアルタイムに落ちるのが、時間効率的な面、分かりやすさの点で圧倒的に使いやすいですね。
あとは限度額の点もメリットを感じています。口座残高より使い過ぎないという安心感がある点と、機動的に使う金額を決められる点、例えば攻めのタイミングで、たくさん使いたいのに限度額があってできない・・・というフラストレーションがない両方の観点で魅力に感じます。いくら使ったのか、詳細もスマホからすぐ確認できるのも助かります。

———これからも、御社の成長のそばにみずほ銀行がい続けられたら嬉しいです。最後に、今後の展望をお聞かせください!
これから世界は、AIを起点にビジネスだけでなく生活スタイルも大きく変わっていきます。弊社は、日本のAI普及を適切な形で支援する身近で頼りになる企業であり続けたいと思っています。今私たちが注力しているAIを用いたデータの蓄積に基づく画像生成、動画生成の領域は、ビジネスの常識を変える可能性を秘めています。SNSなどのコンテンツ生成からマーケティングまで行い、様々なメディアのチャンネルに届けていきたいと思います。特に企業の独自データと画像と動画コンテンツ生成を使ったデジタルマーケティングの領域に対してトータルでアプローチを行い、まずは日本で一番、AIとマーケティングを効果的に使いこなしているスタートアップ企業としての地位を確立していきたいと考えています。それ自体が、日本が今外貨を稼いでいるコンテンツ産業においてまさしく「AIインフラになるということ」に直結すると信じています。私たちのサービスを多くの方々にご利用いただくことで、コンテンツ生成の効率性を大幅に向上させ、皆さんがより質の高いコンテンツを作り上げられるようサポートしていきます。
私たちは企業のAI導入の成功を全面的にバックアップします。自社データの効果的な活用、業務フローにどのようにAIを組み込むか、新しい領域でもある画像・動画生成の現場への活用方法など、最先端の知見をもとに全面的にサポートいたします。「AI総合研究所」を起点として、日本のAI活用のハブとなるようなスタートアップ企業になれたらいいなと思っております。私達は、データ活用とAIをキーワードとして企業がAI活用を進めるための、AIのインフラになるという事にフォーカスして事業展開をしていきたいですね。
【本文中注釈】
- *GPU・・・パソコンで処理した画像などを画面に描写するために使われる画像処理装置。
- *ユースケース・・・システムの利用例や活用事例を指し、システムの利用者がシステムとどのように関わるか明確にしたもの。
- *SaaS(サーズ)・・・サービス提供事業者(サーバー)側で稼働しているソフトウェアを、インターネットなどのネットワークを経由してユーザーが利用できるサービス。
- *CMS・・・キャッシュ・マネジメント・システム。CMSは、ウェブサイトのコンテンツを構成するテキストや画像、デザイン、レイアウト情報などを一元的に保存・管理するシステム。ブラウザ上から管理画面にアクセスして、ウェブサイトの更新を行うことができる。ウェブの専門的な知識がなくても、簡単にサイトコンテンツの変更・管理を行うことができる。
- *アルゴリズム・・・検索エンジンが検索結果に表示するウェブページの順位付けを行う計算式。
- *オウンドメディア・・・自社で保有しているメディアという意味、自社のウェブサイトやブログ、SNSアカウントなど。