資金調達とは?主な3つの方法とそれぞれの特徴を分かりやすく解説!
掲載日:2023年1月10日 資金調達

会社経営において資金調達は大きな課題になることがあります。「資金調達の方法が分からない」「自社に合った資金調達方法が分からない」などの悩みを抱える経営者も少なくありません。資金調達の方法はいくつかありますが、目的や状況に合った適切な方法を選択する必要があります。
本稿では、資金調達方法の主な種類と、それぞれの特徴や注意点を解説します。自社に適した資金調達方法を選ぶ参考として、ぜひご参照ください。
資金調達とは?

資金調達とは、会社経営に必要なお金を外部から集めることです。会社経営では、以下のようなタイミングで資金調達が必要になることがあります。
- 会社を設立するとき
- 既存事業を拡大・新事業を開始するとき
- 運転資金を拡充するとき
会社を設立するときに事務所や店舗を構える場合、賃料や設備投資の資金を用意しなければなりません。また会社設立直後はすぐに売上が確保できない可能性もあるため、数ヵ月分の運転資金も確保する必要があります。
そして既存事業の拡大や新規事業の立ち上げのタイミングでも、従業員や仕入れを増やす場合は運転資金の拡充が欠かせません。
このように会社経営では資金調達が必要になる局面は多くあります。入念に事業計画を立てて資金が必要になるタイミングを見極め、計画的に資金調達できるようにしておきましょう。
主な3種類の資金調達方法

資金調達方法は、大きく融資・出資・資産活用の3種類に分類できます。
| 資金調達方法の種類 | 特徴 |
|---|---|
|
融資を受ける(デットファイナンス) |
政府系金融機関や民間金融機関、地方自治体などからお金を借りる。元本に利子を加えて返済しなければならない。 |
|
出資を受ける(エクイティファイナンス) |
投資家などから資金を提供してもらう。資金の受け手側に返済義務がない代わりに、出資比率に応じて議決権を与えたり、利益が出ると配当金を出したりする必要がある。 |
|
資産を活用する(アセットファイナンス) |
会社が保有する資産を担保にして資金を調達する。資産を売却して資金を作る。 |
それぞれの詳しい特徴や具体的な方法について、以下に解説します。
融資を受ける(デットファイナンス)
融資とは、政府系金融機関や民間金融機関、地方自治体などから資金を借り入れることです。融資で調達したお金は、貸借対照表上で負債の欄に分類されることから「デットファイナンス」とも呼ばれます。
第三者からお金を借りている状態なので、借り入れた資金(元本)を返済する際は利子を上乗せしなければなりません。
なお、融資には複数の種類があり、借入先によって金利や保証料、審査難易度などが異なります。融資の種類ごとの特徴は、以下の表の通りです。
| 融資の種類 | 特徴 |
|---|---|
|
日本政策金融公庫による融資 |
事業者への支援を目的とする政策金融機関。 |
|
地方自治体による制度融資 |
地方自治体・金融機関・信用保証協会が連携して、中小企業者の資金調達を支援する制度。 |
|
信用保証協会の保証付き民間金融機関による融資 |
信用保証協会による保証を受け、金融機関から融資を受ける方法。 |
|
民間金融機関によるプロパー融資 |
信用保証協会の保証を受けずに、金融機関から直接受ける融資。 |
|
ビジネスローン |
事業用資金に特化したローン商品。 |
- *本稿の内容については一般的な情報であり、必ずしもみずほ銀行の見解を示すものではありません。
出資を受ける(エクイティファイナンス)
出資は、投資家などの第三者から資金を提供してもらう調達方法です。貸借対照表の資本の欄に分類されることから「エクイティファイナンス」とも呼ばれます。
融資とは違い、出資によって調達した資金の返済義務は発生しません。ただし、出資者に対して出資比率に応じた議決権を付与する必要があります。
出資方法の種類は、大きく分けて以下の3つです。
| 出資の種類 | 特徴 |
|---|---|
|
株主割当増資 |
既存株主に対し、持株数に応じて有償で新規株式を発行して資金調達する方法。新たな株主に割り当てることによる議決権の分散を避けたい場合に有効。 |
|
第三者割当増資 |
業務提携先や取引先、取引金融機関、自社の役職員といった特定の第三者を対象に、有償で新規株式を発行して資金調達を実施する方法。 |
|
公募増資 |
不特定多数の投資家に対して新たに株式を発行する方法。上場企業が資金調達をする際に利用することが多い。新たな株主からの出資が期待できるため、多くの資金を調達したい場合に適している。 |
- *本稿の内容については一般的な情報であり、必ずしもみずほ銀行の見解を示すものではありません。
資産を活用する(アセットファイナンス)
アセットファイナンスは、不動産や売掛金といった資産を活用して資金を調達することです。保有する資産の価値に基づいて資金を調達するため、小規模な会社など審査に不安がある場合でも利用しやすい資金調達方法です。
アセットファイナンスの手法の代表例と、それぞれの特徴は以下の通りです。
| 資産活用の手法 | 特徴 |
|---|---|
|
動産担保融資 |
棚卸資産などの動的資産を担保に融資を受ける。無担保の融資よりも金利などの条件が有利になりやすく、不動産を保有していなくても利用できることがメリット。 |
|
固定資産の売却 |
会社が保有する機械設備や不動産などの有形固定資産、借地権や商標権などの無形固定資産を売却する。使っていない土地や建物を売却することで、固定資産税や管理コストの削減にもなる。 |
|
ファクタリング |
売掛債権をファクタリング会社に売却して資金を調達する。支払期日よりも先にお金を受け取れるので、資金繰り改善につながる。手数料が差し引かれるため、調達できる資金は売掛金の金額より少なくなる。 |
|
リースバック |
保有している不動産を売却した後、その物件を賃貸契約してそのまま利用する。賃貸契約をしているので、売却後も変わらず不動産を使用できる。 |
- *本稿の内容については一般的な情報であり、必ずしもみずほ銀行の見解を示すものではありません。
資金調達方法の違いによるメリット・デメリット
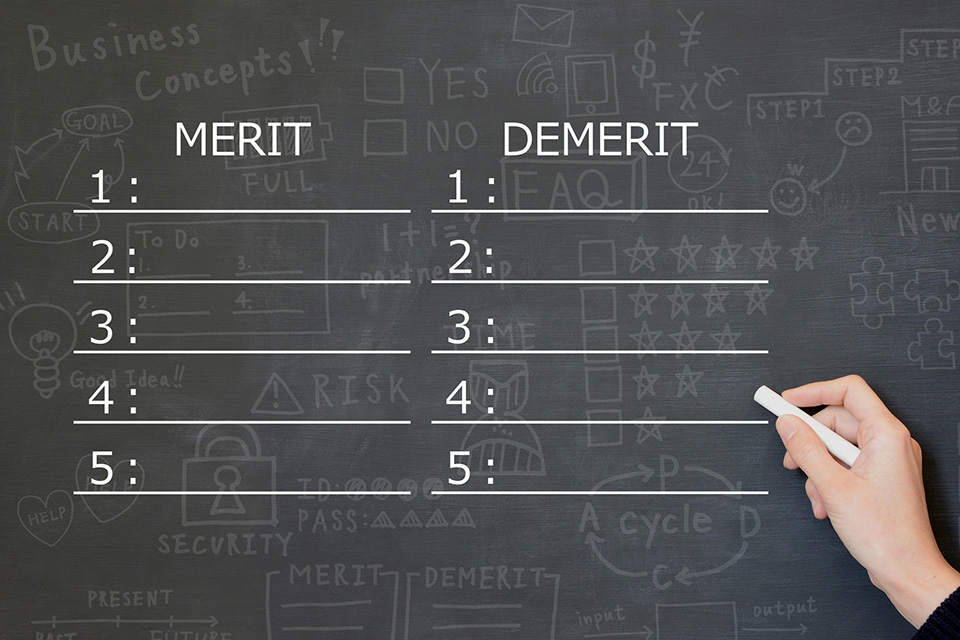
どの方法で資金調達すれば良いかを判断するには、それぞれのメリット・デメリットを把握することが重要です。ここでは3つの資金調達方法(融資・出資・資産活用)について、それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説します。
融資による資金調達のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
政府系金融機関や民間金融機関、地方自治体など、融資はお金の出どころが明確です。そのため、比較的安心して利用できる点がメリットです。また、返済義務を伴わない出資と違って調達した資金は返済するため、第三者に経営権を渡す必要がありません。
一方で、利子の支払が発生する点に注意が必要です。借入額が多く、借入期間が長く、金利が大きくなるほど利子が膨らんで返済総額が多くなります。
また金融機関や地方自治体は審査によって融資先の返済能力を確認します。審査の結果によっては十分な金額の資金を調達できなかったり、場合によっては資金調達自体ができなかったりすることがある点もデメリットです。
出資による資金調達のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
出資の場合は返済義務がないことが大きなメリットです。また、議決権を有する出資者は経営に介入する権利があります。そのため出資者から会社を成長させるためのアドバイスや、事業パートナーの紹介を受けられる点もメリットだといえます。
一方で、第三者が介入できる分、自分で思い通りに経営方針を決められない恐れがあります。複数の株主がいる場合は、経営権が分散して方針が定まらなくなるリスクにも注意が必要です。
資産活用による資金調達のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
不動産や借地権といった資産を売却する場合、融資のように返済能力についての審査を受ける必要がありません。そのため会社の信用度にかかわりなく資金調達できます。また出資と同様に返済の義務がないこともメリットです。
しかし、そもそも資産を保有していない場合、アセットファイナンスによる資金調達はできません。そして不動産売却の仲介手数料やファクタリングの手数料など、現金化のためには各種手数料がかかる点も把握しておく必要があります。
その他の資金調達方法

ここまで解説してきた代表的な方法の他にも、いくつかの資金調達方法があります。例えば以下の3つです。
- 助成金・補助金を利用する
- クラウドファンディングを活用する
- 自己資金を投入する
それぞれ以下に詳しく解説します。
助成金・補助金を利用する
特定の条件を満たしていれば、助成金・補助金によって資金調達できます。代表的な例は以下の通りです。
| 名称 | 管轄 | 概要 | 補助金額上限・補助率等 |
|---|---|---|---|
|
小規模事業者持続化補助金 |
商工会議所 |
小規模事業者の販路開拓や生産性向上を支援する制度。 |
|
|
地域デジタルイノベーション促進事業 |
経済産業省 |
地域の特性や強みとデジタル技術をかけ合わせ、新たなビジネスモデル構築に向けて地域企業等が行う実証事業に要する費用を補助する取り組み。 |
|
|
キャリアアップ助成金 |
厚生労働省 |
非正規雇用者のキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善に取り組んだ事業主に対して支給される助成金。 |
<例>大企業以外の正社員コース(有期→正規雇用):1人あたり80万円 |
- *記載内容はいずれも2024年8月時点での情報です。
上記以外にも助成金・補助金には様々な種類があります。自治体で独自に設けている助成金・補助金もあるため、自治体のウェブサイトなどを確認して利用可能なものがないか探してみましょう。
国や地方自治体、民間団体などから支給される補助金・給付金には返済義務がないことが大きなメリットです。ただし特定の条件を満たし、かつ審査に通過しないと受給できません。申請時は概要や要件を細かくチェックして、審査に向けて申請書や書類を用意する手間がかかります。
クラウドファンディングを活用する
クラウドファンディングは、専用のサイトを通じて不特定多数の投資家からお金を集める方法です。プロジェクト公開は誰でもできるため、ここまで紹介してきた方法よりも手軽に資金を調達できます。
一方で、出資者から見て魅力的なプロジェクトでなければ目標金額に到達するのが難しいという側面があります。そのため支援者のメリットを考えたり、募集ページを作り込んだりなど、プロジェクトに注目を集めるための工夫が必要です。
またクラウドファンディングは、リターンの内容によっていくつかの種類があります。主な種類は購入型・寄付型・投資型の3つです。それぞれのリターン内容の違いについては以下の表をご参照ください。
| 種類 | リターン内容・特徴 |
|---|---|
|
購入型 |
支援者に対して商品やサービスを提供する。支援者にとっては未発売の商品を先行して購入できるなどのメリットがあるため支援者を集めやすい。 |
|
寄付型 |
お礼や活動報告のみで、支援者へのリターン義務はない。支援者を集めるハードルは高い。 |
|
投資型 |
利益が出た場合、支援者に分配する。株式への出資者を公募する形で支援者を集める。 |
- *本稿の内容については一般的な情報であり、必ずしもみずほ銀行の見解を示すものではありません。
利用するクラウドファンディングサービスによって、利用できる募集形式が異なります。まずはどのようなサービスがあるのか探してみましょう。
自己資金を投入する
自己資金はその名の通り、自分の預金を事業資金に充当する方法です。家族や友人から資金を借りる場合も含まれます。資金調達の中で最も基本的でシンプルな方法といえるでしょう。
自己資金が少ない状態では、融資や出資を受けられない場合もあり、最低限の自己資金は準備しておく必要があります。創業資金を準備する場合は、最低でも創業資金総額の3分の1程度は自己資金として準備しておきましょう。
なお、個人事業主とは異なり、法人を設立するにあたって会社と個人の資金は別で管理しなければなりません。個人事業主であれば事業収入から個人的な生活費を支払っても何ら問題ありませんが、法人を設立する場合は、会社のお金を代表の個人的な使途で扱うことはできないのです。
法人設立時は資金面で余裕を持たせるために手持ちのお金の内なるべく多くを法人に注ぎ込みたくなる場合もありますが、一方で個人的な生活資金も確保しておく必要があります。そのため、手持ちの資金をすべて会社の資金とするのではなく、必要な生活資金は残しておきましょう。
資金調達の方法を選ぶうえで考慮しておくべきポイント

資金調達をスムーズに行うためには以下の点を考慮したうえで利用しましょう。
資金調達にかかるコストを考慮する
資金調達にはそれぞれコストがかかります。融資には利子がかかる点が特徴です。出資は資金の返済が不要で、コスト面では一見融資より有利に見えますが、配当金の支払や株主名簿管理、株主総会の開催・通知といった事務手続、出資を受けるにあたって会計・税務分野の専門家や仲介者を頼ることがあればその手数料などが必要になります。
また同じ融資、同じ出資でもかかる金額は異なります。創業したばかりの企業を支援する自治体の融資制度などもあるため、幅広い選択肢から比較検討して、有利な資金調達方法を見つけましょう。
お金以外の要素も十分に検討する
資金調達する際は、お金の面だけではなくそれに付随する要素も検討しましょう。例えば事業会社による出資なら、業務的な提携や取引先紹介、技術支援が受けられるかもしれません。また金融機関からの融資や投資家からの出資の場合に、人材や知見の紹介が受けられたり、経営のアドバイスがもらえたりすることがあります。
これらは将来的に事業を成長させる要素なので、会社の利益につながることが期待できるでしょう。
ラウンドに応じた手法を選ぶ
スタートアップ企業の成長段階を表す以下のような「資金調達ラウンド(投資ラウンド)」に応じた方法を選ぶことも大切です。
- エンジェル:創業前後のアイデア段階
- シード:商品・サービスのリリース前後
- シリーズA:商品・サービスのリリース~ユーザー拡大段階
- シリーズB:収益が伸び、ビジネスが軌道に乗り始めた段階
- シリーズC以降:黒字で経営が安定する時期
まだ実績がないエンジェルの段階では、事業計画や将来性を重視する「日本政策金融公庫からの融資」や「エンジェル投資家からの出資」が適している可能性があります。
一方でシリーズC以降は、安定的な返済が求められる「金融機関からの融資」と親和性が高くなります。このようにラウンドに合った方法を知ることで、スムーズに資金調達を受けられる可能性は高くなるでしょう。
まとめ

会社の設立や事業の拡大のために欠かせない資金調達には、融資や出資、資産活用といった様々な方法があります。それぞれ特徴やメリットが異なるため、適切な選択をするためには経営状況や調達目的に合わせた判断が必要です。本記事で解説した内容を参考にしながら、計画的に資金を調達しましょう。
資金調達などで得た「法人のお金の管理」には法人名義の銀行口座があると便利です。個人のお金と分けて管理できるので、経理業務の負担が減らせるというメリットもあります。
みずほ銀行の法人口座なら、店舗だけでなく非対面での申込も可能です。起業や資金調達にあたって法人名義の銀行口座を開設する際には、みずほ銀行でのお申込をご検討ください。
(記事提供元:株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ)
- *本稿に含まれる情報の正確性、確実性あるいは完結性をみずほ銀行が表明するものではありません。
また、個別の表現については、必ずしもみずほ銀行の見解を示すものではありません。
最新の情報をご確認のうえ、ご自身でご判断いただくようお願いいたします。
執筆者

宮崎 千聖
金融メディアを中心に執筆・監修者として活動するファイナンシャル・プランナー。銀行員としてローンの相談や融資の手続き、企業の財務チェックなどを経験。
保有資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士