法人の消費税とは?課税対象・計算方法・納税方法からインボイス制度まで解説
掲載日:2025年11月6日起業準備
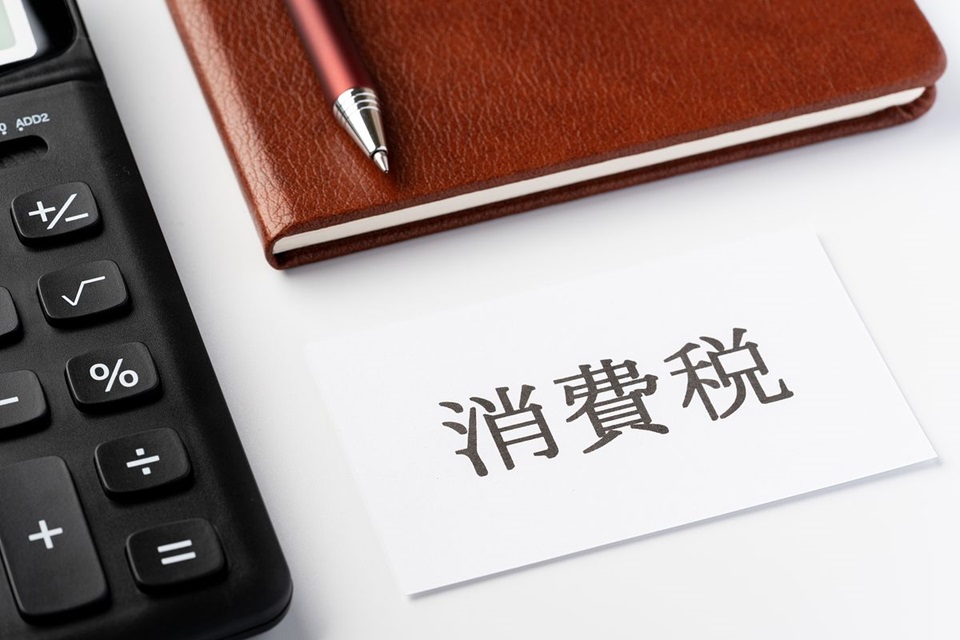
目次
法人の経営において、消費税の理解と適切な対応は重要です。単に売上にかかる税金と認識していると、想定外の納税額の増加や税務調査で指摘を受けるリスクがあります。
本記事では、消費税の概要や課税事業者と免税事業者の違い、計算方法、インボイス制度が法人に与える影響を解説します。消費税の申告・納税手続きや法人消費税を抑えるポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
<最短翌営業日に開設>来店不要で休日・夜間も受付中!
法人口座開設のお申込方法やお得な特典等の詳細は、以下のページをご確認ください。
消費税とは
消費税とは、商品やサービスの消費に対して課される税金です。消費者が買い物やサービスを利用する際に、消費税を事業者に支払います。
しかし、税務署への納税義務を負うのは消費者ではなく、法人や個人事業主の事業者です。事業者は、商品やサービスを販売する際に消費者から消費税相当額を受け取り、自社の仕入れや経費で支払った消費税を差し引いて国に納めます。
法人にとって消費税は、売上の一部として一時的に受け取る「預り金」のようなものです。法人経営者には、預り金を正確に計算し、適切に管理・納税することが求められます。
消費税の課税対象となる取引
原則として、消費税の課税対象となるのは、日本国内で行われる以下のような取引です。
- 事業者が事業として行い、対価を得て行う資産の譲渡や貸付、役務の提供
- 外国貨物の輸入
資産の譲渡や貸付には、商品の販売や会社の建物の売却、特許権の譲渡、オフィスや機械、自動車等を貸し付けて賃料を得る行為が該当します。役務の提供には、運送業や広告業、清掃業、仲介業、美容院、飲食店等のサービスに加え、税理士、弁護士等の専門家が行うサービスも含まれます。
海外から商品を輸入する場合も、消費税の課税対象となります。消費税は、国内で消費されるものに対して課されるため、事業者や個人が海外から商品を購入する際にも課税されます。
消費税が課されない取引
消費税が課されない取引は、大きく以下の3つに分けられます。
| 区分 | 内容 | 具体的な取引例 |
|---|---|---|
|
非課税取引 |
社会政策上の理由や取引の性質により、法律上、消費税を課さないこととされている取引 |
|
|
不課税取引 |
そもそも消費税の課税対象とならない取引 |
|
|
免税取引 |
国外での取引として特別に消費税が免除される取引 |
|
免税取引は、非課税取引や不課税取引と会計処理が異なります。免税取引は、輸出など国外での消費を前提としているため、国内での消費税は課されません。
しかし、商品を製造・販売するために国内で要した仕入れや経費には消費税が含まれています。免税取引の場合、売上にかかる消費税は課されませんが、仕入れで支払った消費税は「仕入税額控除」の対象となり、控除できます。
仕入税額控除とは、事業者が納めるべき消費税額を計算する際に、仕入れ等で支払った消費税を差し引く仕組みです。免税取引の場合は、仕入税額控除によって消費税の還付を受けることができます。
一方、非課税取引や不課税取引は、そもそも消費税の課税対象ではないため、仕入税額控除の適用はありません。
課税事業者と免税事業者の違い
法人は、消費税の納税義務の有無によって、「課税事業者」と「免税事業者」に分けられます。どちらに該当するかによって、消費税の取り扱いが大きく変わるため、自社の状況を正確に把握しておきましょう。
課税事業者とは
課税事業者とは、消費税の納税義務がある事業者を指します。原則として、以下のいずれかの要件を満たす場合に課税事業者となります。
- 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える法人
- 特定期間の課税売上高および給与等支払額が1,000万円を超える法人
- 新設法人で、事業年度開始日の資本金額が1,000万円以上の法人
- 特定新規設立法人に該当する法人
- 任意で課税事業者を選択した法人
- 適格請求書発行事業者として登録した法人
基準期間とは、法人の場合、原則としてその事業年度の前々事業年度を指します。この期間の課税売上高が1,000万円を超えると、その事業年度は課税事業者となります。
特定期間とは、その事業年度の前期の開始日から6ヵ月間のことを指します。この期間の課税売上高または給与等支払額が1,000万円を超えた場合、課税事業者となります。
設立時の資本金が1,000万円以上の法人は、設立初年度から課税事業者となります。資本金が1,000万円未満の新設法人は、設立1期目と2期目は原則として免税事業者です。しかし、2期目の特定期間の売上高および給与等支払額が1,000万円を超えれば、3期目から課税事業者になります。
また、「特定新規設立法人」に該当した場合は設立時の資本金が1,000万円未満でも課税事業者となります。大企業の子会社として設立されたような場合に「特定新規設立法人」とする場合があるので注意しましょう。
課税売上高が1,000万円以下で本来は免税事業者となる場合でも、「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば、課税事業者を選択することができます。これは、多額の設備投資をした場合や、輸出取引が多い場合等、支払った消費税の還付を受けたいときに有効な手段です。ただし、一度選択すると、原則として2年間は免税事業者に戻れないため、慎重な検討が必要です。
また、インボイス制度における適格請求書発行事業者として登録した法人は、全て課税事業者になりますのでご注意ください。
免税事業者とは
免税事業者とは、消費税の納税義務が免除される事業者を指します。原則として、基準期間における課税売上高および特定期間における課税売上高または給与支払総額がいずれも1,000万円以下の事業者が該当します。
免税事業者は消費税を国に納める義務がないため、事務負担が少ない等のメリットがある一方、仕入れや経費で支払った消費税については、国から還付を受けることができません。
消費税の計算方法
消費税額の計算方法には、大きく分けて「原則課税方式」と「簡易課税方式」の2種類があります。どちらの方式を適用するかによって、納税額や経理処理の負担が大きく変わるため、自社に最適な方法を選択しましょう。
原則課税方式
原則課税方式は、消費税の計算における基本的な方法であり、以下の計算式で算出されます。
計算式
納税額=預かった消費税額ー支払った消費税額
原則課税方式では、各仕入れにかかる消費税額を正確に把握し、帳簿に記録しなければなりません。また、仕入税額控除の要件となる請求書や領収書等の保存が必要です。
簡易課税方式
簡易課税方式は、経理処理の事務負担を軽減するために設けられた特例措置です。簡易課税方式を適用するためには、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下でなければなりません。また、事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません。
簡易課税方式における消費税の計算方法は以下の通りです。
計算方法
納税額=預かった消費税額ー(預かった消費税額×みなし仕入率)
簡易課税方式では、実際に支払った消費税額を計算する代わりに、預かった消費税額に業種ごとに定められた「みなし仕入率」を乗じて計算した金額を仕入税額とみなして控除します。
| 事業区分 | 業種 | みなし仕入率 |
|---|---|---|
|
第1種事業 |
卸売業 |
90% |
|
第2種事業 |
小売業、食品販売をする農業・林業・漁業 |
80% |
|
第3種事業 |
飲食料品の譲渡をしない農業・林業・漁業、建設業、製造業等 |
70% |
|
第4種事業 |
その他の事業(飲食店業等) |
60% |
|
第5種事業 |
金融・保険業、運輸通信業、サービス業 |
50% |
|
第6種事業 |
不動産業 |
40% |
簡易課税方式は、事務負担の軽減だけでなく、場合によっては納税額を抑えられるメリットもあります。しかし、一度選択すると原則として2年間は変更できないため、長期的な事業計画を踏まえて慎重に判断しましょう。
インボイス制度が法人消費税に与える影響
2023年10月1日から導入されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、法人の消費税実務に大きな影響を及ぼしています。
以下では、課税事業者および免税事業者に対する影響について解説します。
課税事業者への影響
インボイス制度導入後、仕入税額控除の適用要件は大きく変化しました。原則として、仕入れや経費にかかる消費税を控除するためには「適格請求書発行事業者」が発行した「適格請求書(インボイス)」の保存が必要です。
インボイス制度の導入により、課税事業者は仕入先が適格請求書を発行できる事業者であるかを確認する必要が生じ、事務負担が増えました。また、免税事業者からの仕入れでは、原則として控除が認められないため、実質的なコスト増につながります。
課税事業者には、経理システムや業務フローの見直し、取引先との連携強化が求められています。
免税事業者への影響
インボイス制度は、免税事業者の事業継続に大きな影響を与える可能性があります。免税事業者は「適格請求書発行事業者」に登録しない限り、適格請求書(インボイス)を発行できません。そのため、取引先の課税事業者は、免税事業者からの仕入れにかかる消費税について仕入税額控除の適用を受けられなくなります(ただし、経過措置あり)。
免税事業者は、取引先から取引価格の引下を求められたり、取引自体を見直されたりする可能性があるでしょう。免税事業者のまま事業を続けるか、適格請求書発行事業者として登録して課税事業者になるかの判断が求められます。
法人消費税の申告・納税手続き

消費税は、正確に計算し、期限内に申告・納税しなければなりません。手続きを怠ると、加算税や延滞税が課される可能性があるため、申告・納税期限や必要書類を事前に確認しておきましょう。
消費税の申告・納税期限
課税期間は原則として1年であり、法人の事業年度と一致します。法人の消費税の申告・納税は、原則として課税期間の終了日の翌日から2ヵ月以内です。例えば、3月決算法人の場合、申告・納税の期限は5月末日となります。
前期の消費税額が一定額を超える法人は、年間の申告・納税とは別に、課税期間中に中間申告および納税を行う必要があります。中間申告は、通常、直前の課税期間の消費税額を基に計算される「予定申告」の形で行われますが、仮決算による申告も認められています。
必要書類
法人消費税の申告・納税手続きに必要な書類は、適用する課税方式によって以下のように異なります。
| 課税方式 | 必要書類 |
|---|---|
| 原則課税 |
|
| 簡易課税 |
|
| 2割特例 |
|
インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった事業者は、2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の適用対象となります。申告ごとに適用の有無を選択でき、2023年10月1日から2026年9月30日までの各課税期間において適用可能です。
ただし、インボイス制度開始前から課税事業者であった事業者や、資本金が1,000万円以上の新設法人などは、2割特例の適用対象外となります。
法人消費税の申告・納税が遅れた場合のペナルティ
法人消費税の申告・納税が遅れた場合、以下のようなペナルティが課される可能性があります。
| ペナルティ | 概要 |
|---|---|
|
延滞税 |
申告・納税が遅れた場合に課される。納付期限の翌日から実際に納付した日までの期間に応じて課され、納付が遅れる期間が長くなるほど高くなる。 |
|
無申告加算税 |
申告書の提出が遅れた場合に課される |
|
過少申告加算税 |
申告はしたが納税額が少なかった場合に課される |
|
重加算税 |
意図的な仮装や隠蔽があったと判断された場合に課される |
ペナルティを回避するためにも、申告・納税は期限内に正確に行うことが重要です。万が一申告を忘れていた場合は、できるだけ早く申告を行いましょう。
法人消費税を抑えるポイント
消費税は「預り金」という性質上、法人税のように直接的な節税対策は限られます。しかし、仕組みを正しく理解し、適切に制度を選択することで、納税額を抑え、不必要な支出を避けることが可能です。
以下では、法人消費税を抑えるためのポイントを紹介します。
簡易課税制度を適切に活用する
簡易課税制度は、事務負担の軽減に加え、納税額を抑えられる可能性があります。特に、以下のケースでは簡易課税の選択を検討する価値があります。
- みなし仕入率が高い業種(卸売業90%、小売業80%等)で、実際の仕入率が低い場合
- 多額の設備投資をせず、消費税の還付が見込まれない場合
ただし、一度選択すると原則として2年間は変更できないため、長期的な事業計画を踏まえた慎重な判断が求められます。
専門家に相談する
消費税の計算や申告は複雑であり、税法の改正も頻繁に行われます。特にインボイス制度のような大きな変更があった場合には、税理士などの専門家に相談することで、最新情報に基づいて自社に適した対策を講じることができます。
税務リスクの軽減や適切な節税対策の提案、税務調査への対応等、多くのメリットがあるため、自社での判断が難しい場合は、専門家への相談を検討しましょう。
消費税の適切な管理には法人口座の活用がおすすめ
消費税の適切な管理と申告は、法人経営において重要です。消費税の課税事業者となった場合や将来的な事業拡大を見据えるなら、法人口座の開設が推奨されます。
法人口座があれば、事業の収支が明確になり、消費税額の把握や納税資金の管理がしやすくなります。また、金融機関からの信用を得やすくなる等、事業の成長にもメリットがあります。
法人口座を開設するなら、みずほ銀行がおすすめです。みずほ銀行の法人口座は、オンラインでの申込とウェブ面談に対応しています。さらに、法人口座開設ネット受付では、登記事項証明書・印鑑証明書の原本提出が不要なため、書類準備の手間を軽減できます。
なお、一部のお客さまは、店舗での対応が必要な場合があります。
まとめ
法人にとって消費税は、事業を営むうえで避けては通れない重要な税金です。課税事業者と免税事業者の違いを理解し、自社にとって最適な課税方式を選択することが大切です。
インボイス制度の導入は、今後の仕入税額控除に影響するため、自社の状況に応じて適切に対応する必要があります。消費税に関する不明点や不安がある場合は、税理士等の専門家に相談することが有効です。
消費税を適切に管理するために法人口座を作る際は、来店不要で開設可能なみずほ銀行の口座開設をご検討ください。
<最短翌営業日に開設>来店不要で休日・夜間も受付中!
法人口座開設のお申込方法やお得な特典等の詳細は、以下のページをご確認ください。
監修者

安田 亮
- 公認会計士
- 税理士
- 1級FP技能士
1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。