農業法人設立のメリット・デメリットは?農家の法人化に必要な基礎知識を解説
掲載日:2025年9月29日起業準備

農業の形態には、個人で営む農家の他に、農業法人を設立するという選択肢もあります。
農業法人を設立することで、社会的信用の向上や経営管理の合理化などのメリットが期待されることから、近年は農業法人数が増加傾向にあります。しかし、設立には、一般的な法人と同様に複雑な手続きが必要であり、条件によってはデメリットとなる点への理解も必要です。
本記事では、農業法人設立で知っておきたい基本事項や個人農家との違い、メリット・デメリット、具体的な設立方法等を紹介します。
来店不要でいつでも開設可能(メンテナンス時間:日曜日 0時00分~9時30分を除く)
目次
農業法人とは
農業法人とは、田畑や果樹園のような土地利用型農業、施設園芸、畜産等の農業を運営する法人の総称です。
農業法人は主に2種類に分かれます。
- 会社法に基づいて設立される法人(株式会社・合同会社・合資会社・合名会社で、一般的な営利企業と同様の形態)
- 農業協同組合法に基づいて設立される法人(農事組合法人等)
これらの法人形態のうち、農地法に基づく要件を満たし、農地の所有が認められる法人は、農地所有適格法人と呼ばれます。
個人が営む農家と農業法人には、運営形態が個人事業主か組織かという違いがあります。
-
個人農家
農業で生計を立てている個人事業主で、「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を税務署に提出すれば開業できます。一般的に家族経営が多く、収入は個人所得となります。 -
農業法人
一般的な企業と同様に、組織のルールを定めた定款の作成や役員の選任、出資金(資本金)の払い込み等の手順を経て設立されます。法で認められた組織として、法人税の適用や社会保険への加入義務等、多くの点で個人農家と異なります。
個人で農業を営むか、農業法人を運営するかは、事業の状態や計画に合わせて選ぶと良いでしょう。
農業法人の種類

農業を営む法人組織の総称である農業法人は、組織の目的や状況によって、次の3種類に分類されます。
- ①一般農業法人
- ②農地所有適格法人
- ③農事組合法人
以下では、3種類の農業法人の特徴を解説します。
一般農業法人
株式会社や合同会社、合資会社、合名会社として農業を営む法人は、一般農業法人(あるいは農業法人)と呼ばれます。ただし、狭義では農地を所有しない農業法人を指し、養鶏や養豚等の畜産業、観賞用植物等を育てる施設型農業等、田畑や牧草放牧地等の農地を利用しない農業を営む法人を指します。
農地を所有せずに貸借地を利用する場合には、農業法人ではない一般企業でも農業に参入することが可能です。ただし、農地の賃貸借契約に解約条件が付されている、業務執行役員らが継続して農業に従事している等、一定の要件を満たす必要があります。
農地所有適格法人
農地所有適格法人とは、一般農業法人のうち、農地法が定める要件を満たし、農地を所有して農業を営む法人を指します。例えば、法人として水田を所有して稲作に取り組むには、農地所有適格法人の要件を満たさなければなりません。
また、法人が農地を所有するには、農地所有適格法人の要件を満たしたうえで、自治体に設置されている農業委員会からも許可を得る必要があります。
農事組合法人
農事組合法人とは、農業協同組合法(農協法)に基づき、農業を営む個人らを組合員として設立される共同組織です。組合員が協力し合って農業を行うことを目的としており、法人から組合員に対して給与は支払われません。これは、個人事業主による相互扶助を目的として設立される法人です。
農事組合法人の事業は次のように限定されます。
- ①農業に関連した共同利用施設の設置、農作業の共同化に関する事業を行う(1号法人)
- ②農業を営む法人(2号法人)
- ③①と②に付随する事業
1号法人は農業を直接経営しないため、農地法の農地所有適格法人には該当しません。一方で、2号法人は農地取得が可能であり、農事組合法人でありながら農地所有適格法人にも該当します。
また、利益の追求ではなく、協業を目的としていることから、法人設立時の登録免許税や事業税が非課税になる等、税制面の優遇を受けられます。
農業法人の組織形態ごとの割合
農林水産省による報告書では、農業法人の組織形態ごとの割合は以下のように示されています※。
| 農業法人の組織形態 | 経営体数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
|
一般農業法人 |
株式会社 |
18,942 |
69.4% |
|
合同会社・合資会社 |
168 |
0.6% |
|
|
合名会社 |
867 |
3.2% |
|
|
農事組合法人 |
7,329 |
26.8% |
|
|
計 |
27,306 |
100% |
|
上記のデータからは、農地所有適格法人を含む一般農業法人の数は19,977団体、農事組合法人は7,329団体であり、全体の7割以上が一般農業法人として農業を運営していることが分かります。また、全体の69.4%を株式会社が構成しています。
農業法人設立のメリット
農業法人には一般農業法人、農地所有適格法人、農事組合法人があり、それぞれに特徴が異なるため、期待されるメリットも変わります。
前述のデータによると、設立される農業法人の7割以上は一般農業法人であり、その多くが株式会社を選択しています。そこで、株式会社としての設立を想定し、農業法人設立における主なメリットを紹介します。
会計管理が明確になる
農業を法人化すると、複式簿記による正確な会計処理に加え、貸借対照表(B/S)や損益計算書(P/L)等の財務諸表等の作成が義務づけられます。経理にかかる負担は増しますが、個人と法人の会計が分離されるため資金の流れが明確になり、経営の透明性が向上します。
その結果、対外的な信頼が高まり、取引先の新規開拓や融資の可能性が高まると期待されます。また、経営管理をスムーズに進めやすくなり、事業拡大や生産性向上等のより良いパフォーマンスの実現につながるでしょう。
社会保険制度を利用できる
法人になると、従業員数に関わらず、社会保険制度(厚生年金保険・健康保険・労災保険・雇用保険等)への加入が義務づけられます。通常、個人事業主は従業員が5人未満であれば、社会保険制度への加入義務はありません。しかし、個人農家の場合は従業員が5人以上でも健康保険・厚生年金の強制適用業種に含まれません。
社会保険制度の加入には、年金事務所やハローワーク等での手続きが必要です。
社会保険制度を利用することで、従業員の福利厚生や健康管理の充実に加え、退職後の生活への備えも可能です。安心で充実した労働環境が整うと、良質な人材の確保や従業員のモチベーション向上につながり、持続的な農業運営にも寄与します。
事業をスムーズに承継できる
個人農家の場合、農業を営む本人が死亡した場合には、家族や親族による相続によって農業が引き継がれます。しかし、近年は農業を引き継ぐ人がみつからないケースが多く、さらに農地の分散や相続税の負担の大きさ等から、農地の相続に悩む人も増えています。
しかし、農業法人を設立すると、第三者へ農業を承継しやすくなります。農地や機械・設備、培ってきたノウハウ、取引先や従業員等の関係者も含めた事業承継が可能です。そのため、農業の継続や発展に意欲ある人材を後継者に迎えることで、事業を円滑に引き継げるでしょう。
税制面の優遇を受けられる
農業法人を設立すると、個人農家とは異なる税金が適用されます。事業規模や所得によっては、農業法人の方が税負担を軽減できる可能性があります。
例えば、個人農家に課される所得税は累進課税で、税率は5~45%です。課税所得が695万円を超えると23%、900万円を超えると33%が課されます。一方、法人税は事業の種類や規模に応じた定率課税です。資本金1億円以下の法人の場合、課税所得800万円を超える部分の税率は23.2%、800万円以下の部分の税率は15%(一定の条件下では19%)となります。
そのため、課税所得が800~900万円程度の場合には、農業法人の方が個人農家よりも税率を抑えられる可能性があります。さらに、農業法人は、各種税額控除や経費算入、最長10年間の欠損金の繰越控除等の優遇を受けられます。
ただし、農業法人になると、赤字であっても法人住民税の均等割を納付しなければならず、メリットばかりではない点に注意が必要です。
融資限度額が増える
農業法人になると、農業経営者向け融資において、個人農家よりも限度額が増額されることがあります。融資額が増えることで、設備の導入や事業の安定に寄与するでしょう。
例えば、日本政策金融公庫「スーパーL資金(農業経営基盤強化資金)」の融資限度額は、個人が3億円(特定の条件下では6億円)、法人が10億円(特定の条件下では30億円)です。さらにこの融資では、法人を対象とした「無担保・無保証人制度」を条件付きで利用できます。
農業法人設立のデメリット
メリットと同様に株式会社を想定して、農業法人設立に伴うデメリットの可能性も確認しておきましょう。
法人設立の手続きに時間や負担がかかる
個人農家を営む場合、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届)を提出します。個人事業税の対象であれば、都道府県税事務所や自治体の窓口に「事業開始等申告書」を提出する必要があります。これらの手続きが完了すれば、個人事業主としての開業が可能です。早ければ即日中に農家として開業できます。
それに対して、農業法人として株式会社等を設立するには、定款の作成や法務局での登記等、複数の手続きを経なければなりません。設立までに数週間はかかるのが一般的で、準備や手続きに時間や負担がかかります。
設立時や運営にコストが発生する
農業法人設立には、登録免許税や定款認証費用等にコストがかかります。
- 登録免許税:株式会社の場合、資本金額の0.7%(ただし申請件数1件につき最低15万円)
- 定款認証費用:株式会社の場合、認証手数料1.5万円から5万円、印紙代4万円(電子定款は印紙代不要)等
このように、株式会社として農業法人を設立する際は、出資金とは別に、最低でも約20万円の準備が必要です。さらに、法人設立後に税理士に税務を依頼する場合は、報酬の支払いが必要となることもあります。
農地所有適格法人は適用要件が厳しい
農業法人として農地を所有するには、農地所有適格法人となるための一定の要件を満たし、各自治体に設置されている農業委員会から許可を得なければなりません。
| 法人形態 |
株式会社(公開会社でないもの)、合名会社、合資会社、合同会社、農事組合法人のいずれか |
|---|---|
| 事業内容 |
主たる事業が農業で、売上の半分以上が農業によるものであること |
| 議決権 |
農業関係者が総議決権の過半数以上を占めること |
| 役員 |
役員の過半数が農業に常時従事しており、役員のうち1人以上が農作業に従事していること |
| 法人形態 |
|---|
|
株式会社(公開会社でないもの)、合名会社、合資会社、合同会社、農事組合法人のいずれか |
| 事業内容 |
|
主たる事業が農業で、売上の半分以上が農業によるものであること |
| 議決権 |
|
農業関係者が総議決権の過半数以上を占めること |
| 役員 |
|
役員の過半数が農業に常時従事しており、役員のうち1人以上が農作業に従事していること |
許可を得て農地を取得した後も、農地所有適格法人としての要件に適合していることを確認するために、毎年、事業年度の終了から3ヵ月以内に各自治体の農業委員会への報告が義務づけられています。
廃業にも複雑な手続きやお金が必要になる
設立した農業法人を解散し、事業を廃業するには、株主総会での決議や法務局での解散登記、官報公告、設備の処分や農地の原状回復等、多岐にわたる手続きが必要です。
また、解散登記に伴う登録免許税3万円、清算人の選任登記にかかる登録免許税9,000円、官報公告約3万円等、設立時だけではなく廃業時にも諸費用が発生します。さらに、税務申告や各種報告書の提出では専門的な知識が必要となるため、弁護士や税理士への依頼、報酬費用も準備しなければなりません。
農業法人設立の具体的な手続き
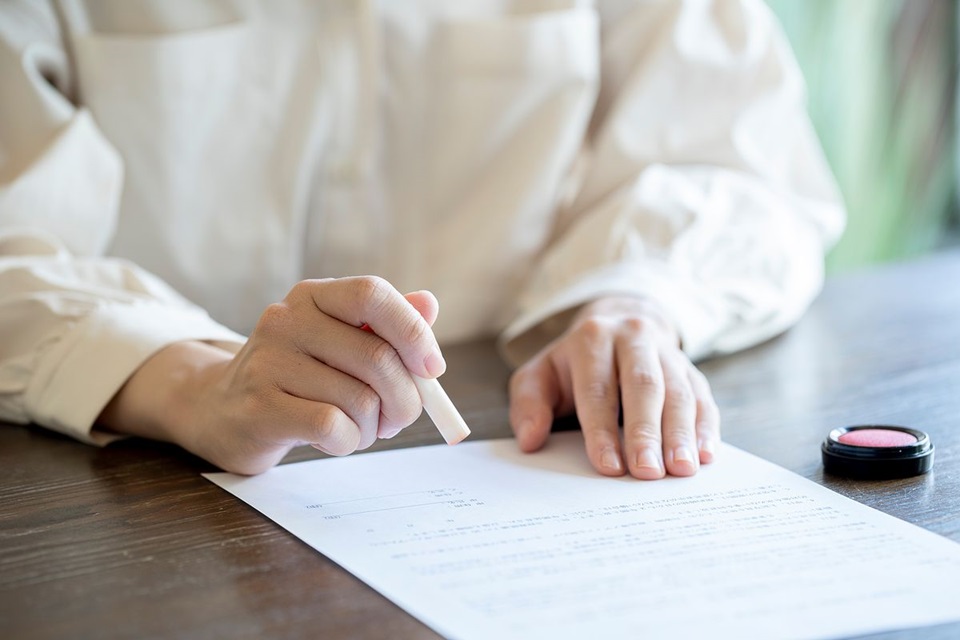
農業法人設立には具体的にどのような手続きが必要になるのか、農業法人の中でも割合が高い、株式会社と農地所有適格法人を例として解説します。
①法人の形態を決める
まず、発起人を中心として、法人の形態等、農業法人としての基本事項を決定します。
- 主な基本事項:組織形態(株式会社等)・法人名(商号)・資本金額・本店所在地・事業内容・役員構成・株式比率(株式会社では発起人による1株以上の出資が必要)・決算期等
基本事項は後に行う「定款の作成」や「出資金の払い込み」にも影響するため、明確に定めておくことが重要です。
②定款を作成する
定款とは、会社の運営方針やルールを定める基本的な規約文書です。法定の絶対的記載事項があるため、漏れなく記載しなければなりません。また、農地所有適格法人としての要件を満たすには、定款に株式の譲渡制限の定めを記載する必要があります。
作成した定款は農業法人の本店所在地管内にある公証役場へ提出し、法令上の不備がないかを確認を受けたうえで、公証人から認証を受けます。公証人による認証には、1.5万円から5万円程度の認証手数料がかかります。
③出資金(資本金)を払い込む
定款の認証が終わったら、出資金(資本金)を払い込みます。株式会社の場合は、引き受けた株数に相当する金額を出資金となります。
この時点では農業法人設立が完了していないため、金融機関で法人口座を開設できません。そのため、出資金は発起人の個人口座に振り込むのが一般的です。口座への振り込みが出資金の払い込みの証明となるため、個人口座内に出資金額以上の預金があっても、いったん引き出したうえで出資金として入金しましょう。
出資金を入金後、通帳のコピー等で農業法人の登記に必要となる「払い込みを証する書面」を作成します。
④役員を一人以上選定する
出資金を払い込んだら、発起人は速やかに、取締役等の役員を最低一人以上選定しなければなりません。取締役会を設置する農業法人とするには、3人以上の取締役の選定が必要です。また、発起人は自分自身を役員に選ぶこともできます。
農地所有適格法人を設立する場合は、選任する役員の半数以上が原則として年間150日以上、農業に従事していること、かつ役員または重要な使用人の1人以上が農業に年間60日以上、必要な農作業に常時従事していること等の要件を満たす必要があります。
⑤法務局で法人として設立登記する
農業法人をはじめとする法人の設立登記は、本店所在地を管轄する法務局で行います。
法人の設立登記には、株式会社設立登記申請書、登録免許税の収入印紙貼付台紙、定款、設立時取締役の就任承諾書、取締役の印鑑証明書、払い込みを証する書面、印鑑届書等の書類提出が必要です。定款の記載内容や役員の人数によって必要書類は変わるため、事前に確認すると安心です。
同一本店所在地に同一の商号の会社があるかどうか等を詳しく調査されるため、書類に不備がないよう注意しましょう。また、法人登記には、登録免許税として最低15万円(株式会社の場合)がかかります。
申請後、1週間~10日程度で農業法人としての登記が完了します。
⑥諸官庁へ必要な届け出を行う
農業法人を設立後、関係機関に対して必要な届け出を行います。個人農家から法人化した場合は、税務署等で個人事業主の廃業手続きもしましょう。従業員を雇用する農業法人は、労災保険と雇用保険の手続きも忘れず行いましょう。
| 官庁 | 手続き | 主な必要書類 |
|---|---|---|
|
税務署 |
法人設立届出書の提出 |
定款の写しや設立登記事項証明書等 |
|
年金事務所 |
社会保険 |
健康保険や厚生年金保険の新規適用届や被保険者資格取得届 |
|
労働基準監督署 |
労災保険 |
労働保険保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書 |
|
ハローワーク |
雇用保険 |
雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届(加入者全員分)、確認資料(登記簿謄本等)、労働者関係書類(従業員名簿や賃金台帳等) |
また、農地所有適格法人については、申請書を提出し、管轄の農業委員会から許可を得る必要もあります。
⑦銀行で法人口座を開設する
農業法人設立の手続きが完了したら、できるだけ速やかに金融機関で法人口座を開設することがおすすめです。
法人口座の開設手続きでは、履歴事項全部証明書、法人の印鑑証明書、株主名簿等の書類の提出が求められるのが一般的です。法人設立と並行して必要書類の準備を進めておくと、口座開設をスムーズに進められます。
農業法人設立後に想定される資金調達先
農業法人の設立直後は、事業の安定化に向けて、まとまった資金を必要とする機会が増えるでしょう。そこで、想定される資金調達先とそれぞれの特徴を紹介します。
JAバンク
JAバンクは、農業協同組合(JA)が運営する金融機関です。事業の運転資金や設備資金等、主に農業従事者に対する金融サービスを提供しています。JA独自の融資のほか、政府や自治体による農業支援を目的とした制度融資の窓口として利用されています。
農業協同組合法に基づく相互扶助の精神のもと活動しているJAが運営するため、JAバンクは農業経営における有力な相談先の一つです。農業の資金調達に悩んだら、まずはJAバンクに相談しましょう。
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫は政府の出資により運営されており、個人事業主や中小企業への手厚い支援で知られています。一般的な金融機関に比べて低金利の融資が特徴で、無担保での融資が可能な場合もあります。また、農業従事者を対象とする融資、公的な制度融資も扱うため、農業法人設立時にも融資を受けやすいでしょう。
ただし、融資ごとに条件が少しずつ異なるため、対象者や融資限度額、返済期間に注意が必要です。
銀行等の金融機関
他業種の一般的企業と同様に、銀行等の民間金融機関を資金調達先として選ぶのもおすすめです。多種多様な業種への融資に対応しており、農業法人にとっても申し込みやすい環境が整っています。
例えば、JAバンク等の一部の制度融資には、自治体に認定された農業従事者のみを対象とする等の制限が多く、申し込めない場合もあります。
また、銀行等の金融機関からの融資は、まとまった資金の準備にも適しています。
法人口座を開設するならみずほ銀行がおすすめ
農業法人設立後は、銀行で法人口座を開設するのがおすすめです。法人口座を開設することで、社会的信用度が向上し、事業の財務状況を把握しやすくなる等、農業法人としてプラスの作用が期待されます。
銀行での法人口座開設なら、みずほ銀行がおすすめです。全国47都道府県に支店を持つため、法人の設立場所に関わらずお申し込みやすく、口座開設後も事業のサポートをスピーディに受けられます。
口座開設は、インターネットからのお申込やウェブ面談等にも対応しており、法人設立直後の多忙な時期でもスムーズに手続きを進められます。一次審査の結果は最長1週間で通知されるため、迅速な口座開設が可能です。
また、インターネットバンキング(みずほビジネスWEB)は、法人設立3年以内ならお申し込みから最長5年間(通常当初3ヵ月間)月額基本料金が無料です。ほかにも、電子帳票に対応したみずほWEB帳票サービス、法人口座からリアルタイムに決済できるみずほビジネスデビットの無料付帯等があり、法人の複雑な会計管理もスマートに行えます。
まとめ
農業法人には、株式会社や有限会社などの組織形態をとる一般農業法人のほか、農地を保有して事業を行う農地所有適格法人、個人農家による相互扶助の性質を持つ農事組合法人があります。農業法人の7割は一般農業法人や農地所有適格法人が占めています。
農業法人の設立方法は、一般的な会社と大きく変わりません。ただし、農地を所有するには農地所有適格法人の要件を満たし、各自治体の農業委員会から許可を得る必要があります。
農業法人設立には手続きの手間やコストの発生等の負担が伴いますが、税制面の優遇や社会保険制度の適用等によるメリットは大きいでしょう。
来店不要でいつでも開設可能(メンテナンス時間:日曜日 0時00分~9時30分を除く)
監修者

安田 亮
- 公認会計士
- 税理士
- 1級FP技能士
1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応などを経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。